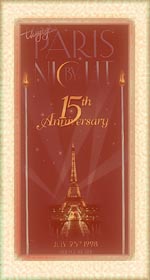
アリーナ同様、ちょっとした歌手紹介をかねて、興味をもったステージを思い出すままに書いてみたい。順番はばらばらだ。
チケットをもらったT氏が「ベトナムで最も素晴らしい男性歌手」と絶賛したのはElvis Phuong。三ツボタンの渋いスーツの彼は50代半ばに見える。マイク一筋何十年といった雰囲気が、ロマンチックなバラッドに込めたソウルとともに伝わってきた。歌心、ここに在り。僕は本当の歌手をみた。
1962年にステージデビューして、68年のレコードデビュー以来、多数の作品を残し続けているという彼は、ロックンロールが好きでエルビスという芸名をつけたのだと言う。しかし歌の幅はその指向を越えて、フォーク、ポップ、バラッドなどに広がる。映画音楽のような声はまさに実力派シンガーだ。
Khanh Lyは前半部に登場した。アリーナとはうってかわって重々しさを前面に出したステージングだった。アコースティック・ギターをフューチャーし、チン・コン・ソンの曲を歌った。
金メッシュの長髪の女性Luu Bichは、バイカー・ファッション(?)風の黒コートに黒皮のブーツ姿で登場。男性ダンサーをとりまきしてロックで踊る。
「こいつはだめだ、そいつもだめだ、どいつもなっちゃいねえよ」
みたいな高飛車パフォーマンスで不良ぶりを発揮。豪華な椅子に陣取り、ダンサーに靴を磨かせるLuu Bich.....僕もそのおみ足に.....おっと(^^);;.......中森明菜のようなキャラクターで面白い。ちょっと前のアメリカン・ロックの女性ヒーローを見ているような気になる。
実はこんなキャラクターでもアルバムでは、重いバラッドを怨念のこもりそうな声で歌ったり、さわやかギターに乗せたアメリカン・カントリーを歌ったりする。初めて聴いたときは、この容貌でこの歌か?!とショッキングだった。Lu Lienを親にKhanh Ha、Tuan Ngocを兄弟にもつ音楽ファミリーで育ち、キーボーディストから歌手へ。ふわりと広がるちょっと鼻声がなんとも魅力ある歌手である。
悪い意味では個性のなさに見えても、V-POPの間口の広さをLuu Bichは体現している。アメリカで育ちつつあるV-POPで、まったくアメリカの影響感覚をなしで聴けるのだとしたら、もしかしたら不自然さも聞こえるかもしれない。その意味でいい。
T氏の奥さんM氏はThe Sonのファンらしく、「The Sonね!」と声をあげ、目を輝かせて前のめりでステージを見つめる。僕は極めて真面目なヴォーカルといったイメージがあったが、イメチェン。おどけ具合がさわやかなステージングだった。
カジュアル姿のThe Sonが登場。静かにバラッドを歌い出した。すると、白のアオザイを着た女子高生がステージに自転車に乗ってやってきた。.......キマシタネ〜、やっぱりこれがないとV-POPは!.......
ゆっくり自転車で進む女子高生が菅かさを""わざとらしく""落とした。そこでThe Son 「おお!お嬢さん、落としましたよ」とこれまた""わざとらしく""拾ってあげるのだ。一瞬見つめ合う二人。頭を下げてステージから去る女子高生。と、その瞬間、すげ笠に白アオザイの女子高生が6人ばかり一斉に自転車で登場。The Sonのまわりをくるくる回り始めたのだった。
ステージですげ笠に白アオザイの女子高生がクルクル自転車で、しかもバラッドのリズムにあわせて回っている姿を想像してみてほしい。かなり笑えると思う(^^);;。その後、The Sonがさっきすげ笠を落とした子を探しながらバラッドを歌ったことは想像に易い。歌だけでなく、懐かしさを笑う明るさの演出もグッドだ。
僕は男性歌手ではThe Sonが一番好きだ。若くて聴きやすい声なうえ、音程も歌いまわしもピカイチ。モダンもトラディショナルも何でもこいである。1987年ごろから活動を開始。サイゴンの国立音楽学校を声楽で卒業し、ギタリストでもある。
24幕中で僕が最も感動したのはAi Vanのステージだ。
バックの大道具は巨大なフエのティエン・ムー寺の絵だ。オレンジ色に照らされた夕方の寺。そこに一人の僧侶が座っている(これはBao Hanだった)。Ai Vanはほうきを持って登場。僧侶と掛け合いながらの歌と話、詩吟による歌劇だ。寺の鐘の音がグオーンとなる。僧侶が木魚を叩く。こうした効果音も楽曲を構成する音の一つになっている。これまでもベトナム文学の傑作といわれるKim Van Kieu(金雲翹)を題材とした音楽作品を発表しているPham Duyの作曲・製作によるものだ。
Pham Duyは前作の完成時に「Kim Van Kieuの音楽を作るにあたり、その詩から浮かび上がる景色を音楽に投影したいのだ。一枚の絵のように」と言っている。
その作品はテクノロジーをふんだんに使い、西洋古典音楽とベトナムの伝統的サウンドやメロディーを大胆に融合させて、Kim Van Kieuのサウンドスケープを実践した現代音楽である。今回は、別の古典文学に題材を借りた新作ということで、同様の流れにある作品であった。
前作でもAi Vanがその透明な声を聞かせていたから、音楽・演出ともに至の境地。幽玄の美と現代的リアリズムが交叉し、音色と色が解け合う作品昇華の空間が広がった。ステージ脇のモニターには最前列に座っていたPham Duyも写し出された。まさに共作だ。
Ai Vanは30代前半ぐらいだろうか。女性。1990年前半までベトナムで歌手として成功し、世界各地でその声を聞かせた後、ドイツに移住し、94年からカリフォルニアで生活。作品多数。
ダンバウやダンチャンなど伝統楽器をバックに歌ったのは女性歌手のHoang Lan。妖零な独特の視線をしている。左右に大きく広がる目に引き込まれそうな感覚を覚える。僕最近の一押しの歌手だ。まさにスペシャルなオアザイで登場し、ベトナム的カントリーソングのノスタルジアで空間を満たしてゆく。若く、決して押しは強くないが、声も歌い方も強烈な個性の持ち主だ。
降臨図(?).......Nhu Quynhはステージ上から飛来して現われた.....昇天の儀(?)
空ろに憂えた表情は何を語っているのだろう。その舞の意味はなんだろう。
古代万葉の似姿の儀か。月夜の嫦娥か。彷徨する徐福伝承か。その涙の訳は「島浮かべども蓬莱を見ず」の嘆きか。神秘な幻想的な舞いに空想は広がる。
ベトナム系批評家 Trinh T Minh-Haの言葉を思い出した。「月の時と呼ばれる瞬間」......つまり......「夜はあらたな目覚めに必要な静けさの時でありつづけるだろう」。Nhu Quynhの歌には、そんな静けさを感じ取ることができる。
中国文化の色濃い日本およびベトナムの古代文化・文学にはこうした共通点を読み取ることができるように思う。「竹取」が媒介とした月と不老不死にこめる世界観・道教思想をかいまみたように思う。越境や希望といった記号の再解釈も込められていることであろう。
もう一つ象徴的なステージがあった。Tommy Ngoのステージだ。いや象徴的というにはあまりにも直接的なステージであった。バックの大道具はマンハッタンの古めかしいアパートだった。
Tommy Ngoとダンサーはウエスト・サイド・ストーリーの一幕を演じたのだ。曲は「America」。プエルトリコ移民が仲間同士で遠く離れた国について言い争う場面の後に流れる曲だ。........「忘れちまったのか。おれたちの国は何もなくても世界一の国さ」「私はマルガリータではなく、アニタ。一度アメリカ人になったら変わらないわ」.........この男女の言い争いの後に流れる「America」はアメリカ移民の物質的豊かさと自由の夢を語り、差別と貧しさの現実で答え、望郷と移住の葛藤を歌ったものである。Tommy Ngoは英語で歌った。曲は 「Life is good in America」と題され、替え歌になった。ベトナム版「America」を演奏するとMCは言った。
「Paris By Night」は15周年にあたり、単に豪華でお金をかけたステージを作り出しただけではなかった。歌手の力やコメディー、芸術、楽器、伝承、類似等の記号をふんだんに用いて、アメリカにおけるベトナム系ポピュラー音楽というアイデンティティの確立をプロデュース成し遂げたのである。この一言で語れない複雑なアイデンティティを、24幕のステージを通じて表現したのである。
|
V-POPというアイデンティティ |