これは、成城大学文芸学部マス・コミュニケーション学科を卒業した時に提出した卒業論文です。
今、振り返ると、これほど単純で幼稚で未熟なものはないなあ、との思いは強いのですが、本を読んだり、文章を書いたりするのに夢中だった頃、そんな頃の小さなお気に入りでもあります。
あの頃は、論文というものが、いったいどういうものかも分かりませんでした。「である」調で書くことですら、ほとんど未経験でありました。ただ、ただ、「書く」ことが楽しみだったのを覚えています。
 しかし、あの頃に読んだ柳田国男や、あるいはさまざまな社会史の類、夢中だったミシェル・フーコーなど現代思想家たち、ロラン・バルトをはじめ文学理論やソシュールのような言語学者や記号論の先駆者たち、アービン・ゴフマンのような刺激的な社会学者たち、アンリ・ルフェーブルとかジャン・ボードルヤールとかアルチュセールとか.......こうした著作に、染みいるような感動を覚え、その衝動は今でも根深く残っています。
しかし、あの頃に読んだ柳田国男や、あるいはさまざまな社会史の類、夢中だったミシェル・フーコーなど現代思想家たち、ロラン・バルトをはじめ文学理論やソシュールのような言語学者や記号論の先駆者たち、アービン・ゴフマンのような刺激的な社会学者たち、アンリ・ルフェーブルとかジャン・ボードルヤールとかアルチュセールとか.......こうした著作に、染みいるような感動を覚え、その衝動は今でも根深く残っています。
大学4年生のときは、2ケ月ほど病に倒れ(といっても、2ケ月で治ってしまったのですが)、そのときにエミール・デュルケイムの著作をむさぼり読んだのを覚えています。宮島嵩先生の訳「社会学的方法の規準」を読んで以来というもの、私は社会学が好きになりました。他にも、いろいろありますが、「そうそう」と思うことがあっても、なかなか書ききれません。
当時、わたしはマスコミ学科に通いながらも、マスコミ論の勉強などほとんどさぼっていました。ですから「内容分析」の方法なんて知りませんでした。社会学といえば「古典」の一種だと思っていました。ですので「カルチュラル・スタディーズ」なんて言葉は聞いたこともありませんでした。
とにもかくにも、「ポップロアを書こう」...........これが当時の思いでした。
今、読むとこんな古くさいものはありませんし、「ポップロア」どころではないありません。でも、たぶん自分のなかでは、なにか目新しいものを書こう、とがんばっていたように思います。わたしは今、マスコミ論を専攻する教員です。卒業以来、それなりに、ドラマの分析の研究事例や潮流などを見てきたつもりです。そして、再び自分のこの卒業論文を読み返してみて.......10年以上も前のものですが........「知らない」とはつくづく恐いものだなぁと思います。今も.....やはりお気に入りではあります。そして今の研究の出発点でもあるようです。
今は、さまざまな側面で余裕がなく、シンプルな実証的研究に没頭しているように思われているかもしれません。が、しかし、いつかきっと社会文芸的なアプローチにも帰る時がくるでしょう。しかし、それはきっと少しでも石を積んできた実証的なものが、基礎になるようなものになるでしょう。両者を並立することができるようになるでしょう。そして、そう希望しています。
語りつがれるポップを書けるように、反省と懐古をこめて、WWWで公開することにします。あまりに稚拙な表現は校正し、間違っている点は改変してあります。が、おおむね元のままです。是非、御感想などいただけたらうれしいです。WWW版に変更する手間上、未完成な部分もあります。例えば、文献リストとか。。。
1992年 日吉昭彦
目次
- 序章
- 第1章 コミュニケ-ションとしてのポピュラー音楽・人間・メディア
第1節 人間と音楽 ~近世までの音楽史
第2節 メディアと音楽 ~メディア時代の音楽史~
第3節 広告と音楽
第4節 まとめ - 音楽と社会 -
- 第2章 トレンディ-・ドラマの現象と原因
第1節 テレビドラマの商品性
第2節 労働・商品としてのテレビドラマ
第3節 トレンディー・ドラマとは ~トレンディー・ドラマの変遷~
第4節 「T.R.E.N.D.Y.」現象と原因
- 第3章 トレンディドラマの主題歌分析にみるメディアミックスとブロックバスター
第1節 主題歌の流行現象について
第2節 「タイアップ」というブロックバスター型メディア戦略
第3節 主題歌と象徴
第1項 「ラブストーリーは突然に」の歌詞の内容分析
第2項 「SAY YES」の歌詞の内容分析
第3項 「SAY YES」と「ラブストリ-は突然に」の共通性
第4節 主題歌の音楽的テクスト
第5節 主題歌の露出とイメージ付け
第6節 主題歌の流行という現象と原因
- 第4章 ドラマ・現実・虚構
第1節 トレンディドラマのシミュラークル性
第2節 トレンディドラマ分析の意義
- 第5章「101回目のプロポーズ」の構造テクスト分析
第一節 登場人物の指標 ~主体と構造~
第二節 映像的諸要素の指標 ~モノと生活~
第3節 感情的諸要素の指標
第1項 恋愛的相互作用の集合表象的側面
第2項 集合表象的「愛」の記号的表出
第3項 集合表象の受容の記号的表出
第4項 互酬と非互酬の記号的表出
第4節 構造から現実へ ~指標の比較研究への視座~
第5節 結婚観の意味作用
第1項 20代OLの持つ「結婚」観の現在
第2項 テレビドラマ内の「結婚」観
第3項 視聴者と検証行為
第4項 結婚行動の現在
第6節 指輪の意味作用
第1項 宝飾品に関する消費者意識
第2項 ドラマ内の指輪の意味
第3項 視聴者と検証行為
第4項 達郎と薫の指標比較から見た消費行動
第7節 「101回目のプロポ-ズ」の構造分析を通じて
- 「東京ラブストーリー」の言説分析
第1節 登場人物の行為分析(簡易版)
第2節 言語/恋愛/記号
第3節 主体の無意識の指標分析 ~恋愛言表の分析~
第1項 「カンチ」の恋愛言表の分析
第2項 「リカ」の恋愛言表の分析
第3項 「三上」の恋愛言表の分析
第4項 「関口」の恋愛言表の分析
第4節 試聴の「場」についての一試論
第5節「東京ラブスト-リ-」の分析を通じて
おわりに
序章
ドアを開けると、8帖ほどの部屋が広がった。
黒い壁の内装はちょっとした高級マンションを思わせる。ソファ-にテ-ブル、角には大きなモニタ-テレビが座っている。これからの2時間は二人の空間になるのだ。
店員が注文を待っている。
「君は何飲むの。え-と僕は........とりあえずビ-ルをもらおうかな」
「わたし、なにかカクテルがあれば........あっ、これにするわ、カシス・ソ-ダを」
「じゃあ、ビ-ルとカシス・ソ-ダでお願いします」
軽やかな会話が進んだ。とりとめもない話だ。
何だか分からないまま笑顔が二人の間を何往復もする。こんな笑いが自分の今の幸せな気分のバロメ-タ-になっているることに、達郎はちょっとした満足気分を味わっていた。
飲み物が来て乾杯する。グラスの音が心地よい。
「始めましょうよ。あなたからね」
薫がすすめる。
「そうだね」
達郎は上着を取って立ち上がった。
と、その瞬間流れだすイントロ・・<SAY YES>だ。
{余計なものなど無いよね・・ああすべてが君と僕との 愛のかまえさ・・}
達郎は薫の目を見て歌った。まるで歌に心を託すように。
恥ずかしそうに歌い終わると達郎は薫にマイクを渡した。薫の前で歌うのは初めてであった。達郎は何度か薫の歌を聞いたことがあった。薫は歌がうまい。アマチュアバンドでボ-カルをやっているのだ。そのシルクのような滑らかな声と美貌はそこいらではちょっょとした人気である。達郎は何度か薫のライブに招待されていた。
「上手じゃない」
意外な答えだった。少なくとも歌には自信がなかったのだ。
2百円を投じて薫が選んだ曲は小田和正の<ラブスト-リ-は突然に>だった。テレビドラマとして人気のあった「東京ラブスト-リ-」の主題歌だった曲だ。
{・・あの日 あの時 あの場所で 君に会えなかったら 僕等はいつまでも・・}
美しいメロディ-が薫の口からこぼれ落ちる。薫も達郎の目を見て歌っていた。
2時間はあっという間に流れた。
※
「え-っ・・・7500円になります」
※
1991年、200万枚を越えたシングル・セ-ルスを記録した曲が2曲生まれた。
小田和正の歌う「ラブストーリーは突然に」と、Chage&Askaの歌う「Say Yes」である。両曲ともフジテレビのテレビドラマ「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」の主題歌であった。
本稿は、このブロックバスター型のメディア現象を通じ、テレビドラマとその主題歌の人気の周辺に存在するさまざまな「力」「心」、「モノ」を分析し、そこに表れた現代社会と人間の関係に迫ってみる試みである。
上記のストーリーは、私があえて恥ずかしくなるようなイメージで作った、カラオケボックスでのワンシーンである。ここにはテレビドラマという現実の模倣であるはずのものが、二人の行動の指針になっているという状況が見出せる。上記のストーリーの主人公の作りだす恋愛世界は、二つのドラマがなければ全く異質のものと変容していたであろう。音楽と感情の合流、音楽の記号化、物語と時間のパッケ-ジソフト化、商品化..........。これらの出来事は、テレビメディアと人間との間の、どのような関係によって作り出されたのであろうか。
トレンディードラマの流行という現象は、マス・コミュニケーションの過程の結果である。この流行現象は、テレビメディアと人間のコミュニケーションによって、「結合され体系化されたある心理的な一つの様式る(デュルケイム1895)」である。流行現象の結果としてできた集合体は、「そこに存在する個人とは全く違った仕方で、思考し、感覚し、行動する(デュルケイム1895)」。そこには個人の意識に関わらない、命令と強制の力がある。このように、流行現象とは、マス・コミュニケ ーション過程によって形成される社会的なものである。
これからの試みは、「101回目のプロポ-ズ」と「東京ラブスト-リ-」という具体的なテレビドラマ、およびその主題歌である「ラブストーリーは突然に」「Say Yes」を対象に、マス・コミュニケ-ション過程と流行現象について分析し、メディアおよび視聴行動に内在する権力分配の合意にまつわる構造を明らかにするものである。いわゆる「マスコミの限定効果説(クラッパー 1966)」や「利用と満足に関する研究(岡田 1976)」など行動主義的なマスコミ研究の文脈では、「受け手」が批判的に自由に読み解くメディアという側面に光が当てられているように思う。マスコミの効果・影響について大きく論じるのは、いささか古臭くも感じる点がある。しかし、こうした観点からは掬いとれない、メディアと「受け手」の合意や権力構造について、「意味」や「テクスト」の生成という観点から、あえて批判的に考察していきたいと思う。
第一に、テレビドラマが「いかにして流行現象と化していったのか」という現象の「原因」 について考察する。マス・メディアによる流通と流行はどのような性質を持つか。間接的な消費としての電波、直接消費としてのCDはどのように商品化されたのか。メディア自体を巧みにマ-ケティングに組み込んでいった方法、そこに触れた視聴者への効果などについて論じる。ここでは、消費社会・資本主義社会におけるマス・コミュニケーション過程の構造を明らかにする。
第二に、テレビドラマに映し出された内的世界を詳細に分析し、現実の世界との関わりについて考察する。テレビドラマはいかなる構造を持ち、それに関わった人間はどのように変容していくのか、「構造分析」や「精神分析」的な方法を用いて分析する。この分析から、マス・メディアが果たす「機能」を 考察していきたい。
現象の「原因」と「機能」を分析するという点で、デュルケイムが「社会学的方法の規準」で論じたような社会学的分析となるだろう。また「マス・コミュニケーションの総過程(田中 1968)」にふれることで、構造的な分析になるだろう。
第1章 コミュニケ-ションとしての
ポピュラー音楽・人間・メディア
まず流行現象の「原因」を明らかにするため、ポピュラー音楽そのものをメディア論的に考察しておきたい。
テレビドラマにおけるメディアとしての主題歌の機能を考えると、それは視覚だけでは伝えられない感情や雰囲気の創出であると言えるだろう。しかし、このような創出が可能となる理由はどこにあるのだろうか。
現在のポピュラー音楽は、メディアそのものの変化や音響技術などの発展・向上に伴って多様化している。近代化を背景としてマス・メディアが発展し、「受け手」と「送り手」の関係は大きく変化した。ポピュラー音楽の享受の仕方、さらに音楽自体をも変化させている。
ところで、「人と人とのインターフェイスとしてのメディア」の存在を考える以前に、音楽というものの構造が「送り手→受け手」という基本的なコミュニケーション構造を持つことに変わりはない。
そこで、音楽とは人間にとって何であるのか、そもそも、音楽とは何なのかという、基本的な人間と音楽の関係を歴史を紐解くことによって、本研究のメディア論的背景を見ていきたい。
第1節 人間と音楽 ~近世までの音楽史
( 本節はシュバープの著作に強い影響を受けました)
音楽という手段で自分が無名になっていくことが大事だと思う
武満 徹 「FM fanインタビュー」より
映像と音楽の関係を理解する上で、こうした非言語的コミュニケーションであった時代の音楽とその変化をふまえることには一定の意義がある。またテレビドラマと主題歌およびその社会学的文脈での理解には、音楽が社会性を持つ過程の理解が欠かせないであろう。本節は音楽学者シュバープの論を中心に、音楽の起源から中世までの音楽を考察する。
「音楽がいつ発生したか」というテーマには、「音楽とは何か」そして「音楽を音楽と規定するものは何か」という問題がつきまとうだろう。言うまでもなく正解はない。作曲家の表現を具現した「作品」が音楽なのか、はたまた机を叩いた「音」から音楽を定義すべきなのか。ここで一つ言えることは、音楽は音によるコミュニケーションであるということだ。音楽の発生段階においては、言葉以前の非言語的コミュニケーションであったといえよう。
人間が一つの動物として進化し始めたとき、生存のための攻守両面における連絡としての叫び声や、意味を音程に持たせた叫び、楽器として利用される以前の打音などが利用されていたと言われている。先史時代の出土品にはそうした楽器らしき存在を物語るものがある。
未知といわれるような時代において、人間には社会と呼べるほどの組織的な機能はなく、ある単位の「群れ」をなして生活を守ろうとした。人間は言葉を持った。言葉を知ると言語として規定できない自然の模倣を試みた。集団を形成する初期の意識の連帯として、信仰が生まれた。神に対する語りかけは日常の言葉とは差別化された。多くの儀式における独特の昂揚のある言葉やリズムから、音楽の発生が予測できる。
このように、現在の音楽といわれるものの存在とは考えを異にする、生活、信仰、政治と直接関わってくるものとして、音楽は発生したといえるだろう。
音楽がより音楽「らしく」なる過程は、社会構造の発展と共に進んだといえる。より複雑なリズムやハーモニーを持つ音楽が、生活に密着し根づくものとして社会に広まってくる。人々はリズムが仕事に「のり」を与え、効率を上げられることを、生活の知恵として知っていた。音楽は生活の反映でもある。このような音楽は現実に鳴り響く音として残っていないまでも、世界中の民族音楽や伝統音楽にその一部を垣間見る事が出来る。
人間は情報の交換の手段として音楽を利用し、その情報を個人内で処理していく(カード、モラン、ニューウェル 1983)。この過程において、個人内での情報処理の方法は、情報内容(この場合、音楽)によって、また各個人内の既存の経験によって変化する。こうして音楽が社会性を獲得していくのである。音楽コミュニケーションの形態と音楽文化の関係は、こうした社会性に見ることができよう。
近世の音楽を一言でまとめるならば「非日常と遊びの空間としての音楽(シュバープ 1986)」といえるだろう。教会の社会的地位の向上と音楽の祝祭空間との結合は、音楽の階層化・階級化を生んだ。貴族のための祝典音楽、宮廷における演奏、学者のためのアカデミー・コンサ-ト、学生の仲間同志の音楽、身分の低いもの同志の競演・・など社会の階層化にしたがって、音楽はその情報内容を多様化させてきた。また音楽の行事化は、人間を演奏する側と聞く側に分化させた(シュバープ 1986)。
17世紀は経済上の大変化が社会に見られる時代でもあった。自給自足経済は資本主義経済へと移行し、都市が発展した。商業主義の思想は音楽にも及んだ。音楽の娯楽的要素と、「弾く/聴く」の分業化を利用したコンサートが多く開かれるようになった。入場料を払えば音楽に参加できるという形態は、不特定多数の聴衆をあてにした音楽の販売行為の始まりだった(シュバープ 1986)。
近世の音楽の歴史からは、音楽コミュニケーションの大衆化が、社会の変化と同時に進行していることと、それによる音楽の変化がみてとれる。
第2節 メディアと音楽 ~メディア時代の音楽史~
別に音楽一筋に生きるつもりはない。かと言って詩や絵、ファッションに没頭する気もない。その時に強い印象を与えてくれるものをやりたいんだ
トーマス・ドルビー 「Sound & Recording Magazine」誌 インタビューより
20世紀に入ると音楽コミュニケーションの形態は大きく変化した。メディアの発展によるマス・コミュニケーション化が進んだことが要因である。これまでの音楽が即時的な「いま・ここで」というような一回性に特徴づけられるものだったのが、産業革命や電気革命によって複製可能となり、「いつでも・どこでも・何度でも」というような新しい聴取のスタイル、コミュニケーション形態が現れたのである。
こうした聴取スタイルというコミュニケーションの形態の変化を考慮に入れておくことは、テレビドラマの主題歌の役割を考察する上での視点を提供するであろう。そこで、音楽メディアの発展を簡略に年表で示したものが図1である。表に記したものは、音楽コミュニケ-ションの形式に変容を与えたと思われるものに絞った。
略年表図1(引用失念しました。失礼します。)
音楽とマスメディア
(1) 1878 エジソンによる蓄音機免許取得 (2) 1920s レコードの発達 (3) 1948 コロンビアレコード社33、1/3LP盤発売 (4) 1940s ラジオの普及 (5) 1953 テレビ放映開始 (6) 1958 ステレオレコード発売 (7) 1959 民放の開局 (8) 1960s FM/テープ/ステレオの普及 (9) 1967 オールナイトニッポン(深夜放送)開始 (10) 1968 ラジカセ発売 (11) 1975 カーステレオの普及 (12) 1979 SONY社ウォークマン発売 (13) 1980s CD/DAT/レーザーディスクなどデジタル化
それぞれの年次のメディアの変化について簡単に説明しておく。
(1)(2)であるが、音楽が「複製」可能になったことは、音楽をめぐるコミュニケーションに急激な変化をもたらした。現在の電気を通じた音楽をめぐるコミュニケ-ションの始まりはここにある。
(3)が示すものは、レコ-ドが「商品」として「大量に生産」されるようになったことである。こ音楽が「大量複製」されることを意味する。
(4)では、それがラジオで流されることにより、さらに「販売」が「促進」され、より「多くの聴衆」を得る。音楽をめぐるコミュニケーションの「大衆化」の始まりである。「ポピュラ-音楽」という「新しい領域」の確立ともいえよう。
(5)(7)を通じ、音楽は「映像」とミックスされる。音楽は、「情報」の観点からより複雑な「メッセージ」となる。情報の「受け手」である視聴者の、音楽聴取のスタイルも少しずつ変化してくる。私たちの聞く音楽が、テレビの提示する世界と、同時に触れ合うこと。これは私たちがコミュニケーションの傍観者になったことといえるのではないだろうか。あるいは音楽コミュニケーションを内に含むコミュニケーションとして考えられるかもしれない(図2)
テレビのもつイメージ、文化、社会を通じて一つのものへと収斂していくものの誕生である。聞くことという娯楽の形態は風俗などと結び付いた。ツイスト、サーフィン、ダンス・・・等。
図2メディア・ミックスとコミュニケーション(音楽)
送り手-[送り手→受け手]-テレビ
↓
受け手-視聴者
(8)では音楽が特定の場から「開放」され、より深く「日常空間」に浸透した。コンサート会場はこの時点で音楽のアジールとしての機能を失くしはじめるのである。かくしてラジカセが仏壇に収められることになる。神棚のテレビに変わって.......。
(9)はAM放送の深夜放送のことである。深夜放送は「若者」に人気を得て、若者文化と密接に結びつき、若者の中心的な音楽メディアとなり、フォーク、ロック、ニューミュージックなどの音楽を支えたと言われる。
(10)では好みの音楽を好きなときに「録音」し「再生」するという、音楽の日常化である。
(11)では音楽の「パーソナル化」がさらに進展した。コンサ-ト会場からステレオ、ラジカセのある部屋へ、部屋から電車のなかへ、電車のなかから車のなかへ。思い起こせば音楽はそれ自身において、移動体の性格を内在していたはずだ。街の街路での出会いのように。都市が人々を切り離すように、テクノロジ-が音楽をある領域に定住させる。そして出会いのない速度機械での移動........。再び開放された音楽......。しかし人々は歌うことはない。近代社会の音楽は交通である。所有の意味が問われる「パーソナル化」である。
1980年代は音楽のデジタル化に注目すべきだろう。CDはアナログレコ-ドを短期間で衰退させた。アナログとデジタル...........数字であるなら全く同じコピ-が作れる。保存、流通にも便利で情報量も多い。「情報化」時代において、音楽が溢れる情報の一つになっていることを、象徴的に表した技術革新である。カラオケは音楽を、「遊びに伴う」ものから「遊び自体」にした。CD、LDなどの普及は良質な音を提供し、視聴者の「聞く」レベルをある意味で向上させているかもしれない。
エレクトロニクスよりも木のアコースティック・クオリティーの方がはるかに重要だ。サウンドに最も影響を与えるのは木なんだ。
ロジャー・サドウスキー 「ギターマガジン」誌 インタビューより
スピーカーから聞こえてくる音楽。機械とのコミュニケーション。そこには作曲家の作品を具現しようとする演奏者の能力や苦悩に触れる遭遇はない。音楽完成の瞬間の稲妻の光、adam&ive的な不完全性へのあこがれも忘却の彼方にある。私たちが小さな円盤を再生機にかけ「本物」と思っているものは、「実は『コピー』なのだ(清水 1972)」。人間の活動範囲を越えて到達した音楽からは、誰が演奏しているのか確かめる術はない。オリジナルなものは遠くにあって手も耳も届かない。「実物はコピーと照合することはできない(清水 1972)」のだ。しかし私たちはコピ-に満足するしかない。コピーに向かって一喜一憂するしかない。
では送る側の意図はどうだろう。送る音楽の取捨選択は一部の独占的な企業によって行われている。そしてコピー作り(ソフト制作)は営利事業である。資本主義的な観点から行われる取捨選択は、マーケティングという「万人主義」や「平均主義」である。すべては売れなくてはならないのだ。こうして公衆は、意識ある消費者と自らを思いながらも、一方的に流される音楽に「音楽」を見出せないまま、消費するのである。マス・コミュニケーション化した音楽に、マス・コミュニケーションの諸問題があてはまることは、現代音楽を論じる際に決して見逃せない要因である。
第3節 広告と音楽
(本節は、小川博司先生の著作に大いに影響を受けました。論文全体もですが....)
音楽からメタリックな輝きを奪い、閉じた空間の中に重く沈殿させる、いくつもの罠。その中でも最大のものが「意味」と「情念」にほかならない
浅田 彰「ヘルメスの音楽」より
ブロックバスター型メディア・ミックス時代のテレビドラマと主題歌の関係を理解するにあたり、コマーシャルと音楽という先行研究は極めて示唆的である。
パッケージ化された音楽の大量生産と販売は、新しいメディアに適合した音楽を生み出した。ポピュラー音楽、テレビのCM音楽、イージーリスニング・ミュージックなどだ。これらはいずれも生活、時間、価値を消費するという傾向と深く関係しているように思われる。そしてメディアと音楽、メディアと消費、消費と音楽という三つ巴関係を考察するにあたり、ラジオやテレビなど、音声のあるメディアが登場して以来、変化してきた広告と音楽の関係の歴史を振り返ることは欠かせない事である。この論文のテ-マの一つである、メディア利用によるブロックバスター型の消費戦略も、これらの一つの延長と考えられるからである。消費の促進と価値形成に大きな力をもつ広告と、音楽はどういう関係にあるのか、主に小川博司の研究に着目し論考していきたい。
「我々は現在音楽に接しない場面に遭遇するほうが難しい(小川 1988)」と小川博司の言葉にもあるように、意思に関わらず投げつけられる音楽は、なぜこれほどまでに大量に流され続けられるのだろうか。その答えの一つに、音楽の広告効果があげられるだろう。それは、ただ鳴っているだけの効果から、音楽のもつイメージ付け効果まで実に多様だ。ラジオやテレビといったメディアは音声機能が重要な役割を果たしているが、その感覚的な効用は、媒体がマス化すると共に注目され、また、常に新しい音楽シ-ンを形成してきた。
この広告音楽の流れを小川(小川 1988)は次のように整理している。テレビ、ラジオが登場して「広告と共に音楽を」という形でCM音楽が広まった。広告音楽は音楽の利用のされ方と広告の形態によって大まかに3段階に分けることができる。
まず初期段階である。1950-60年代中盤までは、CMにおいて音楽は「歌」というよりも「サウンド」として使われた。具体的には簡単なメロディーに、商品名の連呼だけといったものだった。流行歌とは別世界の機能重視のCM音楽である。この背景にはモノを中心にした広告形態があるといえる。
1960年後半あたりから、映像と音楽の結びつきの生む感覚的な効果が注目された。この段階ではサウンドの効果が中心であった。言語的な直接のモノへの言及ではなく、サウンドによるイメージの提示となったことは、モノ離れした広告形態と消費ブームが背景にある。
さらに1970年代にはいると、音楽によるさらなる個性化と差異の主張がなされた。ここではヒットした曲をCMソングとして利用することで、商品なり企業なりを、消費者に注目させよう、知らせようとする。これは音楽からのイメージの転化を狙ったものだ。「音楽が好きだからその商品も気に入ってきた」といったアピ-ルだ。企業のキャンペーン広告とアイドル人気が重なったこの時期に、イメージソングは最盛期を迎える。
音楽もモノも同じで、企業は業績重視である。価値の名の元で、モノや資本主義的情念に屈する音楽.........。それは利用か、大道芸か。いや、むしろ意味からの脱却にこそ、広告時代の音楽が音楽たりえる契機ではなかろうか。
1980年代になると、広告の音楽による個性化と差異主張はさらに声高になる。ありとあらゆる音楽が使われるようになる。聞く側の差異化も進む。メディアの発展とともに音楽の嗜好は細かく分化した。一つの尺度では捕らえられない大衆という、現在の大衆をターゲットにした広告音楽が成立してくる。誰にでも受け入れられる、気に入られるといった音楽よりも、良質さやマッチングのセンス、奇抜さなどが主張される。例えば、ホンダ車のプレリュードのどこにボレロの荘厳さがあるのか、疲れたサラリーマンがアリナミンAを飲みながらなにが「What A Wonderful World」なのか、やや疑問なところだが、音楽文化はこうして生活に根付きながら広まっていくのである。
広告としての音楽を見ていくと、音楽事業にも目がいく。企業メセナとしての音楽支援だ。「冠コンサート」とよく言われる。「こんなアーティストを支援して、我が社はこんなに文化的ですよ」といわんばかりの広告事業である。海外有名アーティストを音の悪い米粒程にしか見えないような大ホ-ルに招聘し、10日間も連続で1万円もとっても「文化的」な企業である。言ってみればイメージソングの事業版である。「バブル経済崩壊だ」といっては真先に文化支援を止めてしまうのも「文化的」な企業である。おおむね「文化産業」とはこうした、広告音楽的で、市場の論理を優先するものである。
このように広告音楽の変遷をみていくと、メディアを介した音楽が、音楽シーンをリードしてきた事がよく理解できる。メディアの作った流行現象が数多くのヒット曲なりスタンダ-ドなりを生んだことは、人間の豊かさを、音楽というコミュニケーションを通じた人々の生活に活性化を与えた点で、メディア時代の音楽は「公的」な文化財でもある。しかしこの公害性も決して無視できない。
第4節 まとめ - 音楽と社会 -
以上、人間・技術・広告の観点から、音楽をめぐるコミュニケーションについて見てきた。まとめてみたい。
1、音楽は人間が生存するのに欠かせない、コミュニケーションの1形態である。
2、音楽はコミュニケーションの結果として、生活や社会的集合体を作りだす。
3、音楽が作りだす社会的集合体は、資本主義社会に利用される。
音楽をめぐるコミュニケーションを社会学的に「現象の原因」の背景として見ていくことと、音楽が作りだす社会的集合体について考えることは、トレンディードラマを分析する際に有効であろう。主題歌はパッケージソフトとして実際に流通機構にのる。それに対し、テレビの試聴行為は、実際の数値的な消費を表さない。主題歌の販売量などのデータは、実際の数値から、経済的な集団を考えることができる。そしてこの集団を、テレビ試聴の集団にシフトしてゆくことが可能になる。
こうして曖昧な視聴率からだけでない、メディアが作りだした社会の規模・性質をより明確に知る事が出来る。
第2章 トレンディ-・ドラマ現象とその原因
第1節 テレビドラマの商品性
1991年オリコン・シングル・レコードチャートでは、1位がChage&Askaの歌う「Say Yes」、2位が小田和正の歌う「ラブストーリ-は突然に」だった。これらは二曲ともテレビドラマの主題歌である。この現象はメディアと音楽、そして消費の関係の一つの新しい形態と言えるだろう。このブロックバスター型の消費現象の実態を、テレビドラマの商品性という観点から考察し、トレンディ-・ドラマ現象とその原因について明らかにしていきたい。
今日、小説や新聞を開きテレビをつけるという行為は、いかにも身近で無造作なものだが、しかしこのささやかな行為が、その後必要となる物語コードを、我々のうちに一挙にもれなく備えつける
ロラン・バルト 「物語の構造分析序説」より
テレビドラマに関して論じる前に、「ドラマ」という言葉について明らかにしておく必要がある。「ドラマ」とは「演劇、劇、戯曲、しばい.....」などなどである。「劇的な」というような意味合いもある。
この論文において「ドラマ」とは便宜的にテレビドラマを指すことにしておこう。「演劇」という言葉は、辞書には(辞書にもよるが)「扮装した俳優が劇場で脚本に従って種々の言語、動作を見せる芸術」とある。であるからテレビドラマとは、簡単に言えば「テレビで見れる作り話」がテレビドラマである。
同時にテレビというメディアによって行われる放送であり、それによって起きるコミュニケ-ション過程においての情報、メッセ-ジである。テレビの内容分類(中野 1963)からみてみると「報道・教育・娯楽・その他」のなかの「娯楽」にテレビドラマは分類されるだろう。
第1節 労働・商品としてのテレビドラマ
テレビドラマという放送を、消費社会になかで「商品」として位置づけて論じる際に、その商品性をいかにとらえるか。労働の代価となるものを商品としてとらえ放送の商品性を論じたのが稲葉 三千夫の「マス・コミュニケーションの生産過程(稲葉 1963)」である。以下はその簡単なまとめである。これを前提に次の考察に進みたい。
マルクスは労働を「人間がその自然との物質代謝を彼自身の行為によって媒介し、規制 し、調整するところの一過程である」と定義している。そして「労働過程が営まれるからにはそこには3つの契機(労働そのもの、労働対象、労働手段)が存在する」と述べている。
資本主義社会の発展と共にコミュニケーションのマス化が進み、組織として発展した 。
マス・コミ産業は上のような労働過程を含む資本家である。彼の労働手段は技術を利用した放送である。そして労働対象は彼の見る世界とその表現である。彼の見るものは社会であり、かつ資本主義社会においてそれは商品である必要がある。さらにはその商品は受け手の欲求を充足し、享受されなくてはならない。ここから放送は商品であることが分かる。
報道にしろ教育にしろ経営のための商品であることには変わりない。マス・メディアが単なるサ-ビス業とは異なるとはいえ、制作活動が労働の中心となっていることは放送が商品であることを表していると言えるだろう。ここからテレビドラマの商品性に着目し、トレンディ・ドラマ現象という経済現象を対象に、現象の原因を明らかにしていきたい。
第3節 トレンディー・ドラマとは ~トレンディー・ドラマの変遷~
自分たちが見て面白いと思うものを同世代感覚で作ったんですよ
大多 亮 「朝日新聞 インタビュー」より
図3

浅野温子
「101回目のプロポーズ」
「君の瞳をタイホする」ほか
織田裕二
「東京ラブストーリー」
「あの日の僕を探して」ほか


今井美樹
「以外とシングルガール」
「思いでにかわるまで」ほか
石田純一
「抱きしめたい」
「思い出にかわるまで」ほか


石田ひかり
「君だけにできること」
「悪女、ワル」ほか
江口洋介
「愛という名のもとに」
「もう誰も愛せない」ほか


田中美佐子
「結婚の理想と現実」
「10年愛」ほか
柳葉敏郎
「素敵な片思い」
「ハートに火をつけて」ほか


中山美穂
「素敵な片思い」
「君の瞳に恋してる」ほか
吉田栄作
「キモチいい恋したい」
「君だけにできること」ほか


浅野ゆう子
「君の瞳をタイホする」
「ハートに火をつけて」ほか
唐沢寿明
「愛という名のもとに」
ほか


小泉今日子
「あなだけ見えない」
「パパとなっちゃん」ほか
大鶴義丹
「君の瞳に恋してる」
「逢いたいときにあなたはいない」ほか

詳細な「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」の内容は、後々説明することになるが、ここでも簡単に述べておく。
「東京ラブストーリー」は、3人の同郷の同級生が東京を舞台に東京で出会った友人を織りまぜての恋愛スト-リ-。出会い、恋、別れ・・といったストーリーが何パタ-ンかあり恋愛感情を中心とした描写が特徴である。
「101回目のプロポーズ」は、99回お見合いしても結婚できない中年サラリーマンと、過去の婚約者を結婚式当日に亡くした100回目のお見合いの相手の美人音楽家との恋愛ストーリー。主人公のひたむきな愛と相手の迷いを中心に、周囲の友情と恋愛をストーリーに散りばめている。
両テレビドラマとも現在人気の「トレンディー・ドラマ」と呼ばれるものだ。二つのテレビドラマに共通する点がいくつかある。第一に恋愛ストーリーという点である。また第二の共通点として製作主体があげられる。この二つのテレビドラマは「フジテレビ」が制作したものである。
「素敵な片思い」「東京ラブストーリー」「101回目のプロポーズ」の三作は、制作段階から、純愛3部作として一連のシリーズものとして製作されている。
第三の共通点は、上記の3つのドラマに共通のプロデューサーが関わっていることである。大多亮氏だ。
第4に俳優や描写の面でも共通点がある。テレビドラマを演じる俳優はほとんど全員(「101回目のプロポーズ」の武田鉄矢は例外?)いわゆる美男美女ぞろいである(図3)。彼らは都会派スタイルの生活を送り、仕事よりアフタ-ファイブを楽しむ。ちょっと使ってみたくなるようなセリフ回し。若者のある種のあこがれを表現したものと見ていいだろう。
簡略ではあるが、トレンディ-ドラマの歴史を振り返ってみよう。始まりは1986年にTBSの放映された「男女7人夏物語」。翌年「君の瞳をタイホする」で本格的にトレンディードラマが始まる。その後はフジテレビが次々とトレンディ-ドラマを放映し、「トレンディードラマといえばフジ」という図式ができあがる。1988年の「抱きしめたい!」「君が嘘をついた」。1989年の「君の瞳に恋してる!」「ハートに火をつけて!」「愛しあってるかい!」。1990年は「世界で一番君が好き!」「恋のパラダイス」「キモチいい恋したい!」。TBSは「想い出にかわるまで」「クリスマス・イブ」と反撃する。
(卒論を書き終えて10年。インターネットが登場し、トレンディ-ドラマもHPで詳細に紹介されている。以下のサイトは、こうしたトレンディ-ドラマの歴史に非常に詳しい。御参考にどうぞ。)
- トレンディ・ドラマの系譜
- テレビドラマデータベース
第4節 「T.R.E.N.D.Y.」現象と原因
WARNING: ADVERTISING CAN CAUSE SERIOUS DAMAGE TO YOUR BRAIN AND OUR WALLET
モスキ-ノ/MOSCHINO 広告ポスタ- より
なぜこのようにトレンディードラマは爆発的な人気を得たのだろうか。こうしたトレンディードラマは、大多氏のいう「同世代感覚」以上に多くの世代間で共鳴を呼んだ。時代背景は「バブル経済」の真っ最中。
そこで、本節では、この流行の原因について、キーワードでもある〔T.R.E.N.D.Y.〕という単語を使って、分析してみたいと思う。
トレンディーとは「TRENDY:流行かぶれの、流行の先端を行く」という意味であ る。「売れる/流行る」などの要因は、多分に多くの要素が絡み合っている と考えられる。以下の図(図4)は、この〔T.R.E.N.D.Y.〕という語に着目しつつ、そのさまざまな側面について触れたものである。
図4 T.R.E.N.D.Y.現象
T
Theme 主題としてのアフェクション 物語 結婚/恋愛/友情 R
Regurar 連続もの。一度みると次もみたくなるのは人の心 円環 時間の強調 E
Eco 見ることに意義がある。問題は次の日の会話 振幅 付和雷同と作為の流行 N
Network プロモーションとメディアミックス メディア 放送の商品化 D
Distinction 俳優が好き 権威 名前に記号 Y
Yourself 鏡よ鏡、最も美しいのは誰 鏡像 それは石田ゆり子に似ている私かしら
T:THEME(テーマ性)は、ドラマの物語の放つ刺激の要素である。こうしたテーマは「受け手」の現実というコンテクストに引き入れられ、視聴者の反応を形作る。テレビドラマのテーマの一つに貫徹しているのは〔AFFECTION=愛〕である。この内容については論の後半の構造分析の際により詳しく論ずるので参照してほしい。
R:REGULAR(連続性)は、視聴者の心理が「見る、見ない」の選択に影響する生活様式の一つである。また、個人の嗜好や気分など、連続性にまつわる要因はさまざまである。生活様式であれば、社会的な背景や状態も反映するであろう。むろん、社会・集団の心理は、個人の気分にも反映しているはずである。
ドラマの放映と時間の関係から、生活者としての視聴者の時間意識について考えることは非常に重要だ。現在の区切られた時間の連続性に基づいた生活が、社会様式を見る標識になるからである。テレビを「見る、見ない」とは実に生活様式そのものなのである。
区切られた時間の連続性はどこに起因するのであろうか。例をあげれば、ミクロなレヴェルにおいて時計の針、マクロなレヴェルでの生と死の間、その中間にあたるカレンダ-などなどが上げられようか。さらに私たちは「メディアの場」というものをしばしばこうした時間測定の道具にしている。テレビに内在する時間の細分化と流され続ける電波。15秒きっちりに収まったCM、現実のカットアップである映像も細切れになり次々と姿を変えて続いていく。テレビを見ることは時間を忘れさせる娯楽ではない。それは意識させ身動きを取れなくする。新聞のテレビ欄を見てみよう。ここには固定され動けなくなった死の時間が表されている。時間のレールに乗せられた人々が連続物のドラマを見続けること。同じ駅から同じ駅へのトランスの連続。それこそがメディアの場に見られる生活様式である。メディアの内も、メディアの外も、である。名だけの時間移動、移動に伴う目的の消滅。流行現象とは移ろいやすい生活様式の場そのものなのである。
E:ECHO(反響性)。社会が流行を規定する。よく言われることである。しかし、同じようによくあることは、その流行が社会を規定し始めるといった倒錯現象である。もはやだれもどちらが真実なのか分からな いまま人々はテレビのスイッチをいれるしかないのである。
N:NETWORK(伝導性)。音楽や雑誌などとのタイアップによるブロックバスタ-型宣伝を、ドラマのメディア戦略がどのように利用したか、そしてどのような効果があったか・・これは前半の中心的論議であるので後述することにしよう。
D:DISTINCTION(卓越性)。ドラマは商品であり、その価値の受け入れられ方は多様化している。中心にあるストーリーだけ見られているわけではない。あらゆる周縁がドラマの価値に転嫁される。現実との差異化が生む「ゆらぎ」は、ドラマのあらゆる映像・感動から引き出される。
DISTINCTIONの意味は「差異」「卓越化」「栄誉」などである。コミュニケーションとは「差異化」の結果という側面がある。同時に「卓越化」という利害的な目的を持っている場合もある。マス・コミュニケーションの場合、こうした傾向はますます強くなる。
Y:YOURSELF(潜在性)。鏡の中の想像の世界と、現実の二項対立は、現実が切り取られシミュレートされメディアに乗った時、それは潜在的な現実として想像と同化する。私たちはテレビにヴァーチャルな自画像を見ることになる。鏡に移る自分の像=メディアの像は、像でしかないと分かっていても、自分自身の認識体系の表出=現実となる。それは、鏡を見たい気持ちである。それが、テレビを見たい気持ちである。
以上、「T.R.E.N.D.Y.」というというキーワードから、「テーマ性/連続性/反響性/伝導性/卓越性/潜在性」という語を浮かび上がらせ、トレンディドラマの人気・流行の原因を考察した。やや観念的ではあるが、これはなにもトレンディドラマだけにあてはまることではないと確信している。「T.R.E.N.D.Y.」な時代が終わった後も、メディアに関わる流行現象には、全般的に適用できるものと信じている。
第3章 トランディドラマの主題歌分析にみる
メディアミックスとブロックバスター
テレビドラマを見ること、つまりはメディアに触れることは、放送を商品性をふまえれば消費の一形態である。しかし、それは間接的な消費であり、「テレビショッピング」などを見ている場合以外には、実際にテレビを前に財布を開くことはない。
視聴率のようなデータが、ある種の市場を指し示すことはあるが、消費者が直接、貨幣と等価交換できる場を創出するまでには、かなりの段階を経ることを要する。
ここでドラマの主題歌について考えてみよう。ドラマ主題歌の消費現象を分析することは、ドラマという放送の流通機構を分析することにもなるであろう。その理由は既に述べた。
音楽の機能として生活の表象というものがあった。では、生活のシミュレーションであるテレビドラマを、主題歌が象徴的に表現しているのだとすれば、主題歌のヒット現象をドラマのヒット現象の象徴として考えることもできよう。CMソングの研究事例を振り返れば、音楽と映像が相互に売り上げを補完している過程がよく分かる。広告のメッセージを音楽に意味として託し、あるいは音楽の持つテクストを広告の表現にシフトした方法は、一種のマーケティングであり、この方法はテレビドラマに関しても応用可能であろう。
主題歌とテレビドラマの相互利益関係をつくり出すこの方法を「音楽マーケティング」と呼ぶことにしよう。「音楽マーケティング」という言葉は既に使われつつある言葉であるが、これまでテレビドラマと主題歌の関係には言及されてきていないように思われる。マーケティングとは「個人と組織の満足させる交換を想像するために、アイデア、財、サービスの概念形成、価格、プロモ-ション、流通を計画・実行する過程である」(AMA アメリカマ-ケティング協会)とある。つまり顧客満足と企業利益の同時進行のための方法論といえる。マーケティングの定義をふまえた上で、テレビドラマと主題歌の関係に注目してみたい。
「テレビドラマ、主題歌、視聴」の3者に関わるル-プに着目してみよう。二つの重なりあいがみえると思われる。1つ目の重なりは主題歌を含むテレビドラマ全体/視聴者である。これはテレビドラマを商品、あるいは財と考えるなら「テレビ局/視聴者」と考えられいわゆるマーケティングの概念に合致する。2つめの重なりはドラマ/主題歌の図式だ。売上を満足とするなら「ドラマ/主題歌=企業/顧客」、あるいはその逆としても考えられる。2つ目の重なりはいわばマーケティングという語から図式的に導き出したものであるが、この2つのル-プの絡み合いを「音楽マ-ケティング」と、ここではいったん定義しておきたい。
ではいかにして「音楽マーケティング」を成功させたのか。本稿のタイトルでもある現代社会のなかでのメディアの位置づけを明らかにしていきたい。
第一に、テレビドラマと主題歌の流行現象について、「うた/テレビ」という二つのメディアの関連から考察し、現象の原因について考察する。
第二に、主題歌がテレビドラマの象徴としての役割を実際に果たしているのか、ドラマは音楽をいかにしてイメージづけたかという観点から、主題歌の流行現象の原因を考察する。
第1節 主題歌の流行現象について
まず第一に、「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」はどのような人に視聴されていたのか、データで示してみよう。図5-1/5-2は「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」の年齢別・男女別の個人視聴率である。
図5-1
東京ラブストーリー 3月4日放送分個人視聴率
年齢層 4-12 13-19 20-34 35-49 50- 男女 男性 女性 男性 女性 男性 女性 視聴率 10.70% 30.40% 20.20% 30.00% 8.20% 15.30% 4.20% 5.10%
図5-2
101回目のプロポーズ 9月2日放送分個人視聴率
年齢層 4-12 13-19 20-34 35-49 50- 男女 男性 女性 男性 女性 男性 女性 視聴率 12.50% 28.80% 15.7% 29.60% 7.50% 18.90% 4.10% 7.20%
ビデオリサーチ者視聴率調査より
このデータから視聴者の年齢や性別によるおおまかな集団分類ができる。
データが示すように、両テレビドラマの最も中心となった視聴者層は、13-19才(これは男女分類がなく、ティーンという範囲だろうか)と、30-34才の女性であり、30%近くとかなり高い視聴率である。
年齢層が高くなるにつれ、男性よりも女性のほうが多く視聴しているようである。
全体的な傾向として視聴率は高く、これは放送期間中はおおむね「人気がある」と言われてきたことからも理解できる。両テレビドラマは明らかに流行現象であったと言ってよいであろう。
テレビ視聴者は、現実において何らかの形と程度において、関心・信念・年齢などの心理学的要因や人口統計学的要因の先有傾向を共通に持つ集団に所属している。放送という商品は、このような集団、つまり商品のターゲットとなるマーケットに対して、メッセージとして届けられている。先有傾向による諸処の要因によって、振り分けられた小集団にこのようなメッセージが届いたとき、その反応は集団によって異なる。しかし、違いこそあれ、流行現象とはマス・メディアによる囲い込み、つまり小集団の差異を内包しながらも拡散・拡大し、その差異を雲散夢消しながら巨大化していく集団の形成なのである。
次に、主題歌が流行するという現象を、テレビドラマの人気との関係から考察してみたい。
図6-1は「東京ラブスト-リ-」の世帯視聴率の伸びと「ラブスト-リ-は突然に」の売上の伸びを、図6-2は「101回目のプロポ-ズ」の視聴率の伸びと「SAY YES」の売上の伸びを示している。横には各数表を示してある。
図6-1 「東京ラブスト-リ-」の視聴率と「ラブスト-リ-は突然に」の売上
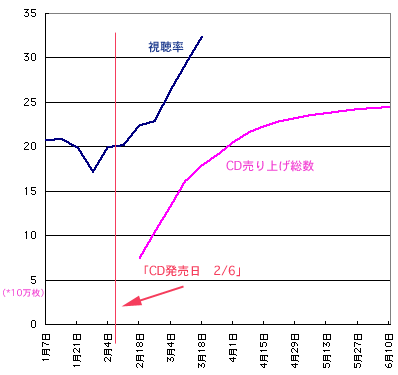
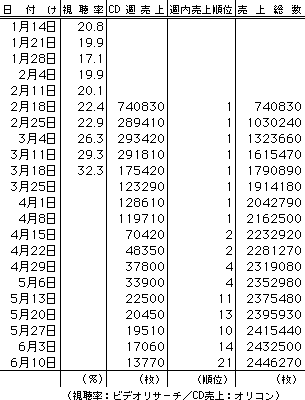
図6-2 「101回目のプロポ-ズ」の視聴率と「SAY YES」の売上
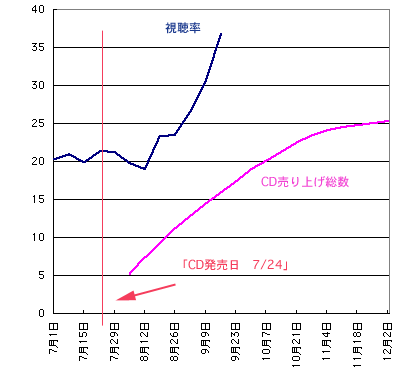

まず視聴率であるが、両テレビドラマともに盛り上がりをみせ、最終回に近づくにつれて、視聴率が右肩上がりに急上昇していることが分かる。
ドラマ主題歌も発売から同様に売上を伸ばしている。
特に総売り上げの伸び率を棒グラフにすると、「ラブスト-リ-は突然に」の最初の三週間の売り上げの伸び率が、「ラブスト-リ-は突然に」の最後の三週間の放送の視聴率の伸び率とほぼ平行しており、主題歌の流行とテレビドラマの人気の関係が明瞭である。
また両主題歌ともに、テレビドラマの放映が終了した後は、右肩上がりの伸び率もやや横ばいへと変化していることが分かる。
数表には、主題歌売り上げの週順位が出ているが、テレビドラマ放送中は常に売り上げ1位を示しており、テレビドラマ放映中により顕著に売り上げが高いことが分かる。
注目したいのは、主題歌はドラマが盛り上がる放送の3~5回目まで、発売なされていないことである。つまり、放送が始まったころは、テレビでしか主題歌は聞けないわけである。視聴者がテレビで2度ほどしか流れない主題歌を、「別の場所で聞きたい」「何度も聞きたい」と思ったころに、狙いを定めてCDを発売するという販促方法があるようである。
CDの売上の伸びとドラマ視聴率の伸びは、見事にシンクロしていて、「囲い込み」の効果は容易に推測できるといえるだろう。
このように、主題歌の流行現象とは、テレビドラマの人気と相互作用的に生まれた現象であることが分かる。この相互作用のことをメディア戦略的には、一般に「タイアップ」と言う。そこで次にこの「タイアップ」という手法について分析しておきたい。
第2節 「タイアップ」というブロックバスター型メディア戦略
第二に、テレビドラマで主題歌を用いる「タイアップ」という手法の効果をある程度、把握しておきたいと思う。
図7は、1991年に発売されたシングルCDの売上上位100曲(オリジナル・コンフィデンス社調べ)を対象に、「タイアップ」先、つまり他のメディアでこれらの楽曲を使用しているかどうかを示したものである。
図7 1991年シングルレコード売り上げベスト100タイアップ先内訳(%)

オリジナルコンフィデンス調べ(オリコン年鑑 1992年)
コマーシャルが33%と最も多く、テレビドラマが「タイアップ」先の楽曲は21%となっている。「タイアップ」のないものは27で%ある。つまり、70%以上は何らかの形で映像メディアと「タイアップ」していることが分かる。ここから楽曲のヒットや流行に、映像メディアがいかに大きな役割を果たしているかが理解できる。「タイアップ」とは現在、最も強力な流行現象の原因となっているようである。
すでに第二章で触れたが、広告音楽の目的はイメ-ジづけと販売促進であった。主題歌はドラマという商品をイメ-ジづけ販売促進(この場合、テレビの商品性を計ることができる視聴率のアップ)するためのものだと考えられる。さらに主題歌はドラマがあってこそ意味付けが行われるという二重性を持っている。音楽イメージにより、「モノに対する共通感覚的なイメ-ジ」形成が見られ、そのイメ-ジによる集団形成がある。
「モノに対する共通感覚的なイメージ」といっても分かりづらいので、CM音楽を例にとって、説明したい。
図8は、1991年のシングルレコード売上トップ100のうち、広告CMとタイアップしていた曲の、広告内容内訳である。
図8 タイアップ曲の広告内容内訳(%)
自動車 5 宝飾品 11 化粧品 11 音響機器 19 食料品 24 企業広告 22 旅行など 8
オリジナルコンフィデンス(オリコン年鑑)
「食料品」のCMが多いが、そのなかの小分類内訳では「飲料関係」が多い傾向が見らている。特に「酒・アルコール」が多い傾向であった。アルコールという嗜好品として付加された価値が商品のものが、音楽でイメージ付けされているわけである。
音響機器は、イメージが直接、音楽である。
企業広告も、広告の性質じたいが、イメ-ジ付けの性質を帯びていて、音楽が適当な媒体となったようである。
このデータは、数値よりもその内容内訳が重要だ。というのも広告全体の量とは比較していないからだ。このように「モノに対する共通感覚的なイメージ」とは、「機能と価値の間」を「埋める」ものとなっているようである。
図9は、1991年のシングルレコード売上数ベスト10の「19911年通算売上数」「タイアップ先」「オリコン誌に初登場した時の、売上数と順位」を表している。
図9 1991年 CD年間売上トップ10

この表から次のようなことが分かる。
1、「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」の売上が、他を引き離して抜群に高いことである。10位のB'Zの売上数の4倍近くである。
2、「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」は、初登場時の売上数が、他と比較にならないほど多いことが分かる。「ラブストーリーは突然に」が、発売した週に売れた数は、Dreams Come Trueが1年かけて売った数より多いのである。
3、タイアップ先がドラマの曲のほうが、タイアップ先がCMやバラエティー番組より、初登場時の売上数が比較的高めである。そのほとんどのテレビドラマはフジテレビで放映されている。ちなみにタイアップ先のない曲の最高順位は、米米クラブの27位が最高となっている。
以上のことから、ドラマの主題歌が、非常に特徴的な売上スタイルを示すことが分かる。明らかにテレビドラマと関連があるようである。そして、その中でも「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」はにその傾向が顕著である。「イメージ」というものをメディア戦略に組み込んでいった結果、こうした現象が生まれてきたのである。
第3節 主題歌と象徴
Resolution
Acknowledgement
Pursuance
Psalm
John Coltrane 「Love Supreme」
CMソング、イメ-ジソングがCMの持つメッセ-ジや広告意図を内包して伝達されたように、ドラマの主題歌もドラマの内容を持ち合わせていたのだろうか。まずは歌詞の世界を分析して、テレビドラマと主題歌の関連を見ていきたい。
(1)「ラブストーリーは突然に」の歌詞の内容分析
~歌詞 右参照~
「ラブストーリーは突然に」
何から伝えればいいのか
分からないまま時は流れて
浮かんでは 消えていく
ありふれた言葉だけ
君があんまり素敵だから
ただ素直に好きと言えないで
たぶんもうすぐ 雨も止んで
二人 黄昏
あの日 あの時 あの場所で
君に逢えなかったら
僕らはいつまでも
見知らぬ二人のまま
誰かが甘く誘う言葉に
もう心揺れたりしないで
せつないけど そんなふうに
心はしばれない
明日になれな君もきっと
今よりもっと好きになる
その統べてが 僕の中で
時を 越えていく
君のために 翼になる 君を守り続ける
柔らかく 君をつつむ
あの 風になる
あの日 あの時 あの場所で
君に逢えなかったら
僕らはいつまでも
見知らぬ二人のまま
今 君の心が 動いた
言葉 止めて 肩を よせて
僕は 忘れない この日を
君を誰にも渡さない
誰かが甘く誘う言葉に
もう心揺れたりしないで
君を包む あの 風になる
「主体」は〔僕〕、「客体」は〔君〕である。
〔僕〕は〔あの日・あの時・あの場所〕で〔君〕と〔逢え〕る。
〔逢えなかったら見知らぬ二人のまま〕という逆説から「出会い」の強調が示されている。
出会いの次の段階として「意思の伝達」が提示されている。
〔僕〕は〔君〕が〔好き〕なのだが、〔君があんまり素敵〕なのを理由に〔ありふれた言葉〕に〔時は流れて〕〔伝え〕られない。
〔二人黄昏〕という言葉から実は〔君〕である人も〔僕〕を好きであると思われる。
〔誰かが甘く誘う言葉〕は恋愛における「事件」の表象だ。
〔もう〕という言葉から「事件」の実在性を確認できる。
〔明日になれば~越えていく〕は恋愛という物語の「連続する時間性」のあらわれである。
〔時を越え〕ることにより〔僕〕は「愛」を手に入れる。
〔そのすべて〕とは〔君〕が〔僕〕を愛する心であって、歌詞全体における〔時〕を意味するものはここで〔僕〕の「愛」の象徴として定義されている。
〔君のために~風になる〕は〔僕〕の「愛の行為」である。
〔翼〕と〔風〕が事件に関する「嫉妬」〔切ない・心は縛れない〕の対局にある自由を表して愛の「成就」を示す。
これまで「愛」の変形であった〔言葉〕を〔止めて〕、「愛」の形は〔肩をよせて〕といった「肉体」の関係に移り変わっていく。
最終的に〔僕〕は〔君を誰にも渡さない〕という宣言のもとに「愛」の「永続性」を宣言する。
〔この日〕を忘れないことは「時間=愛」という形式の確認であり〔心 揺れたりしないで〕と愛を乱す新たな事件が起きないように祈り、終わる。
「ラブストリ-は突然に」というタイトル自体もそうであるが、歌詞の内容は「出会い→伝達→事件→迷い→成就→不安と歓喜」というような構造を持つ恋愛物語である。
(2)「SAY YES」の歌詞の内容分析
~歌詞右参照
「SAY YES」
余計な ものなどないよね
全てが君と僕との
愛の構えさ
少しぐらいの 嘘やわがままも
まるで僕を 試すような
恋人の フレーズになる
このまま二人で
夢をそろえて
何気なく
暮らさないか
愛には愛で 感じ合おうよ
ガラスケースに並ばないように
何度も言うよ 残さずいうよ
君が溢れてる
言葉は心を越えない
とても伝えたがるけど
心に勝てない
君に会いたくて 会えなくて 寂しい夜
恋人の 刹那さ知った
このまま二人で
朝を迎えて
いつまでも
暮らさないか
愛には愛で 感じ合おうよ
恋の手触り 消えないように
何度も言うよ 君は確かに
僕を愛してる
迷わずに
SAY YES
迷わずに
登場人物の「主体」が〔僕〕、「誘惑」される側が〔君〕である。
時間、情景、登場人物に関する情報提供子は一切示されない(〔恋人〕であること以外)。
さらに歌詞は、段落で区切られた単位により、それ自体で意味をなす機能体として存在しつつも、その前後の文脈の相関関係はほとんどみられない。
一つの文脈はそれ自体で完結していて閉じた構造を持っている。
さらに物語としての始まりと終わりがない。
存在するのは登場人物の意識・感情のみである。
そして、分布的で意味提示的な文脈の羅列に生成される物語のテ-マは「愛」である。
〔余計なもの〕は〔無〕く〔すべて〕が「愛」である。
〔少しぐらいの嘘やわがまま〕も「愛」であり、〔愛〕が〔僕〕を〔試す〕(=試練)という認識も〔愛の構え〕の一つである。
〔このまま~暮らさないか〕は〔僕〕の「愛」の認識の一つとして提示される。
〔僕〕にとって〔暮ら〕すことは〔愛で感じあう〕方法である。
「愛情と伝達」の欲求は、〔逢いたくて〕=「愛情の欲求」、〔とても伝えたがるけど〕=「伝達の欲求」のように示され、〔逢えない〕〔心に勝てない〕というように「抑圧」されている。そして(知る)のは〔切なさ〕である。
〔僕〕は〔君〕に対して「愛」を与えかつ求めるという立場にある。
さらに〔言葉〕〔逢う〕の二つが「愛」の認識として意味されること分かる。
最後に〔SAY YES〕という語りかけで終わっているが、〔YES〕は与えられた〔愛〕への「解答」の形態として示されている。
「SAY YES」には「ラブストリ-は突然に」のように明示的な構造を持つ「物語」ではない。「言語的なもの」をその指し示すものを用いずに提示したものである。「愛の欲求」がそれである。詩は要約できないとよく言われるが「SAY YES」は要約できないのである。
(3)「SAY YES」と「ラブストリ-は突然に」の共通性
二つの歌詞に共通することは、場所・登場人物・時間を具体的に示した言葉が示されていないことである。
ただ〔僕・君〕〔あの日・あの場所〕というように、抽象的で非明示的にのみみられる(SAY YESに関しては抽象的にも示されてない)。
また〔僕・君〕という「主体」には「男女」というジェンダーに関する設定はなされていない。歌詞の中で「主体」と「客体」の入れ代わりは見られず、「愛」の「送り手」は常に〔僕〕で「受け手」は〔君〕である。
場所や時間の限定もないので、歌詞は「万人に共通にあてはめられる可能性をもつテクスト」なのである。つまり〔僕〕に男性を、あるいは女性を代入してもそれを遮るような具体的記述はないので、意味の成立においては特に差し支えがない。共通なテ-マである〔愛〕は人間の基本的な社会的・心理的欲求でもあり、そのテ-マ性を訴えられる範囲は極めて広範である。
ドラマのテ-マは既に示した通り「AFFECTION」である。論の後半では、その内容をドラマのほうから詳しく見ていくことにするが、主題歌の歌詞内容のテーマはテレビドラマのテ-マ性に沿ったものであるといえる。実際、「東京ラブストーリー」のセリフには、主題歌の歌詞と全く同じ言葉が見られた場合もある。
「SAY YES」での〔暮らす〕ことは結婚を表しているといえ、この点も「101回目のプロポーズ」の内容に対応している。
「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」の違いについても見ておきたい。「東京ラブストーリー」においては「ラブストーリーは突然に」がその構造を示しており明示的に指し示す対象を持つのにに対し、「101回目のプロポーズ」では「SAY YES」は内容の象徴であり、ストーリーの潜在的な意味内容の提示である。
換言すれば、「ラブストーリーは突然に」が「物語というモノ」の提示をするに対し、「SAY YES」が「愛という物語のもつコンセプト・イメージ」を提示するというように考えられる。この違いと役割から、主題歌はある種の広告音楽的である。広告音楽の歴史からも見てきたように、メロディーに商品名の連呼といったごく初期的な広告音楽の形態に「ラブストーリーは突然に」が当てはまる。この場合の商品は「テレビドラマ」である。商品-モノは曲名や歌詞になり、放送によって露出され繰り返され、曲とモノを連結する。それに対して「SAY YES」の場合は、提示するものは商品としてのドラマのコンセプト、つまり生活様式であり生活感覚であった。この点でイメージソング的なのである。
主題歌の言語的メッセ-ジは、音楽的メッセージと一体化し、言語的メッセージは歌詞として、ドラマの内容を彷彿させドラマの印象をイメージ付ける。一方、音楽的メッセージは、恋の生活様式とあこがれを印象として提示している。これら言語的メッセージと音楽的メッセージによって植えつけられたイメージを持つモノは,それ自体メッセ-ジ性をもつドラマであり、「機能と価値の間」を「往復」しながら、イメージとモノの間を彷徨うのである。
第4節 主題歌の音楽的テクスト
「テレビドラマの人気があったから」というだけの理由で、「ラブストーリーは突然に」「SAY YES」が売れたわけではなさそうである。歌自体にも流行現象となった原因があろう。
演奏するア-ティストの力も忘れられない。広告音楽は作られるイメージをアーティストに期待して、始めから売れるような、曲かア-ティストを使うことが多い。「ラブストーリ-は突然に」を歌う小田和正も「SAY YES」を歌うChage&Askaも事実「超」のつく売れっ子である。小田和正は、1970年代終わりから1980年初頭にかけて「オフコース」というバンドで大活躍したのち、1985年からソロ活動をしている。作詞・作曲・プロデューサー・アレンジャーとして多くの曲を手掛けるビッグアーティストだ。Chage&Askaは、1979年にデビューして以来、20枚もアルバムを出すベテランだ。Aska(飛鳥涼)は提供楽曲ヒットも多く、Chage(チャゲ)は最近にソロ活動も行う。売れるべくして売れたといっても過言でない。
音楽自体の雰囲気などはどうであったか。ごく主観的であるが、その感覚的共通点と特徴を上げておきたい。メロディーは切ない悲しさや不安を持ちつつ希望的であって決して暗くない。コード感、ハーモニーも同印象だ。アレンジは至極現代的であり機械仕掛けの人間的リズム、重厚かつ厭味のないストリングス、1991年のブームの一つだったAORリバイバル(1980年代初頭に流行した、大人の洗練された都会派ロック Adult Oriented Rock)の影響も見えるような曲に仕上がっている。コンテンポラリーなサウンドは実に聞きやすい。
第5節 主題歌の露出とイメージ付け
では、このような特徴を持つ主題歌が、どのようにテレビドラマのなかで用いられ、そしてどのようにイメージ付けをしていったのか、考察をしていきたい。
テレビドラマ内での主題歌の露出について考えてみたい。主題歌はテレビドラマの番組中に何度となく流れる。図10-1は「ラブストーリーは突然に」、図10-2は「SAY YES」がドラマ中のどこで何回流されたかを示している。
図10-1 「東京ラブストーリー」の主題歌の露出
放送回
放送日
放送タイトル
シーンの概略
主題歌の曲調
第1回
1/7
出会いと再開
冒頭
赤名リカと永尾完治(カンチ)の出会い
三上が関口のキスシーンを目撃
フルコーラス
インスト
1番
第2回
1/4
愛ってやつは
冒頭
----------
----------
フルコーラス
インスト
1番
第3回
1/21
二人の始まり
冒頭
----------
----------
フルコーラス
インスト
1番
第4回
1/28
君の翼になる
冒頭
----------
----------
フルコーラス
インスト
1番
第5回
2/4
いつも思い出して
冒頭
リカとカンチのデート
三上を待つ関口、カンチに電話
関口と会ったカンチ、リカの前で仕事と嘘を。怒るリカが家を出る
フルコーラス
インスト
インスト(マイナー調)
フルコーラス
第6回
2/11
赤い糸に結ばれて
冒頭
----------
----------
----------
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
第7回
2/18
愛は待たない
冒頭
----------
----------
リカの買った愛媛行きの切符を見つけたカンチ、感動して抱き合う
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
第8回
2/25
この恋を信じたい
冒頭
----------
----------
カンチとうまくいかないリカ、和賀と公演で相談
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
第9回
3/4
行かないで
冒頭
----------
カンチがリカに「俺なんてよせよ」と突き放す
カンチがリカに会いに行こうとするのを、関口が「行かないで」
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
フルコーラス
第10回
3/11
約束
冒頭
----------
----------
----------
----------
愛媛のカンチの母校、カンチの落書きにリカの名前が
フルコーラス
インスト
インスト
インスト
インスト
フルコーラス
最終回
3/18
さよなら
冒頭
----------
----------
3年後、偶然リカと出会うカンチ、少し話をして別れる
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
図10-2 「101回目のプロポーズ」の主題歌の露出
放送回
放送日
放送タイトル
シーンの概略
主題歌の曲調
第1回
7/1
運命のお見合い
冒頭
知恵が達郎に、薫が昔受けたプロポーズの言葉を教える
達郎、練習場に乗り込み、教わったセリフを叫ぶ
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第2回
7/8
一生に一度の賭け
冒頭
薫、コンサートチケットを達郎に渡す
ボーナスを競馬に注ぎ込んで、薫に見せに来る
競馬ははずれ。薫は感動するが「好きにはならない」
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
インスト
第3回
7/15
僕が幸せにします
冒頭
薫の誤解を解く
公園で達郎と薫が会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
第4回
7/22
愛が動くとき
冒頭
達郎と薫の部屋の描写
達郎、薫の親と食事
薫、達郎が薫の父親の説得したことへ礼を言う
達郎は、静岡に帰った薫を迎えに行く
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第5回
7/29
愛のない結婚できますか
冒頭
結婚について話す各登場人物
達郎と薫のデート
達郎と薫の食事
達郎、以前の婚約者にばったり会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト+コーラス
インスト
フルコーラス(フェイドイン/二番のみ)
第6回
8/5
婚約
冒頭
回想シーン
薫、達郎が好きであることを告げるが..
トラックに突っ込む達郎、「僕は死にません、あなたを幸せにします」
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第7回
8/12
まさかあの人が
冒頭
婚約を発表、薫は知恵に、達郎は純平に
達郎、真壁の墓参りに行く
達郎と薫の婚約パーティ
薫、真壁とそっくりの人物と出会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第8回
8/19
悲しき婚約指輪
冒頭
達郎、薫に無理矢理婚約指輪をはめようとする
薫、藤井の家で抱き合う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第9回
8/26
婚約者を取り戻せ
冒頭
達郎、薫の父親と酒を飲む
薫、藤井と以前結婚するはずだった場所へ
達郎は、桃子に過去の薫の結婚式場を教わり、向かう
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第10回
9/2
僕はあきらめない
冒頭
薫のさよなら宣言
あぜんとして、何も手に付かない達郎
達郎、薫の前で弁護士になると宣言。あきらめない。
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第11回
9/9
愛の女神よ
冒頭
試験勉強をする達郎1
試験勉強をする達郎2
試験勉強をする達郎3
達郎と薫、いつものバーで久々に会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
最終回
9/16
SAY YES
冒頭
過去の回想
留守の達郎にお守りを届ける薫
薫、コンサート途中に立ち上がり、教会へ
試験に落ちた達郎
薫、夜の街をウェディングドレスを着て駆けてくる
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
上記の表のように、主題歌がある特定の場面で露出していることがわかる。
まず、冒頭で俳優やキャストの紹介とともに「ラブストーリーは突然に」は全曲、「SAY YES」は2番から流れる。冒頭での露出により、この2曲が主題歌であり、テーマ曲であることが示される。
ドラマの中では、それぞれの曲が、歌なしのインストロメンタルになって、特定の場面で流れる。「東京ラブストーリー」は永尾完治と赤名リカの心情と行動描写中心の展開であるが、二人に心情や行動の変化に合わせて「ラブストーリーは突然に」が明るい調子になったり、静かな調子になったり、あるいはマイナー調のやや暗い感じになって流される。
私たちがドラマを見るという行為は、ある意味でドラマの中に自分を置き、あるいは自分の中にドラマを引き寄せ、その中の世界を生きることによって、展開する物語を再構造化し、その世界を認識することである。しかし、主題歌は、ある特定の場面が、その物語における鍵となり、感情想起のトリガーとなることを、さりげなく視聴者に示している。「東京ラブストーリー」では「シーンの概略」データが抜けてしまっていることが多いが、こうした視聴行動に一定の指針を与えているのである。
このインストロメンタルは、冒頭と異なり、「いかにも主題歌」というような主張はしない。よって、その存在は希薄であると言ってよい。しかし、データからも分かるようにそのインストは、一回の放送で、少なくとも2回、多いときは4回は流れている。
着目すべき点は、放送期間が後であった「101回目のプロポーズ」のほうが、インストロメンタルの曲をより多く使っている点である。
「SAY YES」がイメージ的な歌詞内容を持つことから、効果的に感情想起の道具となっていることがあげられよう。「SAY YES」がインストとして流された場面を見てみると、「達郎」が主体のときと「薫」が主体のときと、比較的に均等にインストロメンタルが流されている。また、主体が複数あるような描写の場合にも同様に用いられている。つまり、「求める/拒む」というストーリーの主体の位置付けによらず、「SAY YES」はその「愛の欲求」というテーマを刷り込んでいるのである。
また、これは「シングルCD」の販売日時や売り上げと関係していると思われる。実はテレビドラマの第5回の放送までは、両テレビドラマの主題歌ともに、発売がされていないのである。つまり、市場との関わりである。
歌ありのフルコーラスが必ず一回はストーリー中に流される。両テレビドラマとも54分、11-12週にわたって放映されたが、それぞれ一話づつが、必ずある種の物語として完結している設定になっている。そして、それぞれにクライマックスがある。図5-1/5-2には簡単にそのクライマックスシ-ンが書かれている。制作上は実に巧妙で「ハッ」とするシ-ンに、うまく曲の「アタック」を乗せている。例えば、ドアを閉めた瞬間であったり、恋敵とのキスシーンであったり、である。ストーリー中のフルコーラスの露出度はドラマが盛り上がるにつれて多くなっている。
「SAY YES」を音楽的に分析すると、イントロの第一音、つまり曲の始まる瞬間に、各楽器が一斉に音を伸ばしている「アタック」がある。俗っぽく言えば「ガ~~ン」というような感情のような音である。その後に、やや静かになり、鐘の音のような静かに、しかし重く鳴り響くような音でメロディーを奏でる。このアタックと静寂が、登場人物の心境のいわば「ショック」と「無力感」のようなものを表現している。
「ラブストーリーは突然に」も同様に、曲の始まる瞬間は、ギターだけが勢いよくコードを弾く部分がある。カッティングと呼ばれる奏法のこの音が、クライマックスシ-ンの一瞬の静寂を破り、その後に走るような勢いのある曲調へと進行する。
いずれにせよ、非常に巧妙な演出なのである。
このように、露出度の高さと強力なインパクトを与えることによる、効果的な曲の利用によって、主題歌がドラマに映像では与えられない「何か」をあたえる。一方ドラマが主題歌のイメ-ジングを行い、つまり音楽に人格を与えて、視聴者に送りだす。テレビドラマが主題歌に与えたイメ-ジは「愛と感動」である。そして視聴者は「愛と感動」といった人格を持った音楽に、意識的にも無意識的にも、何度も触れることになる。
視聴者は、自らの経験から、主題歌を愛の歌と認識するのを止め、ドラマに触れるという非現実表象が提示する経験から、主題歌を愛の歌であると認識しはじめることになる。ここには、なにも出会い→告白→成就といった図式や結婚形態だけが愛ではないことや、「ラブストーリーは突然に」は愛の歌ではないかもしれないことは、ストーリーテラーの関心外である。テクストは既に作動しているのである。
第6節 主題歌の流行という現象と原因
レコードが売れているってことよりも、ようやく僕等のイメージが変わってきたんだな、という感じのほうが強いですね
Chage&ASKA 「FM fun」誌インタビュ-より
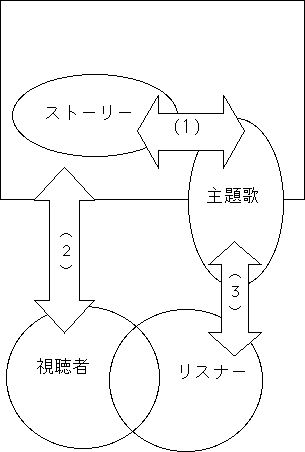 これまで説明してきたように、テレビドラマは「若者・愛」という要因でマーケットの囲い込みをした。楽曲との関連でいえば「囲いこんだ集団に音楽に興味をもつ集団を含んでいた」ということと、「音楽に注目している集団にもドラマに注目させ囲いこんだ」という二つの事象を説明できよう。
これまで説明してきたように、テレビドラマは「若者・愛」という要因でマーケットの囲い込みをした。楽曲との関連でいえば「囲いこんだ集団に音楽に興味をもつ集団を含んでいた」ということと、「音楽に注目している集団にもドラマに注目させ囲いこんだ」という二つの事象を説明できよう。
「SAY YES」「ラブストーリ-は突然に」はこの様に作りだされた、あまりにも漠然としていながら差異を内に含む巨大なマ-ケットの創出によってあのようなセ-ルスが可能となったといえよう。
さきほど歌詞の分析をしたように二つの主題歌は、主体に制限のない構造や、内容の単位においての抽象性を持ち合わせていた。この主題歌は、視聴者がテレビドラマにチャンネルを回したとき(これはリスナーが心に組み込んで物語る以前の段階において)意味とテレビドラマのコンテクストを与えられる。主題歌はドラマを記号化したものである。
歌詞の内容分析でみたきたように、歌詞というメッセージのなかで、物語は完成しておらず、消費者の参加(意味的に、あるいは、ドラマを見て主題歌を聞いて、CDを買って.......)をもってその物語は完成を見るのである。リスナ-が、自分の経験なり心情なりをこの2つの歌に代入し、それぞれ各人の物語を作りだすこと。歌はこうしたテクストの作用から耳にした者を逃さない。それは参加・想像・創作への消費者満足でもある。マーケッターからみれば、複雑な社会心理を持つ(「感性」とか言われるもの)消費者群に対し、抽象的な枠(この場合歌詞のテクスト)を提示することによって、後の市場参加を消費者が意味を顕在化していく過程に任せればいいわけである。この市場が成立するか否かは、いかに消費者が「語りたがっている」物語テクストを示すかである。前章で示した流行の「T.R.E.N.D.Y.」モデルは、このような「音楽マーケット」の心理的創出でもある。
主題歌のテーマである〔愛〕は人間にとって普遍的なテーマであって、決して一時的な流行ではない。人間に必要不可欠な〔愛〕のテクストの提示は、消費者ニ-ズを巻き込んみ、しっかりと掴んだ商品となった。
主題歌は、音楽CDとして流通することによって「一人歩き現象」が見られよう。ドラマの主題歌はドラマの枠を飛び出し、一つの音楽としてリスナーに聞かれるようになるのである。各種の音楽メディアに乗って、より多くのリスナ-に聞かれるようになる。もはやドラマの視聴者だけが「主題歌」とフレーム付けられた音楽に触れるのではない。
音楽自体の解説で触れたように、コンテンポラリ-な2曲はより多くの音楽ファンにアピールした。このことはドラマという商品がターゲットとしたマーケットを、大幅に拡大した。つまり、ドラマのファン以外である音楽ファン層を、ドラマに注目させる可能性が出てきたといえよう。テレビドラマは、その強烈なイメージングにより、市場を形成し拡大する。一方、主題歌はテレビドラマのマーケットを形成し拡大する(右図 参照)。
広告音楽が必ずしもリスナー全体に効果があるとは考えず、音楽的共通認識のもとにある、集団を作りだし、効果の可能性を集団に対して求めているように、ドラマの主題歌も効果の可能性を求めたものである。しかしその対象とする、あるいは作ろうとする共通認識の集団=マーケットは、イメージの世界と相互作用しながら、二重・三重に広がる広範なものである。
第4章 ドラマ・現実・虚構
第1節 トレンディドラマのシミュラークル性
偽物を本物から区別したり、実在をその人為的復活から区分する最後の審判も存在しない。なぜならすべては、すでに死に絶え、前もって蘇っているからだ
J・ボ-ドリヤ-ル 「シミュレ-ションとシミュラ-クル」より
本論後半の第4章から第6章では、トレンディドラマの内容分析を行い、こうした内容の現代的意味を明らかにすると同時に、視聴者である「受け手」がいかなる様式のメディア・コミュニケーションに対峙するのかに着目する。これまでの章では、トレンディードラマに関わる現象が「いかにして生じてきたか」「いかにして現にそのように存在したのか」ということを論じてきた。次には、その現象が持つ「私たちへの関係=機能」を論じようと思う。
こうした「機能」を考察するとき、ドラマ試聴を通じた「現実」と「虚構」の交錯に着目しておきたい。テレビドラマとは既に定義したように「虚構」にほかならない。それは「現実」にはどこにも在りえなかった世界であり、テレビの窓の中において以外では決して触れることのできないものである。作られた物語であり演劇である。視聴者がその世界とコミュニケートすること、言い換えれば、ドラマの世界と相互に作用しあうことはありえない。
しかし、テレビが作りだす世界は視覚的素材が「現実」の「モノ」である。認識ができる「現在」であって、存在する「モノ」が映し出されている。つまりドラマは私たち「人間」そして「社会」「生活」を素材とした「シミュレーション」として「現実的」であり、現実から構成された「虚構」である。
J・ボードリヤールは著書「シミュレーションとシミュラークル」において、画像が「シミュレーション」であることを指摘し、さらにそれが現実と対応関係を失った、「シミュレーションのシミュレーション」、つまり「対応すべき現実を失ったシミュレーション」=「シミュラークル」であると述べている。
このシミュラークルに着目して、テレビドラマのシミュラークル性について議論してみたい。テレビドラマの素材や場所は、明らかに「現実」のモノである。一方、俳優の演じる愛の物語や生活は、私たち個々人の「現実」生活とは無関係である。独自の物語であるか、他人の生活である。しかし、価値や規範において、それをあたかも最も維持すべき必要なものと訴えかけているように感じるものも少なくないのではないか。「現実」としての視覚映像は、それが物語であることを「忘れ」させる。マス・コミュニケ-ションであるから、メディアの映像の中の世界と「受け手」が容易にはアクセスできない。こうしたことから、視聴者は、テレビドラマを「現実」と類似したものとして自分の周囲・周辺と同視する。いわゆるテレビの環境造成機能である。ボードリヤール的に見れば、それは現実の「シミュレーション」であるテレビドラマの画像を「現実的」なものとして見ることである。テレビドラマという「シミュレーション」は「現実」という実在と照合される事がなくなるということである。
一方、テレビドラマは「現実」の現在の時代や欲望を「シミュレーション」として表現しているのであろうか。視聴者は、テレビドラマを見て、「現実」と照合せず、その「シミュラークル」の中でしか生きていないという、「虚構の現実化」をしているのであろうか。否である。
少なくとも、視聴者はテレビドラマを「虚構」として認識し、それが「現実」ではないことをよく知っているようである。例をあげてみよう。「東京ラブストーリー」の主人公である赤名リカのような勝手気ままな女性に、多大な魅力を感じる東京ラブストーリーの男性陣......日常会話で「なんか違う」という話はよく耳にしたものである。「101回目のプロポーズ」における浅野温子と武田鉄矢の結婚、ひたむきな愛の答えにウェディングドレスで夜の街を走る薫........例をあげればきりがないが、明らかに「現実」の行動としては考えられない部分が多い。トレンディードラマはいわゆる娯楽モノとして捉えられている。私たちがドラマをみて笑っている段階で、既にそれは「現実」性の否定であると考えてもいいだろう。
「101回目のプロポーズ」において、登場人物の設定では、武田鉄矢と江口洋介は兄弟である。放映中に江口が友人に「兄弟であることが信じられない」と指摘される場面があった。江口は「髪形が似ているだろ」「昔はもっと似ていたんだ」と答えている。これは一つのコメディ・シーンなのだが、このようなコメディ・シーンが用いられているのは、武田鉄矢が若いころは江口洋介のような髪形をしていたが、決して現実の兄弟ではなく、髪形だけが似ていて、その外見にギャップがあることが、おおむね視聴者に理解されているからである。
視聴者はテレビのスイッチを入れることで、フィクションの世界に入り込みながら、引っ張りこまれたままになることなく、ある距離を保っている。さらにテレビドラマの側からしばしば「非現実感」を助長して、視聴者を「現実」に押し戻す。上の例であれば、主人公と準主人の兄弟のコメディ・シーンが「非現実感」を助長して、二人が俳優であるという「現実」のバックグラウンドを呼び起こし、「現実」に押し戻しているのである。
つまり、ドラマはその「虚構性・非現実性」により、視聴者に「現実」をそして日常を強く意識させるものとなるのだ。「虚構」が「意識」させる「現実的」なもの。これこそボードリヤールのいう「シュミラークル」にほかならない。視聴者はテレビドラマの「虚構性・非現実性」を理解しているからこそ、その対極にある自らの「構成的な現実認識」を強くするのである。
テレビドラマは決して価値・規範を強制したり、視聴者をその枠の中に単純に組み入れたりはしない。その意味でテレビドラマの影響力とは、極めて限定的なものである。しかし、テレビドラマの「非現実性」に気付いている視聴者が、それを楽しむことそのものが、そして、その精神が「シュミラークル」を生み、見えない影響力というテレビドラマの機能がそこに果たされるのである。
既存の価値・規範を繰り返し強化して画一化して規格化していく「機械」。これこそドラマの持つ潜在的機能であり、権力構造である。ドゥルース&ガタリが論じるように、メディアの性質である「断片化や分離化」は機械的性格である。テレビドラマは視聴という文脈において、個々の経験と関心により断片化され、「現実と虚構」に「シミュラークル的」に分離されるのであろう。ドゥルース&ガタリは「機械」について、静的な構造から差異による一元的な結果を生む概念として、そして、動的な自己再生産の形式としてとらえている。こうした「断片化や分離化」は、テレビドラマをめぐる私達の「自動機械化」であり、メディアに触れる人の感情や意思が「規格化や統一」を生産する力になると同時に、メディアに触れることによる動き自体が力となっていくのである。
こうしたテレビメディアの持つ「機械」性を背景に、価値・規範や「知」そのものといった、私たちの拠り所としているものがテレビドラマによって「権力構造」に包括されていくのである。この場合の「権力」とは、フ-コ-が論じるように、「行使されたり利用されたりする力ではなく、人が接する関係自体」という概念である。また、「知」についてもフーコーが述べるように、「環境や物の見方、言語の表現などの在り方を支える認識の体系」を念頭においてある。
一般的なマス・コミュニケーション論によれば、「テレビでの認知は欲求の増大につながっても、直接の購買に結びつきにくい」ということは、これまでしばしば指摘されている。テレビドラマの場合はどうであろうか。テレビドラマの中の生活を見て、そのままの形で消費に転嫁することがあるだろうか。これは上に同じであろう。「虚構」をそのまま「現実」として、消費行動に結び付けることは少ないといえるだろう。
社会心理学的に考察するならば、欲求とその充足の過程をふまえる必要がある。消費行動を引き起こす動機の問題である。欲求とは「生活体の生理的あるいは心理的状態が、なにかの不足や過剰によって安定した均衡を失った状態」をさすとされている。そしてその不足を何らかの行動で足す、あるいは過剰を消し去ることで充足する。テレビドラマの場合で考えるなら、不足や過剰がドラマによって与えられたイメ-ジであろう。一つは「虚構」としてのイメージであり、もう一つが現実の価値・規範に照らされながらもドラマによって生み出された「シミュラークル」としてのイメ-ジである。
そのイメ-ジを「現実化」させること、つまり消費行動によってイメージを消し去る、つまりイメ-ジを消費することによって充足することになるはずであるが、それは直接的な行動では示されないことは既に述べた。では社会心理学的に考えると、テレビドラマの「シミュラークル性」とはどうとらえればよいのであろうか。そこで欲求の質をふまえて議論してみたい。人間の欲求には生理的欲求と社会的欲求がある。後者は人間自身の内で作りだせるものではない。後天的に学習されるものであって、外からの与えられたものだ。メディアによって明確なイメ-ジが与えられ続ける中、私たちの満足への指向は、与えられたイメージの「現実化」という間接的な意味での消費に向けられる。
私たちはテレビドラマに存在するモノの直接的な消費は行わなくとも、それを見ることで生み出された個人それぞれの価値・規範に影響されたイメ-ジを消費しているのである。そしてテレビドラマは無限に続く「シミュラークル」の円環によって、画一化・規格化された価値・規範を視聴者のなかで無限に生成し、確実に消費されるイメ-ジを生成しているのである。この「消費されるイメ-ジ」とは........あらゆる行為の根幹となる「意味」を生成することなのである。
第2節 トレンディドラマ分析の意義
「101回目のプロポーズ」と「東京ラブストーリー」を分析することによって明らかにしたいことはマス・メディア内容に関することだけではない。
しばしば内容分析という手法は、その意義が不明確であることが指摘されることが多い。一般的には、「いったいなぜこのようなことを行うのかが不明である」と言われることが多いように思う。また「内容分析の結果がどう生かされるのかが不明である」という意見も多いように思う。たしかに、メディアの効果や利用の形態が内容という変数と関連しているかどうか、実証的に明らかにしずらいという部分はあろう。こうした点で、禁欲的になっているという側面もあるのかもしれない。
しかし私は実証的な点については譲るにしても、内容分析を通じたメディアの総過程の分析にあえて挑戦してみたいと思う。しかし、その方法はいわゆるマス・コミュニケーション研究の手法に基づいたものではない。個々の方法については個々の分析の前に論じるつもりであるが、以下のように、分析の目的と方法を示しておこう。
分析の目的をまとめて言うなら、「冗談」や「趣味」「愛」「便利さ」「常識」といったような、私たちの生活に欠かせなくて、しかも、自らの意思で自由であると思っているものにある、隠された操作や支配の体系や、自らががんじがらめになっている枠のようなものを、見つけるということだ。
方法について言うなら、テレビドラマから、多くの事象に共通する上のような「権力の構造」を見つけていくために、構造主義や記号論、テクスト分析など方法を採用する。
ピアジェは構造について「定式化と変換の様式」と定義しており、レヴィ・ストロースは「要素と要素間の関係からなる全体であって、この関係は、一連の変換過程を通じて不変の特性を維持する」と言っているが、物語と視聴をめぐる空間を構造的にとらえることにより、なにが定式化されなにが変換されるのか、こうしたことについて明らかにしていきたい。
以下の章は「101回目のプロポーズ」と「東京ラブストーリー」の構造テクスト分析の試みである。「101回目のプロポーズ」の分析では、内容の要素を記号化することで、ドラマだけではない、メディア自体や試聴行為といったことに言及できるような「変換様式」を作る。いわゆる構造分析という方法を用いる。「東京ラブストーリー」では精神分析のな見方を中心に、メディア・テクストの分析を行う。
第5章 「101回目のプロポーズ」の構造テクスト分析
分析対象となるテレビドラマ「101回目のプロポーズ」は、1991年7月1日から9月16日までの期間に、一回の放映あたり広告を含めて54分、毎週一回12回で全12回の放映が行われた。時間にして10時間48分にあたる。
対象となる放映をビデオテープで録画し、分析を行った。
各放映ごとのタイトルなどは図10-2(第3章)に示してある。放映においてドラマは毎週50分の単位で終了し、週単位で完結した物語を内に含むが、それ自体が物語構造の単位とは限らない。意味的な単位は放送の枠を越えた、大きな物語に位置付けられるものである。よって以下の分析では、放映単位を基準としてはいない。
以下、「登場人物」を単位とした分析(第一節)、「用いられるモノ」を単位とした分析(第二節)、登場人物の「感情」を単位とした分析(第三節)を行う。
次に「視聴行動」について議論し(第四節)、第一節に対応する現実の人口統計調査(第五節)や、第二節に対応する「指輪」の意識調査(第六節)、第三節に対応する「結婚観」の意識調査(第七節)などを分析し、テレビドラマの意味作用について考察する。
第一節 登場人物の指標 ~主体と構造~
第一に、主体の行為に着目しながら、この「101回目のプロポーズ」を構造テクスト分析してみよう。
「101回目のプロポーズ」は「お見合い」で出会う「達郎」と「薫」の二人を主体として展開していく。
「101回目のプロポーズ」特徴として、主体の二重性をあげられよう。相互の心理描写を対等に行うことによって、物語内における「送り手」と「受け手」を、同時にかつ分離不能に表現している。
行為のレベルでは二者は明らかに対等な位置付けにプロットされている。
一方、意味のレベルでは明らかに対立している。
両者は「主体」でありかつ「客体」である。
物語の発端は「お見合い(結婚しようとする男女が面会してお互いに様子を見ること)」による出会いによって始まる。
「見合い」とは以下の3点を指し示す指標となっている。
第一に、登場人物の提示である。登場人物は男女であり、かつその時点まで全く顔見知りのない他人であったことが分かる。「達郎」と「薫」は手違いによって見合い写真を見せられていず、そのため出会いの会場で相手を間違える。同時に外見的判断材料が提示される。会話内容に登場人物の社会的背景が示されている。
第二に、登場人物の物語への態度および性格等が示される。見合いへの意識が物語における「達郎」と「薫」の役割を指し示す。見合い賛成派か「達郎」で、反対派が「薫」である。このことは同時に、恋愛における二人の態度が暗示される。「達郎」が「薫」に対して恋愛的行為を示す。「薫」は行為の積極的な受け手である。
第三に、「お見合い」は結婚を暗示する。つまり今後、展開されるであろう恋愛・結婚の物語を指し示している。一見していわゆる似合わなそうなカップルである二人の恋愛物語の始まりを、出会を自体を唐突なものとし肯定することが見合いの意味となる。「お見合い」という伝統的な出会いの様式を、きわめて近代都市的な恋愛として転換するのがこの冒頭なのである。
図11は両主人公が冒頭で提示した初期情報である。
図11 主体の初期情報

物語の素材としてのその他の登場人物をみてみよう。
物語は「達郎」と「薫」の二人だけに主体の特権を与えていない。主体の複数性は「達郎」と「薫」の二人だけにとどまらず、両者の家族/友人の併置のなかにも見られる。
彼等自体の行為は独自に機能的シークエンスを完結させている。つまりそれだけでも物語と成立しうる。ドラマ内の構造は閉ざされてはいるが、社会的構成物として「開かれた」形式(エーコ)をとっていることがわかる。
「達郎」の弟である「純平」と「薫」の妹である「千恵」とは、「達郎」と「薫」か出会う以前に同じ大学の生徒として出会っている。二人はその後は、大学の友人として、さらに次第に淡い恋心を持つニ人として描写され、「達郎」と「薫」の恋愛物語を連続させる下位構造となっている。
「純平」は「達郎」が相談を受ける部下の「涼子」に恋をする。
「千恵」は「薫」に恋をする人物「尚人」に恋をする。
「涼子」は「尚人」に恋をするが、「達郎」にも極軽い恋心を持ってている。
さらに後半に出てくる「藤井」は「達郎」の上司であって、「薫」に恋をする。
このようにテレビドラマ内で見られる社会構造は、偶然性に支配され、あるいはそれを許容する村落共同体的な小さな社会構造を示している。デュルケイムが単純な社会構造の連鎖を生物学的にとらえた環節的社会の図式であるともいえよう。図12は図式化したテレビドラマ内の関係図である。
図12 「101回目のプロポーズ」に見られる恋愛関係
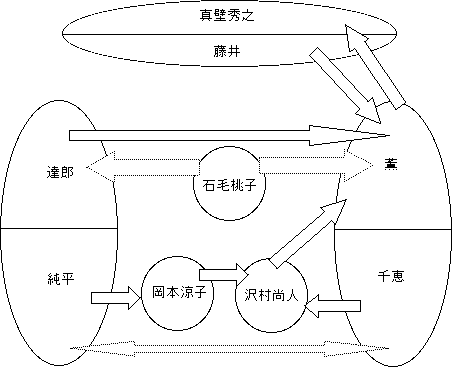
図13 プロップの行為モデル
1. 不在
2. 禁止
3. 侵害
4. 偵察
5. 引渡・漏洩
6. 詐欺
7. 共謀
8. 悪行・敵対行為
9. 仲介
10. 反作用・決定
11. 出発
12. 試練の提供
13. 試練との対面
14. 供給・準備
14-2. 魔法作用
15. 空間移動
16. 戦闘
17. 照準
18. 勝利
19. 初期不幸・欠乏の解消
20. 回帰
21. 追跡
22. 援助
23. 気づかない到着者
24. ニセの主人公の強要
25. 難題
26. 解決
27. 承認
28. 自己顕示
29. 変身
30. 処罰
31. 結婚
周囲の家族や友人などの相互交流が、出会いから恋愛成就へと移行する物語展開に、常に介在する。ロラン・バルトが物語の機能に言及したように「あらゆることがさまざまな程度に意味する」。このようにその他の登場人物は物語構造において機能的な役割を担う。
単独で意味をなさないと思われる事象も、主体および客体の上位の意味的物語に組み込まれることで意味が与えられる。
「101回目のプロポーズ」では恋愛物語が上位の意味的物語であろう。
「101回目のプロポーズ」は、物語の大部分を「達郎」の求愛と「薫」の迷いの描写に費やしている。
そのなかで、主人公「達郎」および「薫」の兄弟同士の淡い恋と友情のさまよいは、「達郎」と「薫」の物語を継続させる役割を明示することなく持つ。「純平」と「千恵」の絆が、「達郎」と「薫」を結び付ける要因となり、「純平」と「千恵」が、それぞれ別の人物と恋をすることは、恋愛による強固すぎる結び付きと、決定的な別れを回避させているのだ。つまりこうした兄弟たちの行為は物語の「補助者」としての役割を持つこととなる。さらに純枠な補助者としての「薫」の友人「桃子」や「薫」のもと婚約者の思い出など、あらゆる人物、行為、事象か物語を意味づける。行為の連関が、より上位の意昧性が付与される「シークェンス」に組み込まれて物語を形成している。
この意味で、「主人公=主体」という構造は成り立たない。しかし、意味的な構造のうちでは、主人公は物語構造の上位に組み込まれていることになる。そこで、主体の上位構造を担う主人公の二人を中心に分析していく。
上位の意味的物語である「達郎」の求愛と「薫」の迷いの場面について、いくつかの機能的な単位「シークエンス」に分割して分析を行う。
この「シークエンス」に分割のため、以下のモデルを採用する。
第一に、プロップのモデルであり、ロシア民話を31個のモデルを使って説明した(図13参照)ものである。
第二に、グレマスのモデルであり、相対する登場人物の機能を対にして類型し、適用しやすいモデルを作成していたものである(図14参照)。これは登場人物の心情や行為を、言語の文法に基づいたモデルであり、登場人物の目的論的モデルである。
図14 グレマスの行為項モデル
送り手 → 対象 → 受け手
↑
補助者 → 主体 → 反対者
この二つのモデルを用いて「101回目のプロポーズ」をテクスト分析したものを、以下に示す。
第一の単位(不在・移動・侵害・禁止)
(ストーリー)
両主体は見合いによって出会う。見合いとその後の食事で二人はまったく会話がかみ合わない。結果は「薫」からの断わりという形で締めくくられる。
(テクスト)
この場合、「不在」とは二人が出会う以前の状況である。主体の二重性のなかで、客体なき状況で主体はありえず、行為の意味は「不在」なのである。
見合いは物語行為中の「移動」である。
出会いは両者の「侵害」となる。
特に「薫」の不本意な見合いが「侵害」を強調している。過去に婚約者に結婚式当日に交通事故で死なれた「薫」にとって、「不在」への「侵害」でもある。
100回目の見合いに出向く「達郎」は相手の写真を見ていない。気の向かない見合いは「侵害」となる。
見合いの断わりが「禁止」である。
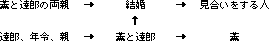
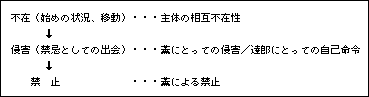
第二の単位(共謀・仲介・出発)
(ストーリー)
「達郎」は「薫」の妹から「薫の以前の婚約者」のプロポーズの言葉を教えられる。有名なセリフ「僕は誓う。50年後の君を今と変わらず愛している」だ。
「達郎」はこの言葉を「薫」が所属するオーケストラの練習場まで訪れて叫ぶ。
(テクスト)
妹の「仲介」および「達郎」との「共謀」であり、既存のプロポーズの言葉による再生産が行われる。
両主体は、恋愛という関係性を持って「出発」となる。
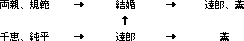

第三の単位(偵察・詐欺・悪行)
(ストーリー)
「薫」は動揺・感動しコンサートに来てもらうようにチケットを渡す。
喜ぶ「達郎」が知らぬうちに妹はセリフを教えたことを「薫」に話す。「薫」は怒りコンサートに来た「達郎」につめたく当たる。わけの分からないうちに喜びと悲しみを味わう「達郎」。
「達郎」は部下の「涼子」の相談を受けているところを「薫」に見られ冷たくされる。
「涼子」は「達郎」が立派に相談を果たしたことを「薫」に伝える。
見直され好期限になった「達郎」は「薫」にプロポーズするが、「薫」は突然、過去の婚約者に会わせて、と泣きすがる...............。
また「達郎」は偶然に「薫」の家にいるときに「薫の父」が尋ねてくるが、新聞の押し売りと間違えて罵倒する.........など。
(テクスト)
「達郎」の求愛が純真にも誠実にも繰り返される。「達郎」の再「侵害」である。
あるいは脇役の誰かによって「達郎」の英雄的行為が示唆されたりする。こうして「共謀」「詐欺」が実現を生む。
これに対し「薫」は感動や慰め、愛情を感じる。
しかし、その度に「達郎」の失敗や「薫」の誤解などで試みは失敗に終わる。両主体は常に「偵察者」として行為し、真実を知らぬままループに陥る。
「薫」の「禁止」によって「欠乏」という不幸を再生産する。
そして「仲介」によってフィードバックした「欠乏」が物語を振りだしに揺りもどす。
物語の脇役は一貫してフィードバック系を担うシステムとして機能している。
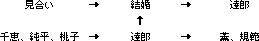

第四の単位(試練の提供・試練との対面)
(ストーリー)
「薫」はデート中に「達郎」の収人の話をするが、ボーナス全額を競馬の一点買いに投ぜられないような人(「薫」に言わせれば勇気のある人、かつ断りの理由だった)とは結婚できないという。
「達郎」は断る言い訳と知りなから82万円近くをつぎ込むのだった。
当然、競馬などやったことのない「達郎」は(これも「達郎」の性格を表わしていると言えるだろう。というのは競馬はこの時期の流行であったのだか、「達郎」はそのようなことには疎くかつ賭けといったような大胆なことや競馬が表彰する緻密な計算といった行為は出来ない性格である)当たらない。「達郎」のこの行為は「薫」の「お金、いっぱい使っちゃいましたね」という言葉と笑顔だけか報酬となった。
(テクスト)
「達郎」のプロポーズは「薫」にとって「試練との対面」であったが、「薫」も主体として「達郎」に「試練の提供」をする。
この要求は竹取物語的無理難題である。
「過去の婚約者に会わせて!といった要求、また嫌われないて別れたいいという「薫」の感情も一種の暗黙の「試練の提供」となっている。
試練の提供 → ← 試練との対面
第五の単位(戦い・狙い・勝利・魔法・初期欠之の解消)
(ストーリー)
「どんなにあなたか索敵であろうと好きにならない」と言われた「達郎」は、一時的に田舎(静岡)に帰った「薫」を追って行く。一瞬の気持ちの通じ合いが起こる。「薫」はそれをフィーリングと表現する。
デート中に迷子の子供を助け尊敬を得る。
「薫」が別に恋人を作り妊娠したという噂(桃子の「詐欺」による)によって誤解が起きる。「達郎」はそれを聞き、結婚していない「薫」の生活を心配し夜に工事現場でアルバイトをするのだった。
「薫」はそれを聞き工事現場に駆けつける。「薫」は「達郎」か好きだが、以前のように恋人に死なれる(愛するものを失う)ことを恐れていることを「達郎」に打ち明ける。すると「達郎」は猛然と走ってくる道路のトラックの前に飛び出す。トラックはぎりぎりで止まり「達郎」は「僕は死にません!あなたか好きだから!あなたを幸せにします!」と叫ぶのだ。
(テクスト)
物語中盤は「達郎」の求愛は成功へ向かい「勝利」が見え隠れする。
フィーリングに代表される小さな「魔法」が小出しにされる。
「狙い」の対象となったのは「薫」ではなくトラックと自己の生であった。これがマスコミで騒がれた有名なシーンであり、生を消費することで生まれる「魔法作用」である。
ここで一応二人は婚約し見合い以来続いていた「初期欠乏の解消」を行う。
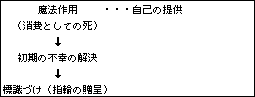
第六の単位(認められない存在・処罰・回帰・追跡・難題の解決・変身・結婚)
(ストーリー)と(テクスト)
物語後半では「達郎」の行為に対する敵対人物が出現する。それが「藤井」という人物である。彼こそが「認められない存在」だ。この敵対人物は「薫」の以前の婚約者とそっくりな人物で、「薫」とは偶然の出会いによって恋愛物語に引き込まれ「達郎」とは敵対者であるうえに仕事上の上司となって現れる。バルトのいう「あらゆることがさまざまに意味する」ように。
「薫」はたちまち「藤井」と恋に落ち、それが原因で「達郎」との確執か起きてくる。死者へと「回帰」する「薫」。
連郎は弟が祝福に渡した貯金で婚約指輪を購入するが、誤ってサイズの遵う指輪を無理やりに「薫」にはめようとする。これが恋の終わりの表象かのように「薫」は「藤井」に魅かれていく。消費の魔法作用によって求愛を表現し成功していた「達郎」への「処罰」である。
「藤井」と「薫」のキスシーンは死者へ「回帰」する「薫」であり、場面を目撃する「達郎」は自ら恋愛関係を放棄してゆくのだ。
上司との恋愛上の確執は「達郎」を退職へと導くことになる。
その後「達郎」は少年野球のチ一ムの補欠選手の逆転ホームランという場面に遭遇し、「薫」への愛をあきらめない決意をする。
達郎の「回帰」であり、「変身」のきっかけでもある。
「達郎」は「薫」が以前から求めていた夢と自信をつけるために、若いころの自分の夢を思いだし、司法試験を受け弁護士になることを志す。そしてそのことを「薫」に告げる。その時のセりフ「泣くんです。心がピーピー泣くんです(中略)・・もう一度、男としてあなたを取り返します」。「薫」はその努力を止めさせようとするが「達郎」は耳を貸さない。
「普連じゃないと思う。もう一度はだめなんだ。101回目はないんだ」という連郎のセリフは「薫」との恋愛か最後であることを示す。これが「迫跡・難題の解決・変身」である。この場合の難題は自分に課すもので対象が描かれていない、自己言及である。
その間、薫は「藤井」の離婚暦などの過去を知り、「ニセの主人公の摘発」を行っている。
「達郎」は司法拭験に合格発表の日に、合格したら「薫」が以前結婚式を挙げようとした教会に指輪を置いておくとの言葉を残し去る。発表当日、薫はコンサートの最中に突然立ち上がり教会に向かう。薫による「主人公の識別」である。
しかし教会にあったのは指輪のケースだけであった。「達郎」海で指輪を投げ捨てる。全てをあきらめて土方のアルバイトをする「達郎」のもとに「薫」はウェディングドレスを身にまとい駆けてくる。薫は道ばたに落ちているボルトを自ら自分の指にはめ、「達郎」を抱きしめる。薫の非現実的な意味での「魔法作用」である。
鳴り響くウェディング・ベルとともに物語は終幕を迎える。

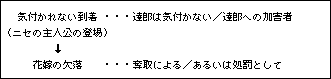
↓

↓

第二節 映像的諸要素の指標 ~モノと生活~
本節では、登場人物の「住」生活という観点から、テレビドラマで用いられる「モノ」に着目し、その「モノ」ふが指し示す意味について論じてみたい。
まずは住居である。
「達郎」は私鉄沿線郊外に住んでいる。観察からすると丸の内線沿線である。
家は和風の内装の4、5階たてのマンション。
部屋を風景描写から再構成すると図15のようになる。映像として全く移らない部分もあったので不正確な部分もあるが......
4畳半の「達郎」の部屋と6畳近くの「純平」の部屋に簡単な台所、8畳ほどの台所と、ベランダがある。
「純平」の趣味がアニメという設定のためか、大型のテレビが居間に置いてある。
またオーディオはコンポサイズのものが置いてあり(「達郎」は音楽に疎いことはミュージシャンである「薫」との会話で分かるから〉「純平」のモノの多さが伺われる。
「純平」と「達郎」が20才近く年の離れた兄弟であることをも暗に指し示している。このときの恋の強力兵器である電話は「達郎」宅も「薫」宅もコードレスフォンである。
途中ではピアノが購入され、部屋はさらに狭くなる。
図15 達郎の部屋
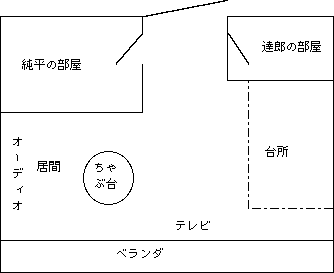
それに対して「薫」は都市住宅街に仕む。観察からすると高井戸から徒歩数分に位置する。
6、7階建ての洋風建築の高級マンションに住み、内装は豪華。
ニ人の兄弟はそれそぞれ約8畳の部屋をそれぞれ個室に使用し、間取りの広いダイニングキッチンにバス・トイレ付き。
部屋中には6か所にも生け花が、7か所に絵画が飾ってある。
大きく高級な家具がふんだんに配置されている。
不思議なことにテレビのない部屋である。
「薫」の部屋にはダブルベッドかあり、グローゼットには洋服がもう入りきらないほど掛けてある。不思議なことにテレビのない部屋である。
バスタブなどは体を延ばしてもまだ余りそうな大きいものだ。
部屋を風景描写から再構成すると図16のようになる。
図16 薫の部屋
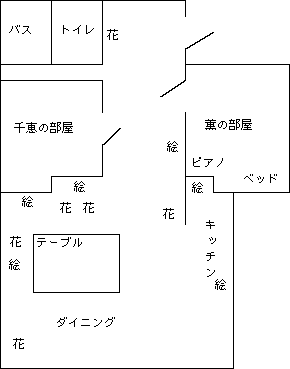
次に、登場人物の家庭における食生活を覗いてみよう。
「達郎」の家で食ベられたもの、飲まれたものをざっとあげてみると............「カツカレー、メザシ、味噌汁、ご飯、鯵の開き、コップでウイスキ‐の水割り、オレンジジュース、麦茶.............」。これをちゃぶ台の上で食べる。
「薫」の家では........「サラダ、スパゲティー、そうめん、エビフライ、ステーキ、アイスクり一ム・ワイン、ビール、紅茶、カクテル............」これをテープルで食べる。
対象的なのは、喉が乾いたときの飲み物で、必ず麦茶の「達郎」家とワインの「薫」家である。
また「ちゃぷ台」と「テ一プル」が二人の主体の対象を示す指標となっている。
外食場面はほとんどないが、異常に多い場面を見せるのが「酒」の場面だ。
この場面がない放映週はなかった。
「達郎」が一人で飲む時は赤堤灯の日本酒、見栄を張るときだけはバーに行く。
「純平」は赤堤灯の日本酒か、一人で水割りを飲む。
これに対し「薫」とその友人はもっぱらバーである。
「薫」はバーではマティーニしか飲まない。食事前も食中も食後も、嬉しいときも寂しいときもマティーニだけだ。
衣装をみてみよう。
「達郎」はサラリ一マンなのでスーツ姿か多い。でなければスラックスにポロシャッやチョッキ。家ではパンツとノースリ一プシャツだ。
純平は一貫してジーンズにティーシャツ。
これに対し「薫」は出る度に服が変わる。もしかすると同じものは一枚も重複してないかもしれない。女性出演者はみんなそうだ。
次に自動車である。
「達郎」は会社の軽のトラック(趣称軽トラ)を極たまに私用で使っている。
それに対し、「尚人」は赤のトヨタ・セリカ(一応スポーツカーである)。
藤井は白のトヨタ・マーク2である。大衆的でありなから高級車に位置する。観察によると2500c cの夕一ボモデルでこのクラス最強のモデルである。
以上の例は物語を構成する全ての要素ではないにしても、それ自体が物語の内容を表わす指標と成りうる重要な要素だ。
家屋の違いは「達郎」と「薫」の生活レベルの指標に、衣・食生活の違いは価値観の指標となっている。
つまり明らかに物語の中で特定の意味を与えられた「モノ」なのである。
住居はさておき、上記の例であげた「モノ」はドラマのスポンサーとなった企業の製品と合致していることには留意しておく必要がある。
テレビドラマで用いられる「モノ」は、「モノ」自体、そのものがそれとして持つ意味とは区別されている。
「軽トラ」も「セりカ」も「自動車」であるには変わらないが、指標として物語に組み込まれたときには「達郎と尚人の違い」という意味を持ってくる。
さらに意味は物語の構造に網目に位置付けられ、生産され、記号的な離脱となる。
付加価値的な意味合いがもともと強い「酒」のような嗜好品も、テレビドラマのなかではさらなる意味づけがなされている。「マティーニ」は「薫」の拒絶の強い意識を与えられるともに、その反転意識である「達郎」のしつこさという意味を与えられる。
一方、記号としての「ワイン」は、実在との関係を明確に示さしないドラマにおいては、視覚映像が実在としての「ワイン」を見せるんので、言語のように指標としてだけの機能に注目させない。映像に「あれ」はないのである。そのときは「ワイン」であり、そのことを否定する指標構造上の体系は見当たらないのである。
マスコミ研究において、積極的なメディアの「受け手」の存在、つまりリテラシーがあり理性的にメディア内容を解釈する主体としての「受け手」の存在についてしばしば言われている。しかし、「受け手」がいかようにも映像を解釈したとしても、そして、それが物語に与えられた意味と差異が生じていても、その解釈は「差異」そのものを明確化するにとどまる。実在としてのモノの意味を顕在化する過程なのである。それは、映像の意味生産および付与における、虚構と現実の二重の交錯、つまりシミュラークルが存在するからである。
このシミュラークルの分析によって、批判的な読者の冷静な(一般に冷めた言われる)態度こそが、既存の意味を生産する受け手像が見られるのである。それは、実はメディアによって生産された意味の再生産なのである。
第3節 感情的諸要素の指標
これまで「達郎」「薫」および登場人物、映像の構造的な役割を論じてきた。構造的役割としての分析を通じて、二人の行為が指標するものや、無意識のレベルで物語言説が表すことを読み取ることである。「101回目のプロポ-ズ」が表すものは、ダイナミックな社会の象徴、あるいはコミュニケ-ション過程のモデルと捉えることができよう。
主体の「薫」と「達郎」は物語においてそれぞれの心理的役割を持つことが分かる。心理的役割として「達郎」は「愛」の「送り手」であるのに対し、「薫」は「愛」の「受け手」だ。「達郎」と「薫」という二つの主体の行為を、愛を媒介にした相互行為とする視点で分析してみよう。
二人の「愛」に対する相互の意味付与の過程から、テレビドラマで意味づけられる「愛」の意味の差異と変化が見られであろう。これは「愛」という観念的構成体を、合意的な共通項としてコミュニケーションする主体の、ディスコミュニケーション状況の描写でもある。言語や視覚を媒介とするコミュニケーションのなかで、感情というものが、そこにいかに侵入し、コミュニケーションを規定していくのか。また、どのようなレベルでの合意をしていくのであろうか。
第1項 恋愛的相互作用の集合表象的側面
二人の行為者が指し示すものを、マクロにとらえていくと、「達郎」は「一般化された制度・社会、あるいはその根底観念でもある集合表象」として置き換えることが出来るであろう。「薫」はそこに存在した要素・個人である。つまり主体の行為は、他者と相互作用するコミュニケ-ションの象徴として考えられるのである。
物語中、一貫して変化しない「達郎」の結婚願望と結び付いた「薫」への「愛」は、社会的にある一つの制度のなかで共有されている意味、デュルケイム流に言えば「集合表象」的意味である。
結婚制度に「愛」という感情が基礎になるという一般的事実は、個人的な「愛」という感情を、一般的な「愛」へと拡大させる契機である。それが制度に組み込まれた「達郎」の「愛」である。
そして、制度的に組織的に成立していないような集合意識が、「達郎」に「薫」を無理目の女、似合わない女として扱わせるという構造にいなっている。「達郎」は制度のなかで恋愛の自由を追い求め、常に不可視の制度によって制限されている人物だ。
「薫」は恋愛を受けるという作用のなかで、その恋愛感情を変化させてゆく。「愛」という、相互作用の媒介である意味を、コミュニケーションのなかで変化させてゆく人物である。
第2項 集合表象的「愛」の記号的表出
第1項で、変化の媒介となる「愛」とは観念的構成物である。そこで、「愛」自体の意味性を行為のレベルに落として分析を行いたい。「愛」は表象され、行為として表現され、その意味を付与される言語的存在であるからだ。一方、「愛」はモノとして映像的にも表現される。
「薫」はどのような集合表象に対して作用したのであろうか。それは、表象である「達郎」自身の行為において見ることが出来よう。「達郎」における「愛」の定義は何だったのか、「達郎」が「愛」に求めたもの、その成就に求められたものを見ていこう。
「達郎」は「薫」の幸せと自己の幸せを同一化することで、「薫」の幸せを結婚と結び付けている。「薫」が「愛」にどのような形であれ「答える」ことは、「達郎」にとっては結婚そのものにあたる。「薫」の「幸せにしてください」という言葉は、「達郎」にとっては「プロポーズ」と響く。
第1に、 「達郎」の「愛」は「幸せ」である。
しかし「幸せ」は行為とはいえない。「幸せ」を満たすものがそれである。
「達郎」の「幸せ」は「結婚」である。
「結婚」はそれ自体が行為として制度化されていることは言うまでもない。
その意味で「薫」は単なる幸せの一要因でしかないのだが、「薫」と結婚することがその条件となることから、自分が「薫」を幸せにする必要がある。
「達郎」から見れば「薫」の幸せ=結婚=自分の幸せとなるからだ。
彼にとって結婚に必要なものが「愛」なのであり、制度がその集合意識を規定していく図式が見ることが出来る。結婚は「愛」という観念から自由になりつつも、すべきことになっているのだ。
第2に、「達郎」の「愛」は「手段」である。
つまり「薫」を得るために必要なもの......「手段」が愛なのだ。
彼にとっての方法は3つの内容を含む。
それは一つは「薫」を自分に引きつけること、一つは「薫」に対する献身的な態度、もう一つは「薫」の望む「達郎」に変身することである。
「薫」との仲が浅い段階では「達郎」は「薫」を「見栄」による演技で引きつけようとする。
コンサ-ト鑑賞の後のフランス料理は「達郎」が普段家で食べる「めざしと味噌汁」と対比されて見栄の象徴となる。
二人で合う場所は「ピアノのあるバ-」にほぼ限定される。「薫」の頼む「マティ-ニ」は、マティ-ニの名前を覚えられない「達郎」流に言えば「オリ-ブの串刺し入り焼酎」だった。
「達郎」は「薫」との偶然の出会いを期待して足しげくバ-に通う。
「薫」の聞くクラシックのCDを買うこと、競馬の一点買いにボ-ナスを注ぎ込むこと・・など、あらゆる見栄が愛の手段となる。そしてこの見栄は消費によって実現するのだ。
こうしてようやく第三の愛の定義が行動として表される。「消費」こそ「達郎」が定義する愛なのだ。
「達郎」と「薫」が婚約する決定的原因は「「薫」が愛するものを失うことを恐れるのに対した、「達郎」のトラック飛び込み事件」である。
自らを死という象徴的意味においての消費.......最も美しく、最も贅沢な、ボドリヤ-ルの言葉を借りれば「まさにこのことによって消費社会がその豊かさを具現するような」......におくことで、拡大再生産する愛の形を示したこの事件が、愛が消費であることを観念的に決定付ける。
婚約後の「愛」の手段を象徴するものが「婚約指輪」である。
この100万円する「指輪」はテレビドラマ後半の「愛」の動きに密接の関連する。
婚約=指輪という消費図式だけではない。
結婚に悩む「薫」に、焦った「達郎」がサイズの違う指輪を無理やりはめ込もうとする場面は、サイズの違う指輪に「愛」のすれ違いが象徴されている。
無理やりはめようとする「達郎」は、変化しない「愛」の定義をおしつける「「達郎」の規範性」を象徴する。
試験に落ちた「達郎」は指輪を海に投げ捨てて「愛」の放棄を証明する。
「薫」が「達郎」の愛を受け入れるとき.......このことが個人が社会において適合化していく象徴として物語を締めくくるのだが.......「薫」は自ら落ちているボルトを指にはめることによって、「愛」の意味としてモノの必要性、「愛」の定義としての「消費」を肯定するのだ(それまでは執拗に否定してきた)。
「私を貰ってください!」というセリフは、「達郎」の「愛」の定義である「消費」 を肯定するのである。
第3項 集合表象の受容の記号的表出
次に「薫」の「愛」の定義について分析しよう。
「達郎」と出会う以前の恋愛場面において、「薫」は自分なりの「愛」を自覚していることが示唆されている。それはおおむね、「愛」=「自分自身を幸せにしてくれるもの」という定義づけがなされている。
「達郎」とのコミュニケーションを、その定義された「愛」を媒介としていない、あるいは媒介する意味が定義された「愛」ではない、という意識のもとに、恋愛という関係性を否定する。「薫」の持つ「愛」の意味は、これまで経験的に会得してきた意味に制限されている。
達郎の行動を見て、コミュニケーションの媒介は「温情」へと変化する。「温情」は「愛」へと変化しないという確固とした自己認識を持つ。セリフでは「とにかくフィーリングがあわないの、もうあなたとは会えません」とある。この「フィーリング」とは、物語構造上では、「愛」と「温情」の中間的位置付けとなっている。この「フィーリング」、「なんとなく」といった以心伝心的意味合いである。
「フィーリング」を経て、「達郎」の献身を「愛」に意味に置き換える過程が存在する。「薫」にとっては「愛」は、自分自身を幸せにしてくれるものであり、「達郎」の献身がそれにあたったのである。
「為せば成る・夢を持って・女は夢を見たい」という「薫」の「変化」への要求が「達郎」の目標になるとき、「達郎」は職業を放り出して、弁護士になると決意する。
「薫」は「女は」といった社会的属性の価値方向性を示して、社会的価値を象徴する「達郎」に反抗・衝動の態度を示す。
その結果として「何もない、ただのおじさんですよ」と言ってしまう「達郎」に「愛」を抱く「薫」は、社会的適応過程を通じて「愛」を再定義するのだ。
第4項 互酬と非互酬の記号的表出
ここまでで「達郎」が象徴するものが、形態としての「制度(結婚を代表とする)」や、手段としての「消費」を表すことが分かった。しかし、これだけでは、社会が個人に対して適応を助長するという機能に限定した見方である。
「薫」の行動に象徴される、全体性に対する個人の要求の利己的な一面も十分に見ていく必要がある。「達郎」の愛の要求は、見方によっては、一方的な供与といえるような交換の非互酬による権力性の象徴のようにも見れる。視聴者にさえ同情を与えるような「薫」のことごとくの「達郎」への冷たい態度がまさにそれへの対抗であった。
ところで、「薫」の前に「藤井」という過去の婚約者とそっくりな人物が現われる。一度は「達郎」の「愛」を受け入れた「薫」は、過去の婚約者とそっくりな男性(純個人的欲望の対象)へ「愛」を媒介としたコミュニケーションを移していく。
この愛の移行は、形態としての「愛」と意味としての「愛」の同一視である。さらにいうなら「藤井」の存在は「薫」の二つの「愛」の意味の解釈の矛盾および葛藤なのだ。つまり、定義されたものが経験的であることと、積み重なる経験によって生成されるものとの葛藤である。
いったんは葛藤は過去への回帰によって解消される。
一方、「藤井」は存在そのものが虚構的であった。過去の離婚歴や離婚理由の嘘などがそれを象徴する。過去という非実在の、過度の美化による失望は、イミテーションとしての経験的現実認識へとたどり着く。
「薫」は、「愛」を解釈することに迷いを持つ。
これは自分自身を弱い人間であると認識することで解決しようとする。「薫」の妹である「千恵」は、「わたしは弱い人間です。そんな顔をして会いにいけばいい」と相談にのる。
もしも、最後に拾った指輪(ボルト)が「消費」とは無関係のものとして表象されており、それによって愛を価値的判断から引き離した、といった結論と解釈するなら、それは愛という観念が生成されるものではない、という考えに基づいた解釈であろう。
こうして恋愛は成就することとなるが、自己の意味解釈を一般的な形態を持つ方法に適応させつつ、満足することで可能となるのだ。
これにより「達郎」の意味する「愛」を肯定するのだ。幸せな結婚形態およびその表出である「消費」である。
つまり、そこには意味の生成があるのである。
第4節 構造から現実へ ~指標の比較研究への視座~
真実と虚偽、現実と幻想の「非差異」を受け入れることこそ、演劇が機能するための条件なのです
M・フ-コ- 「M・フ-コ-」より
これまで「101回目のプロポーズ」が提示した要素を、行為/登場人物/映像/感情にわけ、指標という観点から「101回目のプロポーズ」の意味生成過程を論じてきた。しかし、さらに論じるためには、この指標を導いた概念のコ-ド、つまり体系の存在が先になくてはならない。このコ-ドこそ現代社会を形作る集合表象であるのだ。
「101回目のプロポーズ」を「愛」の物語としてとらえると、その構造は、多くの物語が従っている「民話的」なものであるし、あるいは「神話の断章」として見ることができよう。
例えばユングの著作にある「美女と野獣」では、主体の具体的な行動を、無意識と意識に関することの束縛/解放・親切/残酷といった行動へと還元し、「美女」の行動が「精神と自然の結合」であると述べている。恋愛の形を借りない同じような構造を持った物語は多く見つけられるだろう。
レヴィ・ストロ-スは神話を次のように定義している。1つは、「太古の物語であり、事物の生成、現況、将来を記述し、それぞれがそれぞれを説明するときの秩序の連続性の確認」であるという。また2つには「一現象説明による多次元の状態の説明」と述べている。
「101回目のプロポ-ズ」を「神話の断章」と述べたのは上の定義に沿うような、それでいて現代的な事象を盛り込んだ物語であるからだ。「事物の生成」の記述とは、「101回目のプロポ-ズ」の場合、見合いから始まる社会と個人の関係の発見である。「現況」の記述とは、恋愛行動というコミュニケ-ション過程の表現である。「将来」の記述とは、恋愛成就という社会へのコミットメントの表現であり、人間の社会化という行動の社会心理学的側面を説明している。そしてこの恋愛物語は規範の権力性を「神話的」に説明しているといえよう。
神話は社会の近代化とともに解体し、爆発した。そしてその断片が気付かぬ所に散りばめられている。私たちはその断片の一つ一つを見つけ、掘り起こすことによって、かつて「神話」が説明しようとしたことを精神活動に取り込もうとする。その方法が音楽であり、文学であり、芸術であり・・・テレビドラマである。それらは規範の権力性を説明する「神話の断章」なのである。
制度化された意識、規範、道徳、思想などの暗黙の社会理論は、モノの記号化を可能にし、さらには「行為」の記号化も行う。行為は個人の精神的活動を基礎に置きながら、社会的な制限を受けつつ、相互に意味交換するような体系になる。行為はそれ自体の単純な結果だけに意味があるのではなく、上のようなコ-ドによって社会的にかつ個人的に何かを指し示す「指標」となるからである。
行為はモノと違い自然としてそこに存在せず、個人の精神活動を必要とするので個人的なコ-ドによる規定の度合いが物のそれより大きくなる。
「達郎」のあらゆる恋愛行動はある人にとっては純粋に男らしい行為として写るだろうし、ある人にとってはまったく考えられない行為に見えるだろう。しかしあらゆる人はこの物語が恋愛の物語であることは疑わないであろう。つまり「達郎」の行動は社会的行為として「現実」であり、個人的行為として「現実」と「虚構」を往復することになるのだ。
このような二つの観点から、ドラマの視聴者は、単にドラマが「物語」として「虚構」であるという認識以上に、つねに個人の精神的活動の一貫として、社会的な集合表象による規制になるような、「意味の検証」を行っているのだ。
この「検証行為」がテレビドラマ視聴のメカニズムである。テレビドラマの「現実」や「虚構」は、視聴者の社会的・個人的現実認識のあり方を表出せずには存在しないのだ。言語が体系を認識せずともそれに規定されざるをえない図式は、テレビドラマの記号的解釈=検証を行う視聴者が認識ぜずともそれによって規定されるものの存在を裏付けていよう。
さらにこの視聴者が認識をする・しないに関わらず規定されざるをえないものは、ドラマを見ること、つまりテレビのスイッチを入れた時に始めて出現する。テレビドラマ視聴という行為の記号的解釈はその方法によって、それまで認識されなかった現実を産む。ここで留意すべきなのは、それが存在しなっかったわけではないことである。
ドラマの視聴だけでなく、あらゆる映像メディアにおいて、このメカニズムによって視聴者は絶えず、繰り返し「虚構」と「現実」の検証を繰り返す。そして、「既存」の社会的構造の法則を生産し、拡大していく。こうしたメディアの機能こそ潜在的な権力として、社会的統合を実現するのである。
ドラマのような恋をしないことですら、メディアによって作り出された意味に支配されている。自由な記号体系の選択といった観点からは、そもそも自由で主体的な「受け手」という概念は成立し得ないのだ。メディアに支配された意味作用とは、強制的顕在化という「受け手」の積極性によるものなのである。
「101回目のプロポ-ズ」において何が「現実」で何が「虚構」なのかを明らかにすることは非常に困難なことになる。
そこで「愛=消費」という構造をもつことは説明した通りだが、そこおける物語内の行為や表象を、現実の行動と比較検討する。
そのために、消費者の意識を探ったいくつかの市場調査の結果を用いる。このデ-タが視聴者とは決して限らないところは、デ-タが「視聴に伴う生成された現実=シミュラ-クル」ではなく、「既存の現実」であることによって、構造と現実・実践を結ぶ判断を可能とするだろう。
そこで、指標について整理しておきたい。指標とは
第一に、一つの指示対象を持つものに与えられた記号の体系である。
第二に、物語構造において意味づけられた記号の体系である。
第三に、現実の社会生活で意味づけられた記号の体系である。
物語内の行為や表象を、現実の行動と比較検討するため、上記の3点の記号の体系の比較、指標の比較研究を行う。
そこで、「101回目のプロポ-ズ」のうち、重要な要素であり、物語構造のメルクマール的存在である、「指輪」「結婚観」を選択することにする。
上記の、「視聴者が、あらゆる指標を比較/認識しながら意味を生みだしてゆく行為」を「検証行為」と筆者は定義しておこう。第一の記号体系はドラマそのものであるから、すでに論じたことになる。第二と第三の記号体系を比較することにより、理念的な「検証行為」について考えてみたい。
第5節 結婚観の意味作用
「101回目のプロポ-ズ」では、全体としてのテ-マの中に「結婚」が重要な意味を持つ。「達郎」と「薫」は過程こそ違えども、恋愛行為の帰結として「結婚」を考えていることに違いはないからだ。
第1項 20代OLの持つ「結婚」観の現在
「101回目のプロポ-ズ」が放映された同時代を生きる若者は、「既存の現実」としていったいどのような「結婚観」を持っているのだろうか。
以下のデ-タは、「ポ-ラ文化研究所」が「20代OLの結婚観・職業観」についての意識調査を行ったものと、「総理府」が行った「女性に関する世論調査」「婦人に関する世論調査」「東京女性白書 '92」からの抜粋である。
「ポ-ラ文化研究所」の調査は1989年8月に「大都市圏の会社に勤める20代OL」を対象に行われたものである。結果は右図のようになっている。
「ポ-ラ文化研究所」 「20代OLの結婚観・職業観」
対象数は「292人」である。その内訳は20才(8%・22人)・21才(11%・31人)・22才(9%・25人)・23才(13%・38人)・24才(17%・48人)・25才(15%・41人)・26才(10%・29人)・27才(9%・25人)・28才(4%・11人)・29才(3%・8人)となっている。
「30代で結婚したいですか」との質問には88.6%もの人が「したい」と答えている。したくない人の理由については「年齢にこだわらない(27.3%)、夫に縛られたくない(15.2%)、相手なし(12.1%)、一人が楽(9.0%)」などとなっている。
「今、結婚したいですか」という質問では「はい」と答えた人が46.3%、「いいえ」の人が53.7%になっている。「いいえ」と答えた理由は「まだ若い(39.0%)、相手なし(12.3%)、独身のうちにしたいことがある(10.3%)、夫に縛られたくない(8.9%)」となっている。
「今一番欲しいもの(自由回答)」では「お金(14.5%)、時間(14.2%)、車(10.6%)、彼(2.5%)」
「今一番したいこと(自由回答)」では「旅行(39.0%)、遊び(6.0%)、結婚(3.5%)、のんびりしたい(2.8%)」
「男に養われることは嫌か」との答えには「いいえ」が82.8%となっている。 「結婚して、子供がいて仕事を続ける女性を素敵と感じるか」では、「はい」が77.8%、「いいえ」が22.2%となっている。
「映画に出てくるようなキャリアウーマンに憧れるか」では、「はい」が36.9%、「いいえ」が63.1%となっている。「入社するとき結婚までの腰掛けの意識はありましたか」では、「はい」が30.9%、「いいえ」が69.1%となっている。
「東京女性白書 '92」では、「結婚適齢期の有無」についての調査があるが62.7%の人が「ある」と答えている(マガジンハウス社のCLiQUE誌より抜粋)。
「国民生活白書」は、昭和54年の調査と「結婚観」の比較をしていて分かりやすい。
「女性は結婚したほうがいいのか」という質問で、昭和54年の調査では、男女ともに60-80%の人が「結婚したほうがよい」と答えているのに対し、平成2年の調査では、40-60%に減少している。
「女性が結婚する・しないの理由」を幾つか上げ選択させた項目がある。 内容は、「1.女の幸福は結婚にあるから」「2.精神的・経済的に安定するから」「3.人間である以上自然だから」「4.独り立ちできればしなくてよい」「5.自由を束縛するからしなくてよい」「6.個人の自由なのでどちらでもよい」である。
結果は昭和54年では、1と2の回答率が平成2年より1割高である。3は変化がなかった。6の選択肢は平成2年だけのものだが、圧倒的に他の選択肢より回答率が高い。
以上の資料を分析してみたい。
現在、女性が「結婚適齢期に30代という壁を考えていること」が分かる。
「今結婚したくない人」が53.7%と「結婚したい人」を上回っていることは、調査の対象が20前半のほうが若干多いことからも納得いくところだが、このことは25、26、27才と年齢を上げるにしたがって結婚願望が即時的・現実的になっていることを示していると言えるだろう。
20代OL達にとって「結婚」が意味することも、いくつかの質問の回答から推測できる。
「結婚」は生活上の明らかな変化として考えられている。しかしその変化の内容といえば、日常生活の変化が中心であり、視点はごく身近で、その場限りのものというか、近未来的なものでしかない。
自分の仕事は「腰掛け」とは考えていないまでも、仕事に夢や情熱を賭けるというほどのこともなく、また結婚と仕事の問題は明確になっていない。
つまり、「遊ぶ」ことや「自由」であることといった、曖昧な意味で、現在との変化を望まない一方、明確な自立意識などは持たないという、ある意味で矛盾を持つ思考である。その場限りの「遊び」や「自由」を束縛するものとしての「結婚観」は否定できない。といって経済的生活の場としても結婚を否定したりはしない。 こ
のような自己中心的な思考から、モラトリアム人間の思考が思い出される。モラトリアム(執行猶予期間)を20代と設定して、その場に居続けたいというような思考。手身近で不確かな人生設計。まるで生活のための結婚と、自分の目標を区別して、かつ結局は「結婚」しなくてはならない事実を、ク-ルに受け止めているようなふりをする。
その矛盾を埋める一時的な解決方法は、旅行に代表される「消費」である。欲しいものが「お金と時間」で、したいことが「旅行」。「旅行」はその指標として「日常=束縛からの脱出(一時的な)」を表すかのようでもある。
第2項 テレビドラマ内の「結婚」観
「101回目のプロポーズ」の「薫」にとって「結婚」とはどのようなものであったのか。薫の言説から「結婚観」を引き出すことが出来る。
薫にとって「結婚」が「恋愛」と同義として捉えられたのは、亡き「真壁」との関係においてであり、真壁の死が恋愛と「結婚」の関係を断絶させている。
次第に「(達郎と)いっしょにいると楽しいしほっとする」ということを「結婚」の必要条件と考え始める。
薫にとって「音楽という仕事」は「結婚」との対比上には存在してこない。暮らしや生活は「結婚」に影響を与えるとされていない。ただ幸せの永続(愛の成就)の象徴としてのみ「結婚」を定義している。この場合の幸せとは自他の幸せである。
象徴的意味において、「薫」の愛への欲求は、自分の愛の力の外化が、真壁の死によって、意図的・非意図的に搾取されたのである。いわば薫のヒューマニズム的な疎外をうめるものとしての「結婚」や、全体的人間の完成......失われた薫の愛の力を、埋めるべきものを探究する過程......への「結婚」に、意図的とも思えるような「消費」の概念の欠如が見て取れるのだ。この欠如が否定的とさえとれるほどに、物語は「虚構性」を強調する。あるいは「愛の感動」の影に隠されることになる。
第3項 視聴者と検証行為
「101回目のプロポーズ」の最も高い個人視聴率を持ったのは20-34才までの女性だった。彼女らが上のような、新たな「結婚」の意味に触れたとき、即ち「検証」を行う。
結婚=束縛、結婚=先の話、と考える視聴者が「薫の」「結婚」を見たとき,考えることは(当然、各自違うだろうが)どのようなことだろうか。
世論調査によれば、「結婚」は「個人の自由」と考えられている。「薫」が誰と「結婚」しようが、それは「自由」として判断される。
ところが「結婚」への考えと、「自分が結婚すること」はまるで違う。
「自由」でも「自分は30代までに結婚したい」のだ。そして「結婚への不安」は「消費」によって解決したいのだ。
「薫」の結婚はその文脈ではどうであろう。音楽つまり仕事はどうするのか、あれだけ広い家は手放すのか、本当に暮らしていけるのか........。あるいは「愛」があれば自分とは関係ない自由と思うかもしれない。
この点で、ドラマ内の「結婚」の意味には、社会における20代OL達の「結婚」観との間に、大きな「差異」がある。
この「差異」がなにであるかは各自の視聴者の違いによる。しかし、20代OL達が「101回目のプロポーズ」を「差異のある物語」として判断した瞬間、彼女たちの「結婚観=意味の体系」が顕在化されるのだ。
つまりより大きな「意味の体系」の中で、二つの体系(ドラマ内とOLの持つ意味)がお互いの「差異」によって、より大きな意味を生み出し、顕在化するということだ。それは「メディアの意味作用の体系」である。
この「認識=顕在化した意味」は、「101回目のプロポ-ズ」に触れることで起きたものであり、彼女の既存「結婚」観を浮かび上がらせる。こうして思い浮かんだ既存の「結婚」観が、彼女たちを「制度としての結婚」に向かって急ぎ足にさせるのだ。
「検証」の方法や「結果」(簡単に言えば「101回目のプロポーズ」をどう思うか)は、いかにも主体的で主意的なようでありながら、「101回目のプロポ-ズ」が提示したコ-ドの支配を受けているのである。
第4項 結婚行動の現在
結婚行動の現在を、厚生省が行っている「人口動態統計」と総務庁が行っている「国勢調査」を使って示してみよう。
「人口動態統計」では30代の婚姻数が85年から90年にかけて8万7000人から10万2000人と2万人近く増加しており、20-24才の婚姻数は逆に5万人近く減少している。
「年齢別人口(国勢調査)」を見ると、20代人口は1687万1000人、30代人口は1679万2000人と、約8万人ほど20代の人口が多い。
ここから、婚姻年齢が上昇していることが分かる。
「年齢階級別有配偶率(国勢調査)」をみてみる。
20-24才の男性(6.2%)、女性(13.5%)。
25-29才の男性(33.9%)、女性(57.5%)。
30-34才の男性(65.2%)、女性(82.7%)。
35-398才の男性(78.1%)、女性(87.3%)。
「平均婚姻年齢(人口動態統計)平成元年版」によると、東京都の男性(29.3才)、全国の男性(28.5才)、東京都の女性(26.7才)、全国の女性(25.8才)である。
以上の統計からは、女性が20代後半から30代始めにかけて、婚姻数や、結婚している人の数が、実際に増加していることが分かる。
「人気・流行=共感」でないことは明らかだが、「人気・流行=意味生成・強化」であることは言えそうである。
「101回目のプロポ-ズ」の最も多かった視聴者層は20-24才の女性だった。彼女達の「モラトリアム結婚観」は、視聴・検証行為によって、確実に強化され、行動化されているのである。
第6節 指輪の意味作用
「101回目のプロポーズ」後半において、「婚約指輪」が「愛」の象徴になっていたことはすでに指摘した。映像としては明確な「モノ」であって、指標する意味も多く持つ「指輪=宝飾品」について、視聴を通じた意味作用を考えてみたい。
第1項 宝飾品に関する消費者意識
「指輪」を代表とする宝飾品は、現代社会に生きる人々にとって、どのようなものなのか。
次の資料は「プラチナ・ギルド・インターナショナル」が「宝飾品ギフト」にかんする意識調査を行ったときのものと、「郵便貯金振興会」が「お金及び金銭感覚に関するアンケ-ト」を行ったときのものである。
「プラチナ・ギルド・インターナショナル」の調査は、「東京30Km圏」で「19-69才」の男女を対象に「1010人(女493/男517)に行われた。(91年5月)
宝飾品の保有状況は、女性全体で98.2%が平均8.7個を所有している。さらに18-29才の女性は99.2%が平均9.6個の宝飾品を所有し、女性全体の平均を上回っている。つまり「宝飾品」が女性の非常に身近で、特に若い女性においてその傾向が高いということである。
女性の宝飾品の年間受理率は全体で35.1%である。いっぽう18-29才独身の女性は67.0%と、3人に2人は何らかの宝飾品を誰かかれかから受理している。30才代になると数がぐっと減っているのがわかる。
男性の宝飾品の年間贈与率は全体で21.9%、18-29才で25.0%、30代で24.8%である。
女性がプレゼントされる機会の増大とともに、男性がプレゼントする機会も多くなっているようだ。
「愛する人の贈りたいもの(複数回答)」の調査では「宝飾品」がトップである。以下に「花束」「食事」と続く。
18-29才の女性(贈られたい意向)は宝飾品が84.4%、花束が63.1%。食事が46.7%だ。
一方、男性(贈りたい意向)は宝飾品が60.3%。花束が49.6%、食事が37.4%となっており、総じて男性の贈与意向のほうが、女性の受理希望よりも低い。
20代独身女性は91.0%もの人が宝飾品を望んでいる。一方20-30代独身男性は宝飾品の贈与意向が36.8%と非常に低い。
宝飾品の受理意向のある20代独身女性はその予算を、1-2万円が10.9%、3万円が42.2%、5万円が18.8%。10万円が9.4%と考えている。
一方、贈与意向のある20代独身の男性は1~2万円が14.3%、3万円が25.3%、5万円が28.6%、10万円が14.3%と考えている。
つまり女性は男性が考えるほど高い宝飾品を望んではいないのである。
「郵便貯金振興会」の調査は、銀座と渋谷において20-49才男女20人づつ100人を対象に行ったものである(92年1月)。
「あなたにとって大金とは」との質問に、1000万円が34.0%,100万円が26.0%、1億円が21.0%となっている。それ以上という人も3.0%いる。この時期はバブル経済全盛の時代であったことも付加しておきたい。
男女別にみると、男性は1000万円が34.0%、それに続いて1億円が30.0%、1000万円が20.0%だが、女性は10000万円が34.0%、1000万円が32.0%と同程度に存在し、1億円が18.0%、50万円以下が12.0%となっている。男女間で金銭感覚は類似しているものの、総じて男性のほうが大金の額が大きい。
「もし大金が入ったら何に使うか」という質問では「海外旅行、41.0%」「不動産購入、36.0%」「衣料、23.0%」「レジャー、21.0%」と続く。
男女別では「海外旅行」が女性では54.0%とトップなのに対し、男性は28.0%と少ない。
一方「不動産購入」では男性が46.0%とトップなにに対して、女性は26.0%とすくない。
宝飾品と答えた人は全体では6.0%、男女別では男が4.0%、女が8.0%だ。
大金の額の男女差が、使用額の違いになり、女性を消費財指向に向けているといえそうだ。
「友人・知人と食事を楽しみたい時の費用の上限」に関する質問では、男性で「5千円超2万円以内」が57.0%でトップなのに対し、女性は「3千円超1万円以内」が76.0%となっている。宝飾品ともども男性のほうが高めである。
「恋人や配偶者への誕生日のプレゼントの費用の上限」に関する質問では、男性で「5万円以内」が34.0%、「3万円以内」が32.0%と続くのに対し、女性は「3万円以内」が44.0%、「1万円以内」が32.0%となっており、「プラチナギルド・インターナショナル」の調査とも合致しているようである。
以上の結果を分析すると、女性にとって宝飾品は非常に魅力的なものであり、また一般的にもなっている。かつそれは愛の証としても魅力的になっている。
女性は男性が上げたい気持ちよりも多く貰いたい気持ちがある。
しかし女性は決して高い宝飾品を望んでいない(安いとは言えない)。
どちらかと言えば、値段は男性の「愛」の気持ちを表す方法としての意識の表出である。
女性は宝飾品を気持ちとして貰いたいが、値段として気持ちが現れることは望まない。
男性は贈与意向が低いが、気持ちとして上げたくない訳ではない。
どうせ上げるなら高いほうがといったところだろうか。
男性は、総じて支出額が高めになる。このことは支出の対象や目的の違いによって生じたと考えられる。
このように見てくると、宝飾品は、経済や文化といった体系によってその意味を決定されているようである。金・プラチナといったような自然的な特性だけでない、「愛」の証、「消費」の対象といった意味である。
第2項 ドラマ内の指輪の意味
「101回目のプロポーズ」で「指輪」はどのような意味をもったのだろうか。
達郎の購入した指輪は100万円近い値段のものだった。
なぜ買ったのか。それは婚約=指輪として考えていたからである。
婚約という「愛」の契約形態を、指輪という「消費」
財で交換しようとしたのである。
信用は利益を意味として内包するという現代社会の法則を愛にあてはめたのだ。
達郎は愛のためには指輪を贈呈しなくてはならなかったのだ。
さらに物語では「愛」の終わりを悟った達郎は指輪を海に投げ捨てる。つまり達郎にとって「愛=消費」の一つが「指輪」の意味だった。
薫は達郎の愛を受入れたものの、即形式的な行動にでる達郎を疑う。指輪は薫にとって拘束の恐怖を誘うもので、けっして「愛」の証などではない。
一方、全てを失った達郎の「愛」を受け入れる薫は、落ちているボルトを指にはめて「愛」の証とする。薫にとって「指輪」とは「指輪=金・銀」では全くなく、ただ「指輪=愛(無償の)」であった。
第3項 視聴者と検証行為
視聴者は、テレビドラマで提示された多彩な意味を持つ「指輪」に触れ、検証行為を行う。
「101回目のプロポーズ」は、従来のトレンディードラマに比べ「普通のおじさん(達郎)」が出演していて、親近感があるという風潮だった。しかし実際はどうであろう。
「愛」の証として、気持ちだけでも入っている宝飾品が欲しい女性層からみると、達郎の行動は奇異に写るだろう。
達郎は形式(指輪が表象する契約)より「愛」を重んじるべきだ、あるいは食事でもして愛を語ったほうがいい、という考えが浮かぶかもしれない。
デ-タで示した現実をみれば、どんなささいなことでも、形式だけでないプレゼント(安くても愛があるという意味、あるいはプレゼントする気持ち)が欲しい女性の心が現れている。
贈与意向の低い男性から見れば達郎の行動はまた奇異に写るだろう。なぜ、そんなにまでしてプレゼントを希望するのか?。
愛しているとはいえ指輪がそれを表さないという考えが浮かべば、それはますます男性の贈与意向を下げるだろう。
「愛」の証としての宝飾品の費用上限の高い男性からみれば薫の行動は全く奇異に写るだろう。達郎は100万円もする指輪を上げたのに、喜ばないなんて変だ!。
あんな高い指輪をあげたのだから「薫」は喜ぶべきだ、と考えれば男性は高い宝飾品を誰かを喜ばすのに購入するだろう。
デ-タで示した現実をみれば、宝飾品よりも「愛」をといった男性の意識が表出されている。実は、男性が贈与意向が低いのは、規範に忠実なだけなのである。
「かもしれない分析」であるが、これは「達郎」の行動から導かれた、女性からの「男性への行動規範」に類するものであろう。しかし、この生成された規範こそが現実を、そして行為を規定していくことになるのである。
第4項 達郎と薫の指標比較から見た消費行動
「指輪」が直接「モノ」として消費の対象になる。
「達郎」や「薫」を「消費者」として見た場合、どのような位置付けにあてはまっていたのか考えてみたい。
データとして1992年度の経済企画庁が行った「国民生活白書」を利用してみよう。
「達郎」の働く会社は「中堅どころの建設会社」という設定である。
ボーナスが「82万円(競馬の時の言説)」であるから、推定月給は「30万程度」と考えられる。
とすると推定年収は約442万円ということになる。
「薫」は「オ-ケストラ楽団員」であるが、収入等は全く不明だ。
「国民生活白書」によると「30人以上の規模の事業所で支払われた賃金」の平均は、月平均(定期給与+特別給与(ボ-ナス等))で37万2390円、年収にすると446万8680円となっている。
「達郎」は職業分類では「建設業」、職種分類では「一般事務係長」にあたる。
「薫」は「自由業」あるいは「分類不能の職業」にあたる。
1992年は全職業帯で前年比4.6%の給与の伸びを見せた年だった。
一方、消費者物価の伸びが9年ぶりに3.3%と、3%の大台を越える伸びを見せ、全体としては、生活が変化したとは言いがたい。
達郎が分類される「建設業」は「特別給与」が前年比18%増しと、最も伸び率が高く、成長を見せた分野であった。
この点、達郎は42才という年齢を考えると、決して裕福な状況とは言えない。
ともすれば物価の上昇と相まって、苦しい生活を送ることになる。
消費 消費支出の伸びを、職業別・年齢別にみよう。
「自由業」では7%、「民間企業」では9%の伸びである。
30才代では7%、40才代では11%の伸びである。
年令の要因は、家族構成や収入と関わりがある。ここから「達郎」と「薫」の家族構成分類をしておこう。
「達郎」は20才下の弟と2人暮らし。両親はいない。
「薫」は10才下の妹と2人暮らし。両親からの仕送りを貰っている。
2人とも統計上は「二人以上の普通世帯」である。
注目すべきなのは2人の「家」である。
達郎の家は「持ち家」である。さらに達郎はロ-ンが残っている(何年分かは不明)。
薫の家は賃貸だ。
「土地・家屋の所有形態別、消費支出の伸び」は、持ち家/社宅/民間借稼世帯の順で伸び率が高い。そして住宅ロ-ンの有無は伸び率と相関がないという。
「薫」は自分で家賃を払っていないので、消費支出に対する住宅費を考えなくても良い。
しかし、現実の「薫」の年代の人々の、消費支出の伸びにおける住宅費が占める割合いは少なくない。
さらに注目すべきなのは、1992年の年代別消費では50代の消費が特徴的なことだ。 50才代の消費支出の内訳は、突出して「教育費」が高い。さらに「その他」の内訳で、「(学費等を目的に、大都市圏に出た長期不在者を持つ世帯の)仕送り金」が高いのも50才代だ。平均「仕送り金」額は14万9000円(月)である。
大学生程度の子供を持つ世帯の消費支出に、大きな伸びが見られたといえる。こうして年代別消費支出の伸びは50才代がトップになっている。
「達郎」の弟「純平」も、「薫」の妹「千恵」も、同じ大学(私立)の大学生だ。
以上のデ-タを分析すると以下のようなことが分かる。
「達郎」は収入において平均より少ない上に、養う弟がいる。ところが「達郎」の年代で家を持つ家族はロ-ンの有無に関わらず消費支出が伸びていた。ロ-ン持ちで弟を大学に通わせている「達郎」の支出はかさむいっぽうであろう。
「薫」は、一般の30才代に比べ住宅費がないことから、それ以外の消費支出の割合が高くなるはずだ。さらに「千恵」の学費は両親が出しているのだから、負担はない。収入の謎に上乗せする、支出のなさ。
このような状況において、「達郎」は「薫」のために「愛=消費」をしていることになる。
例えば、「達郎」が一ヵ月間、「薫」に偶然逢おうと毎日通っていた「ピアノバ-」を考えてみよう。「達郎」は必ず「マティ-ニ」を飲んだ。カクテルの相場は店によってまちまちであるが、「マティ-ニ」はバ-において決して安くはない。生演奏つきのバ-ならチャ-ジもあろう。私がフィールドワークとして、新宿の「ピアノバ-・ダンス」でマティ-ニを一杯飲んで出たところ、請求書には1200円+1500(チャ-ジ)で2700円であった。私が他店でもフィールドワークを続けたところ、統計的には明らかでないが、この値段は高くもなく、安くもないということが分かった。「達郎」がバーに30日間、毎日通った場合を、この例で計上するなら、約8万円ほどの支出になる。
苦しい「達郎」が、「薫」を愛すると、さらに支出がかさむが、「薫」は変わらない。不均衡が募るばかりである。100万円の指輪もその一つであった。ここで「ああ、かわいそう」などという主観的な感情は出すまい。むしろそれが現実とどうけ検証されるかである。
100万円といえば、アンケ-トでみたように男性にとって2割もが大金として上げているだけの額である。バブル崩壊で大金が入っても株の購入は考えないような、消費より貯蓄指向が見られる男性にとって、達郎の行動はまさにバブルな「消費」として写るだろう。
100万円の指輪を捨てないことを考えるだろう男性を証明するように、平成景気の落ち込みが見れるのは...........実は「メディアの意味作用の体系」であったのであろうか。これは仮説として留めておこう。
「愛」は値段で計れないかのようにボルトを指にはめる「薫」であるが、現実には女性も3万円近い値段を受理宝飾品の妥当な値段と考えているのである。いくら宝飾品が値段ではないといってもボルトでは済まされない。3万円は消費されなくてはならないのだ。
第7節 まとめ
「101回目のプロポ-ズ」の構造分析を通じて、「指輪」や「結婚」だけではない、モノやあらゆる行為、物語の構造がすべて「検証」の断罪に上る。
そして、検証の基準としての社会的意識・規範を強化していく。
それはメディア内の映像の、身辺性や即自己性による、単純な現実化・行動化などではない。
メディアと人間のコミュニケ-ションの過程においての作用なのだ。
こうして顕在化された規範の類が、意識・行為の基礎となって、社会的な行動やイデオロギ-を強制する。
これこそ資本主義社会におけるメディアの機能と言えるだろう。
「消費」という規範を生産し、消費させ、拡大再生産することによる、手に負えない統一こそ「メディアの権力性」といえよう。
第6章 「東京ラブストーリー」の言説分析
「東京ラブストーリー」は、1991年1月7日から3月18日まで1回放送ごと54分を11回放映されている。1991年2月といえば、世界では湾岸戦争が勃発していた時期でもある。情報統制の意義など、メディアの在り方にも注目のいった時期でもあった。そのような時期に30%近い視聴率をコンスタントに稼ぎだしていた「東京ラブストーリー」。メディアという「場」がいかなるものかを深く考えさせるものであった。
メディアとはそもそも十字路を意味する「場」の概念である。しかし、この「場」とは、「101回目のプロポーズ」の分析で「愛」に関して何度も言及したように、概念的な構成物である。この「場」という概念は実在と存在の間を交錯し、時には認知的枠組みとなり、時にはテレビジョン・セットという機械の外枠・窓枠ともなる。「東京ラブストーリー」の内容に関してはどうだろうか。「東京ラブストーリー」は枠組みとしての「場」がいかように提示されているのか。「場」の分析を行ってみよう。
第1節 登場人物の行為分析(簡易版)
「東京ラブストーリー」も「101回目のプロポ-ズ」と同様主体を1人にした人物構成ではない。「東京ラブストーリー」の場合は4人の描写がほぼ平均的になされることで物語が成り立っている。ここでは、「場」の分析のために、若干簡易化した行為分析を行っておきたい。「」付きでの行為のモデルは、「東京ラブストーリー」の主題歌「ラブストーリーは突然に」と対応するように示してある。
第1の単位:出会い
場面は「カンチ(永尾完治)」が空港にて「リカ」(赤名「リカ」)」と出会うところから始まる。
「カンチ」は田舎の愛媛から上京して就職(中途)のためにやってくる。
「リカ」はその会社(スポーツ用品商社)の社員である。
「カンチ」は高校時代の親友である「三上(三上健一)」と連絡をとる。
話題は二人の高校時代の憧れであった「関口(関口さとみ)」であった。
「関口」は「三上」と同様に高校卒業時に上京していたが二人は数回あった程度だった。
「カンチ」が東京に来たのは卒業後5年後という設定だ。
「カンチ」以外の登場人物は既に東京にいて、「カンチ」の行動が4人を結び付けている。導入部に不在な人物「カンチ」は主体の審級の上位に位置するといえるだろう。
その後、高校の在京同窓会で3人は再会する。
「リカ」と「三上」はその同窓会の日に偶然の出会いをし4人が結び付けられる。
第2の単位:伝達・成就
恋愛関係の提示がそれぞれ対等に併置されていることから恋愛関係の順序を追って見ていきたい。
1. 「カンチ」の場合と「リカ」の場合
「カンチ」は「リカ」に高校から憧れている女性がいることを話す。それが「関口」である。「リカ」は「カンチ」の恋に協力するが、一方では恋人であるように振る舞う。「関口」の電話番号を知った「カンチ」は「関口」に接近するが、「三上」と「関口」のキスシーンを見てしまう。失望した「カンチ」は「リカ」に慰められまた告白される。「カンチ」は一端「関口」に告白するが自ら断ってしまう。そしていつのまにか「カンチ」は「リカ」に恋愛感情を抱いてゆく。
2. 「三上」と「関口」の場合
「三上」は高校の同窓会で久しぶりに「関口」と会う。「関口」はナンパな「三上」を見て怒る。「三上」も「関口」の潔癖を非難する。「三上」は「関口」に嫌われていると思っていて、「関口」は「三上」が自分の事を好きだとは思っていない。気持ちの通じたところで「三上」は「関口」にキスする。「関口」は「三上」を好きになることを恐れるが、「三上」が真面目になることをすることで愛し付き合えるようになる。
3. 4人の場合
4人はお互いの付き合いを認め、4人での「食事や温泉旅行」などで絆を深めてゆく。
第3の単位:事件その1
1. 「三上」と「関口」の場合
「三上」は「関口」と付き合いつつも、大学でクラスメートの「長崎」と接近する。「伝達」状態で二人は止まっている。「関口」は用事で「三上」の大学に行くが、長崎と「三上」の仲良くする姿を見て不安になる。また過去の女性が「三上」の家を訪ねてくる。長崎は「三上」を「待つこと」で感情を維持するが、「三上」と長崎が抱き合うのを見て、別れを決心する。
2. 「カンチ」と「リカ」の場合
「リカ」は、「カンチ」が「関口」のことを「好き」であることを知っている。「リカ」は「カンチ」が「大好き」であることから、「関口」と「カンチ」が会うのを拒まない。その結果、「カンチ」は「関口」に近づいていってしまう。さらに「リカ」のロサンジェルス支社転勤が内定する。「遅刻」なり「誤解」なりから別れをむかえる。
第4の単位:事件その2
1.「カンチ」と「リカ」の場合
「リカ」がロスアンジェルス支社転勤を放り出して失踪する。「カンチ」は「リカ」を探しに、以前「連れてゆく」と約束した愛媛を探す。「リカ」と「カンチ」はそこで出会うが、「リカ」は一人で帰ってしまう。そのまま「リカ」はロスアンジェルスへ行ってしまう。
2.「三上」と長崎の場合
長崎は婚約者がいるが、「三上」のことが好きだった。長崎は一旦結婚するが、新婚旅行を放り出して帰ってきてしまう。
第5の単位:不安/歓喜
3年後、「関口」と「カンチ」は結婚する。「三上」と長崎も結婚する。「カンチ」が偶然街で「リカ」と会うが、「リカ」は一人だった。「カンチ」は「リカ」に連絡先を聞くが、「リカ」は教えないで別れた。
第2節 言語/恋愛/記号
以上のように、「東京ラブスト-リ-」は主に4人、脇役を加えて6人の人物の行為描写から、彼らの行為の媒介であった「恋愛」という概念を導き出す物語であったと言える。
「恋愛」とは自然的な裏付けを持って存在する「モノ」ではない。それは内容や特性であって形態を持たない。であるから「東京ラブストーリー」から見られるものは「恋愛」ではなく、「恋愛という意味を作りだしたもの」である。つまり「恋愛」という記号の言表としての物語なのだ。
言い換えれば、「東京ラブストーリー」という文脈に位置づけられることによって確定された、「恋愛」という記号の生成、あるいは変換過程としての物語なのである。
ソシュ-ルは言語の構造について研究したのだが、その簡単な内容を以下の示す。
ランガ-ジュ(構造化できること、普遍的で生得的なこと)とラング(顕在化した構造、規則の総体)とパロ-ル(個々の言表)の関係は、モノをコト化する主体の活動を通じて誕生する関係である。このような関係を媒介するのが、言語という記号である。この記号は「意味するもの(シニフィアン」と「意味されるもの(シニフィエ)」を結びつける。意味は、ある体系から差異によってシニフィエを摘出すること「言表行為」によって、生まれる。
「東京ラブストーリー」は恋愛の言表行為である。であるなら、ラングを「愛」として、パロ-ルを「恋」として(これは暫定的に)、「ランガージュ」のある人間が「ラングとしての愛」を「パロ-ルとしての恋」に顕在化させていく言語的・記号的な考えができるのではないだろうか。
そこで、「東京ラブストーリー」の分析では、「101回目のプロポ-ズ」の分析とは若干視点を変えることになる。というのも構造的には非常に単純で、心理描写中心のスト-リ-であるから、「モノ」や「行為」から指標を選ぶよりも「東京ラブストーリー」の主人公達の「言説=セリフ」から登場人物の「無意識」が指標するものを分析するほうが有効であると考えれられるからだ。
第3節 主体の無意識の指標分析 ~恋愛言表の分析~
まず物語において重要な指標となる「移住」の要素から考えておきたい。
登場人物には必ず自分の育った場所が示される。
この「場」が、社会的人間の行為の基準となるものであるかのように、登場人物の行為の在り方をあらわす象徴となっている。
4人のうち、最後に愛媛から東京にやって来た「カンチ」は、5年前の思い出を忘れられない「愛媛」そのものである。
「リカ」は小さい頃から外国暮らしが続き(特に「おおぞら」が描写される)現在は東京に住み働いている。自由奔放な性格で、愛しても愛されることを恐れる「リカ」はユ-トピアとしての象徴「おおぞら」であり、またけっして定住のできない「場」を持たない人物である。
「三上」は高校卒業後すぐ東京にきて大学へ通う。「カンチ」と同じく、「関口」に好意を持ちながら、不特定多数の女性と交流を持つ「三上」はその多様さや派手な行動からも「東京」である。その後、「三上」は「関口」との別れから医者を目指し「愛媛でない東京の外側」へと変身していく。
「関口」は高校卒業後に東京に来て保母さんになる。「三上」と「カンチ」に迷う「関口」はあらゆる場に適応できる人物であり、付き合う人によって「場」が変わる。
「長崎」は東京を田舎にする人物の代表として「東京」であり、「羽賀」は東京で働き生活する人物として「東京」だ。
次に中心となる4人の恋愛言表の分析を行いたい。
第1項 「カンチ」の恋愛言表の分析
「カンチ」にとっての「愛」とは「愛媛」に象徴されるものであり、それが行為と感情になって「恋」として現れる。
「カンチ」は「愛媛から東京に移って来て高校時代のあこがれの女性に会う」というテクストの中で、また「憧れの女性を前に自由奔放な行動をする「リカ」に戸惑う」というテクストの中でのみ「愛」を「恋」として表現する。
「カンチ」は物語中において2つの「恋」をする。
「関口」に対してと「リカ」に対しての二つだ。
「カンチ」の「恋」する「関口」とは、愛媛の思い出の中の「関口」である。
思い出の中では、常に「「三上」・「関口」・「カンチ」」が同時に登場するそれは自己と他との区別なき世界における、全体としての思い出である。
つまり「カンチ」の「恋」する「関口」は、自己の中の他者なのである。
それに対して、「カンチ」が行為する現在(東京に居る「カンチ」)には、「関口」や「三上」が東京にいて、それぞれの生活や感情を持っている。
東京においては自己と他が分離していることを明確に意識させられる。
空白の5年間や環境の違い、感情の食い違いがそれを表している。
ここから、「カンチ」にとって東京での現実がどうあろうと、「関口」を「恋する」感情に代わりはないことが分かる。
「関口」が「三上」と付き合っている間も、自分自身が「リカ」と付き合っている間も、「カンチ」は「関口」に「恋」している感情を持てるのだ。
なぜなら、それは「関口」に「恋」することではなく、自分自身(あるいは自己の中の「関口」)に「恋」することになっているからだ。
「カンチ」が「愛」を「行為」として表現しない(「関口」が好きでも何もしない)のは、「カンチ」の「愛」に対する理想=愛の意味が、「他者を思いやる心」に根底を置いていることから葛藤が起きている。
この場合他者は「「三上」と「関口」」、「「関口」」、そして「「リカ」」である。
「カンチ」は理想に従って「他者を思いやる心」として「リカ」と付き合うが、自分が他者に「愛」を持たないことが他者への思いやりに反する、という考えにおいて「リカ」と別れる。
つまり「カンチ」の理想の「他者を思いやる心」は「自分が恋すること=愛を表現すること=自分の気持ちに反さないこと」に置き換えられる。「自分が恋する」対象は自分自身であるのだから、「カンチ」の言表した「愛」とは「自分自身への思い」ということになる。
図解 「カンチ」の恋愛言表

第2項 「リカ」の恋愛言表の分析
小さい頃から商社に勤める親とともに、外国を転々とする「リカ」は「故郷」を持たない。
それが象徴するように、「リカ」には一帰結としての「恋愛成就」はない。
明確な対応関係を持たないで浮遊する「リカ」は「狭い東京」にて「広大なおおぞら」を夢見る。
世間を騒がせた「赤名リカ現象」の本質はここにあるといってよいだろう。
「リカ」は「対象を恋すること」を望んでも「対象に恋される(妙な表現だが)こと」を望まない。
「恋すること」によって「愛」の存在証明をしていく。
ところが「対象に恋されること」を望まない「リカ」は、それによって自己の「愛」の欠如を示してしまう。「愛」は存在しても、決して持つことはないこと。
これが「リカ」の「愛」である。
多くの対象との「恋」(例えば羽賀との恋)を通じて「リカ」は「愛」の欠如を明確化していき、「愛」の場所を概念的に指定していく。
その概念的場こそ「おおぞら」だ。
「リカ」にとって「カンチ」との「恋」は「東京」という「場」の仲介によってのみ起きる。
つまり、自己と他の関係を維持する仲介機能として「場」があるという構造だ。
「リカ」は「場」へ準拠すること(東京にいるからという理由で「カンチ」と恋する事)でファルスとしての「愛」を、自己と他の間に関連付けることができる。
「カンチ」との「恋」のために(あるいは恋のためでなく、準拠の結果として)「場」へ準拠する。
ところが、「カンチ」にとって、「東京」とは「愛媛」との距離の差によってのみ意味される都市(つまり愛媛じゃない場所の、何処でもいいうちの一つ)でしかなかった。
概念として「カンチ」は「愛媛」にいるのである。
ここから「愛媛」という概念としての「場」が、「カンチ」からファルスとしての「愛」を剥奪する(「カンチ」は、愛媛という自分自身を含んだ場を愛としていた)。
そこで「リカ」は「愛」を「奪われた場=「カンチ」の愛の有るところ」に求めるようになるのだ。
「リカ」の「愛」は「場」に存在する=あるいは向かっていることになる。
こうして「リカ」は「カンチ」との別れの後に「愛媛」に向かうことになる。
しかし現実の「愛媛」は「リカ」と「カンチ」を仲介した「場」ではなかった。
こうして決定的な別れの後再び「東京」へ戻る。
人と人を仲介する概念として「場」を考えるとすると、「場」を持たない「リカ」が「恋」されるのを恐れる理由が理解できる。
3年後、「カンチ」が「リカ」に再会する時、「カンチ」は「関口」と、「三上」は長崎と結婚しているが「リカ」だけは一人であった。
だが「リカ」にとっての「愛」の言表行為(愛の一方通行)に、結婚という形態(愛の相互交通)は存在しないのである。
図解 「リカ」の恋愛言表
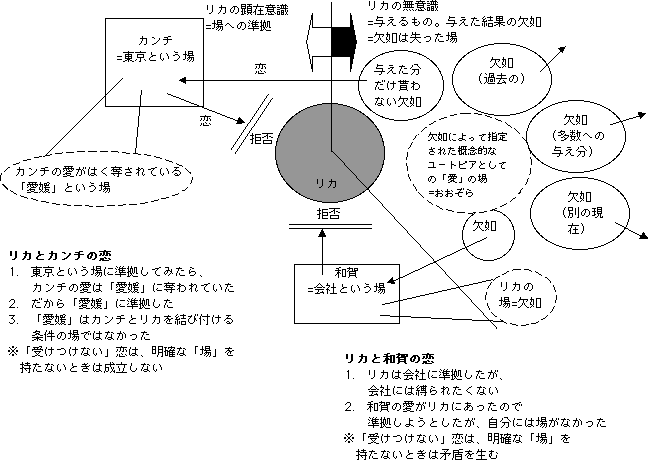
第3項 「三上」の恋愛言表の分析
「三上」は親を筆頭に、田舎つまり「愛媛」を嫌っている。
その理由は示されない。
「三上」の親は金持ちであり、「三上」も「東京」では結構な暮らしをする。
「三上」は私立医大に通っているが、それは親に金を遣わせてやりたいという反感であることだけが示されている。
ここから「愛媛」に対する理由なき反抗は、「東京」の「三上」の感情を支配していることが逆説的に理解できる。
「三上」にとって「愛媛」を土台にしてのみ「東京」が存在するのだ言葉を変えるなら「愛媛」との差異によって「東京」の意味が決定されているのだ(これは「カンチ」も同じだ)。
このことは「三上」の卒業後の夢が地方の医者になることからも、潜在的に汲み取れるのである。つまり「東京」が好きなのではない。
「三上」にとって、「東京」における「くだらない女たち」とのつきあい(これは「遊び」)は、「近づきも遠ざかりもしないもの、だから(自分を)縛ることの出来ないもの」としての「思い出としての「関口」」への反抗の帰結である。
「思い出としての「関口」」はまさに「愛媛」が象徴している。
「愛媛」への反抗となるものが恋愛言表なのだ。そのことが「東京」における「三上」の「誰とでも寝る遊びの恋」として表現される。
つまり「三上」にとって「愛」は「近づきも遠ざかりもしないもの、だから(自分を)縛ることの出来ないもの」であり、「縛る」ことへの「反抗」として、近づいては遠ざかる不特定多数の女性と交流を持つのだ。
「関口」も長崎もその一つである。
「三上」は「近づきも遠ざかりもしないもの」に自ら「近づく」ことによって、東京での「遊び=恋」を支配していたコードとしての「愛」を行為化する。
それは「三上」が医者となって地方へ赴任し長崎と結婚したことが表している。
図解 「三上」の恋愛言表

第4項 「関口」の恋愛言表の分析
「関口」は愛媛時代に親がラブホテルを経営していたことから、その反発として異常に恋愛的行為に対する嫌悪感を持っている。
このことから「関口」は「三上」との「恋」を嫌悪することになる(「三上」の恋は、すなわちSEXに結びつくものだった)。
ところが「三上」の「恋」は「愛媛への反抗」である。
「関口」は愛媛の思い出をいつまでも大切にする人物として、「三上」の「恋」に嫌悪する結果として、「愛媛への回帰」つまり「「三上」を愛する」ことになるのだ。
「東京にいて愛媛に回帰する」という矛盾は二人を別れさせる。
「二人(「三上」と「カンチ」)が仲良くしているのを見ているのが好き。ずっとこのままでいたい」という「関口」の言葉は、愛を「愛媛」で象徴していた「カンチ」に向けはじめることを示す。
「関口」は「寂しいのとか悲しいのとか、ヒョイっとすくい上げてくれた」「カンチ」を、「リカ」への純粋に献身的な態度から評価を高くしてゆく。
「関口」にとって他への「恋」も、自己への「恋」も同じように「愛」と考えている。
つまり自己から他へのコミュニケーションも、他と他のコミュニケ-ションも、本質が同じならば形態も同じものとして判断するのだ。
だから「関口」にとって過去の傷を癒す本質が「愛」であり、その方法が「恋」となるのだ。
図解 「関口」の恋愛言表
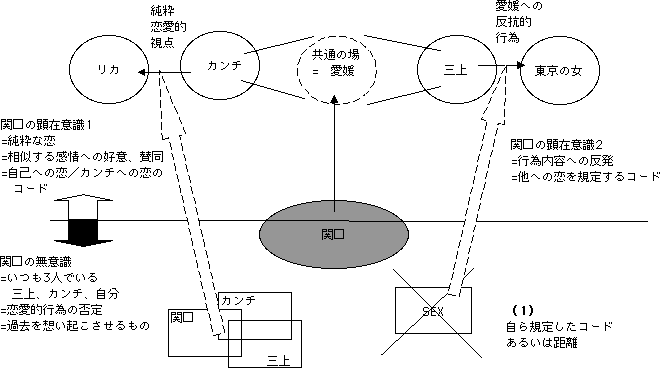
第4節 試聴の「場」についての一試論
本節は「東京ラブストーリー」の試聴という行為を通じた意味作用について論じる。第3節で述べたような「場」の指標と、メディア視聴という「場」の指標を対応させたいという試みである。しかし、この点に関しては、本卒業論文の作成において時間切れになってしまったので、一試論ということにしておきたい。いずれ、本格的に試みてみたいものである。
さて、「東京ラブストーリー」を視聴者が見るという行為は、以下のようになるといえる。
1. 「東京ラブストーリー」を、ある意味の表出として、その記号をとらえる。
2、とらえた記号を、自分が持つ意味の体系=ラングという構造に代入する。
3、構造のなかで意味を判断・検証する。
テレビドラマは視覚情報である映像と聴覚映像である言語によって意味を表出している。視聴者はあらゆる経験から、ラングを構造化して持ち合わせている。
テレビドラマも人間もそれぞれ独立してその潜在的構造を持ち合わせている。人間は視覚を持ち、テレビドラマは映像を持つ。これに関しては、テレビドラマを視覚するしないに関わらず、当該の潜在的構造は存在する。
しかし、潜在する本質だけであるテレビのスイッチを入れたと同時に、ドラマの言説は視聴という文脈の中に位置づけられて、意味生成の言表「パロ-ル」と化される。
これまで「東京ラブストーリー」における登場人物の行動から見てきたものは、「愛」という意味を「行動・心情としての恋」に変換する過程であった。
視聴者にとっても、「愛」という意味は視聴行動によって提示される。しかし映像や言語を駆使したドラマも、「愛」というものが実態のない概念であることを隠せない。「東京ラブスト-リ-」において、「愛」の象徴としてのモノが存在しても、「愛」という実質が映像で現れることは決してない。状況に合わせて「愛」という意味を文脈によって置き換えるような変換が行われているのみである。
その変換過程の一つが、視聴という文脈であることは、「愛」が「東京ラブスト-リ-」の中にしかないものではないことから理解できる。
つまり「カンチ」達が「愛」をパロ-ル化したことと、視聴によって「愛」を判断することは、記号の変換のレベルの差の問題である。
ここで以下のようなことがわかる。「愛」という本質が形態として存在しないがために「パロール」としての「恋」が「愛」と認識される、あるいは「愛」を意味していることになっている。「東京ラブストーリー」において「やさしさ」や「SEX」が「愛」として語られていたようにだ。
ならば視聴という、「他」としてのメディアとのコミュニケーションにおける「愛」の検証行為は、視聴者が「パロール」として「恋」を表象する過程と言い換えてもよい。
「愛」が意味を表現しようとするとき(それが恋であるとする)それは差異化を生む。それは、意味のレベルの差異であったり、自己と他という差異であったりする。これによって、コミュニケ-ションにおける「愛」の意味作用が生まれる。
この差異の空間を、より小さく、より狭くさせるもの。これが「場」である。
「東京ラブスト-リ-」の「場」は、自己と他を同化(狭さゆえ、鏡には奥行きがないゆえに)させたり、関係を仲介(出会うには、囲い込みが必要なゆえに)させたり、明確に指示するものを持つものとして(空間はすでになく1対1対応ゆえに)差異を作りだす........といった機能を持っていた。
つまり意味は「場」があることによって、生産されるのだ。「場」がなければ、意味は構造の網の目に迷い込んだら最後、再び出てくることはない。
視聴者が身を置く「場」とは何処か。もはや言い尽くされた電気の村でもなければ、「送り手」という資本主義のビルディングの中でもない。視線と意味が複雑に混じり合う視聴行為という、差異化と検証の渦型のピラミッド。ここである。
第5節 「東京ラブスト-リ-」の分析を通じて
「東京ラブストーリー」の分析を通じて、物語の意味作用を「恋愛」を例に説明したのだが、それは「視聴」という「場」にまで物語の意味作用が関与していることの分析でもあった。
こうして、メディアと意味の関係を考えてゆくと、メディアは、実態として存在しない限り、意味を実質的に持たないような全てに対して、視聴を意味そのものへと導くようにさせるのではないか、という結論に達せざるをえない。
つまり、視聴という行為が意味作用の根本的な規範としての役割(つまりラング・構造としての役割)を与えられることになるということだ。
「東京ラブストーリー」において登場人物が「存在しない愛」を「場」に移植して「恋」として言表したように、視聴者は「存在しない愛」を「テレビという、あるいはそれを視聴するという場」に移し替えたのだ。
メディアに意味生成の機能が付けられることによって、意味するものと、意味されるものの格差が意識的に、あるいは無意識的に拡げられることになる。実質と形態の対応関係さえも、メディアの操作(意識的な、あるいは無意識的な)の中に含まれることになる。するとメディアを支配する社会的コ-ドが意味生成を支配することになる。
それはまさしく資本主義的精神の再生産であり、経済的な要因の直接の有無とは関わらない、「恋愛」や「友情」といった感情までもが、思考や言表、態度、反応などの形で再生産されるのである。
視聴者がそれらの意味生成に了解するしないに関わらず、その支配の性格は変化しない。たとえ同意の上の認識でも、支配的強制がそこにあることには変わりはないからである。
第7章 おわりに
私がこの論文を書く直接のきっかけとなった理由は、実はほんの些細な出来事だった。
※
それは私が友人とのドライブを楽しんでいた時の事だ。夜の街を意味もなく徘徊する、そんなゆったりとした時間の流れを、軽い語らいと共に感じていた時の事だ。 言葉に疲れると手はカ-ステレオに向かった。夜の街と車と歌。この3つが揃わなくてはならない。皆が歌いだした。夜明けのなかでかかった曲に「SAY YES」があった。
この時である。友人の一人が冗談で「SAY YES」を歌い終わったと同時に、「101回目のプロポ-ズ」を提供していた会社のCMメロディ-を歌い始めたのだ。車の中は笑いの渦に包まれた。そう!思い出してみると、主題歌が流れ終わった後には、必ず同じCMが流れていた。順番も内容も、である.
※
その時冗談だった事は、そしてその時の笑い声は、確かに皆の一歩醒めた感覚を浮かび上がらせていた。楽しさに隠された目に見えない力、一瞬の笑いと引換えに盲目にも受け渡している何かを、薄々と感じ取っていた。
これといって何の魅力もない、耳をとらえない音の宣伝が、「SAY YES」と共に冗談になる。今では、もう覚えてもいないだろう商品や会社名。「101回目のプロポ-ズ」は、そんなことさえも主題歌にしてしまった。
私も友人も、決してそのCMメロディ-を覚えたかったわけではない。広告効果に影響されたとも思っていない。CMなんて好きでも何でもない。とはいえ、彼の冗談に気付いてしまった。笑ってしまった。記憶の沼に沈みかけていた広告が、「101回目のプロポ-ズ」とは全然関係のないあの広告が、脳裏に浮かんできてしまった。
私たちは何を歌っていたのだろう。もはやラブソングでなくなった「SAY YES」か、広告機能をなくした音の宣伝か。マグリットならこう言うだろうか。「君は歌っていない」と。
唇を動かせば溢れ出るメロディ-。体を動かせば揺れ出るリズム。会話のハ-モニ-。「音楽」はこんなにも簡単に見えて、「歌」わずにはいられない。しかし、「歌うこと」は決して簡単なことではない。投げつけてくる意味の矢から身をかわしながら、時には意味の沼に溺れないように、時には意味の森に迷わないように、「音楽」すること。それが「歌うこと」だ。
カラオケボックスには意味の監獄に閉じ込められた「歌」達が、面会を待っている。デパ-トにはサラリ-マンとして働く音楽が、役目という意味を遂行している。そして、テレビの絵本を開くと、「感動と共感」が翻訳されている。
歌っていると思っている人は、歌わされていたのだ。意味に縛られた私の友人が、笑いをとるためにCM音楽を口ずさまなくてはならなかったように。
※
ドラマの虚構/社会の現実という対立を越えて、全てのモノや行為を意味の体系に縛ること。これこそ権力の概念だ。そして権力の「場」は確実に存在している。民主主義の根源は「場」を均等に分配することだったはずだ。ところが、「合理化」「労働と生産」「消費」「愛」「趣味」「価値」などの、社会的精神や個人的精神の意味を作りだす体系は、権力を中心化している。
権力は、核の恐怖や暴力、支配/被支配の関係などだけに存在するのではない。点在する権力をまとめる「場」がある。それは民主主義をあやつっている力なのだ。 よく考えれば、私たちは生まれたときに、既にあらゆる意味の体系に位置づけられていたのかもしれない。客観的で完全な自由など、ユ-トピアでしかないのかもしれない。しかし、それが利用されていることは、全く別問題だ。全ての人々が、同じように思考・判断したり、同じようなモノが溢れたり、同じような場所で、同じような行為をする光景は、そら恐ろしい。これは意味のファシズムとでも言えるのではないだろうか。
※
私はこの論文を通じて、決して流行現象やメディアを積極的に読み解く「受け手」像を否定しているわけではない。実際に、私は「101回目のプロポ-ズ」も「東京ラブスト-リ-」も生で体験した。見ている時は楽しかったし、感動もした。泣きそうになったときも・・。私なりの解釈をし、私なりの視聴スタイルで、それを体験した。
ただ、誰もが同じようにトレンディ-ドラマの曲を聞いていたり、ドラマのような恋の話ばかりしたりすること。あるいは、盲目にも、売れているからといって、トレンディ-ドラマの主題歌だったという理由だけで、商業音楽に口を塞ぐことや、芸術/大衆の価値判断からだけで、物語を「開かない」こと。このようなことに触れるに従って、私は流行現象の弊害や、メディアを積極的に読み解く「受け手」像という知的な傲慢さを感じていた。
好きなことにお金をかける人のことも、それを使って儲ける人のことも、私の思考の対象外にある。「だます・だまされる」は表裏一体だ。しかし、権力に支配された「意味」を使って、判断した思考を押しつけること、これは見破らねばならない。その批判の一つ一つが、メディアを積極的に読み解く「受け手」像という、理念型ではない実態を照射するに違いにない。
※
※
「SAY YES」と「ラブスト-リ-は突然に」から意味を解き放って、もう一度、耳を澄ませてみよう。きっと大切にすべき宝石のぶつかり合う音が聞こえるはずだ。しかも宝石箱に入れたままの宝石ではない、大切に身にまとっている宝石の音が。
終
special THANX to.......
- Seigo Yamanaka
- Atushi Katayama, Tomo Ochiai, Chigusa Ito, Mr.Kanai, Mr.Yazaki, Kumiko Sato, Yukiko Ushikosi, Mr.Oochi, Mr.Kawazoe
- Fumiko Kikuchi
- Hironobu Takahasi, Hiroyuki Nakamura, Yasumasa Ohizumi
- Katuhiro Iwama
- Seiji Kimura, Sachiko Kitamura
- Jun Takahashi
- MUSiC JUNCTiON,beat club,seijo univ,Laser TX-R,audi gle,hutari-no-coffee-jinn,video research
- Natsuko Sekizawa
- Taku Ariyasu,Tuyosi Ohwada,Yasuhiro Ida
- Kyoko, Yumiko, Koujun, Miho, ,Rituko, Megu
- Takato Kuwahara, Hidekuni Shida
- Akira Masuda, Takahisa Suzuki
Get In Touch.
よろしければお気軽にメッセージをお寄せくだされば幸いです。
Error
Your message was sent, thank you!
第1節 人間と音楽 ~近世までの音楽史
第2節 メディアと音楽 ~メディア時代の音楽史~
第3節 広告と音楽
第4節 まとめ - 音楽と社会 -
第1節 テレビドラマの商品性
第2節 労働・商品としてのテレビドラマ
第3節 トレンディー・ドラマとは ~トレンディー・ドラマの変遷~
第4節 「T.R.E.N.D.Y.」現象と原因
第1節 主題歌の流行現象について
第2節 「タイアップ」というブロックバスター型メディア戦略
第3節 主題歌と象徴
第1項 「ラブストーリーは突然に」の歌詞の内容分析第4節 主題歌の音楽的テクスト
第2項 「SAY YES」の歌詞の内容分析
第3項 「SAY YES」と「ラブストリ-は突然に」の共通性
第5節 主題歌の露出とイメージ付け
第6節 主題歌の流行という現象と原因
第1節 トレンディドラマのシミュラークル性
第2節 トレンディドラマ分析の意義
第一節 登場人物の指標 ~主体と構造~
第二節 映像的諸要素の指標 ~モノと生活~
第3節 感情的諸要素の指標
第1項 恋愛的相互作用の集合表象的側面第4節 構造から現実へ ~指標の比較研究への視座~
第2項 集合表象的「愛」の記号的表出
第3項 集合表象の受容の記号的表出
第4項 互酬と非互酬の記号的表出
第5節 結婚観の意味作用
第1項 20代OLの持つ「結婚」観の現在第6節 指輪の意味作用
第2項 テレビドラマ内の「結婚」観
第3項 視聴者と検証行為
第4項 結婚行動の現在
第1項 宝飾品に関する消費者意識第7節 「101回目のプロポ-ズ」の構造分析を通じて
第2項 ドラマ内の指輪の意味
第3項 視聴者と検証行為
第4項 達郎と薫の指標比較から見た消費行動
第1節 登場人物の行為分析(簡易版)おわりに
第2節 言語/恋愛/記号
第3節 主体の無意識の指標分析 ~恋愛言表の分析~
第1項 「カンチ」の恋愛言表の分析第4節 試聴の「場」についての一試論
第2項 「リカ」の恋愛言表の分析
第3項 「三上」の恋愛言表の分析
第4項 「関口」の恋愛言表の分析
第5節「東京ラブスト-リ-」の分析を通じて
序章
ドアを開けると、8帖ほどの部屋が広がった。
黒い壁の内装はちょっとした高級マンションを思わせる。ソファ-にテ-ブル、角には大きなモニタ-テレビが座っている。これからの2時間は二人の空間になるのだ。
店員が注文を待っている。
「君は何飲むの。え-と僕は........とりあえずビ-ルをもらおうかな」
「わたし、なにかカクテルがあれば........あっ、これにするわ、カシス・ソ-ダを」
「じゃあ、ビ-ルとカシス・ソ-ダでお願いします」
軽やかな会話が進んだ。とりとめもない話だ。
何だか分からないまま笑顔が二人の間を何往復もする。こんな笑いが自分の今の幸せな気分のバロメ-タ-になっているることに、達郎はちょっとした満足気分を味わっていた。
飲み物が来て乾杯する。グラスの音が心地よい。
「始めましょうよ。あなたからね」
薫がすすめる。
「そうだね」
達郎は上着を取って立ち上がった。
と、その瞬間流れだすイントロ・・<SAY YES>だ。
{余計なものなど無いよね・・ああすべてが君と僕との 愛のかまえさ・・}
達郎は薫の目を見て歌った。まるで歌に心を託すように。
恥ずかしそうに歌い終わると達郎は薫にマイクを渡した。薫の前で歌うのは初めてであった。達郎は何度か薫の歌を聞いたことがあった。薫は歌がうまい。アマチュアバンドでボ-カルをやっているのだ。そのシルクのような滑らかな声と美貌はそこいらではちょっょとした人気である。達郎は何度か薫のライブに招待されていた。
「上手じゃない」
意外な答えだった。少なくとも歌には自信がなかったのだ。
2百円を投じて薫が選んだ曲は小田和正の<ラブスト-リ-は突然に>だった。テレビドラマとして人気のあった「東京ラブスト-リ-」の主題歌だった曲だ。
{・・あの日 あの時 あの場所で 君に会えなかったら 僕等はいつまでも・・}
美しいメロディ-が薫の口からこぼれ落ちる。薫も達郎の目を見て歌っていた。
2時間はあっという間に流れた。
※
「え-っ・・・7500円になります」
※
1991年、200万枚を越えたシングル・セ-ルスを記録した曲が2曲生まれた。
小田和正の歌う「ラブストーリーは突然に」と、Chage&Askaの歌う「Say Yes」である。両曲ともフジテレビのテレビドラマ「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」の主題歌であった。
本稿は、このブロックバスター型のメディア現象を通じ、テレビドラマとその主題歌の人気の周辺に存在するさまざまな「力」「心」、「モノ」を分析し、そこに表れた現代社会と人間の関係に迫ってみる試みである。
上記のストーリーは、私があえて恥ずかしくなるようなイメージで作った、カラオケボックスでのワンシーンである。ここにはテレビドラマという現実の模倣であるはずのものが、二人の行動の指針になっているという状況が見出せる。上記のストーリーの主人公の作りだす恋愛世界は、二つのドラマがなければ全く異質のものと変容していたであろう。音楽と感情の合流、音楽の記号化、物語と時間のパッケ-ジソフト化、商品化..........。これらの出来事は、テレビメディアと人間との間の、どのような関係によって作り出されたのであろうか。
トレンディードラマの流行という現象は、マス・コミュニケーションの過程の結果である。この流行現象は、テレビメディアと人間のコミュニケーションによって、「結合され体系化されたある心理的な一つの様式る(デュルケイム1895)」である。流行現象の結果としてできた集合体は、「そこに存在する個人とは全く違った仕方で、思考し、感覚し、行動する(デュルケイム1895)」。そこには個人の意識に関わらない、命令と強制の力がある。このように、流行現象とは、マス・コミュニケ ーション過程によって形成される社会的なものである。
これからの試みは、「101回目のプロポ-ズ」と「東京ラブスト-リ-」という具体的なテレビドラマ、およびその主題歌である「ラブストーリーは突然に」「Say Yes」を対象に、マス・コミュニケ-ション過程と流行現象について分析し、メディアおよび視聴行動に内在する権力分配の合意にまつわる構造を明らかにするものである。いわゆる「マスコミの限定効果説(クラッパー 1966)」や「利用と満足に関する研究(岡田 1976)」など行動主義的なマスコミ研究の文脈では、「受け手」が批判的に自由に読み解くメディアという側面に光が当てられているように思う。マスコミの効果・影響について大きく論じるのは、いささか古臭くも感じる点がある。しかし、こうした観点からは掬いとれない、メディアと「受け手」の合意や権力構造について、「意味」や「テクスト」の生成という観点から、あえて批判的に考察していきたいと思う。
第一に、テレビドラマが「いかにして流行現象と化していったのか」という現象の「原因」 について考察する。マス・メディアによる流通と流行はどのような性質を持つか。間接的な消費としての電波、直接消費としてのCDはどのように商品化されたのか。メディア自体を巧みにマ-ケティングに組み込んでいった方法、そこに触れた視聴者への効果などについて論じる。ここでは、消費社会・資本主義社会におけるマス・コミュニケーション過程の構造を明らかにする。
第二に、テレビドラマに映し出された内的世界を詳細に分析し、現実の世界との関わりについて考察する。テレビドラマはいかなる構造を持ち、それに関わった人間はどのように変容していくのか、「構造分析」や「精神分析」的な方法を用いて分析する。この分析から、マス・メディアが果たす「機能」を 考察していきたい。
現象の「原因」と「機能」を分析するという点で、デュルケイムが「社会学的方法の規準」で論じたような社会学的分析となるだろう。また「マス・コミュニケーションの総過程(田中 1968)」にふれることで、構造的な分析になるだろう。
第1章 コミュニケ-ションとしての
ポピュラー音楽・人間・メディア
まず流行現象の「原因」を明らかにするため、ポピュラー音楽そのものをメディア論的に考察しておきたい。
テレビドラマにおけるメディアとしての主題歌の機能を考えると、それは視覚だけでは伝えられない感情や雰囲気の創出であると言えるだろう。しかし、このような創出が可能となる理由はどこにあるのだろうか。
現在のポピュラー音楽は、メディアそのものの変化や音響技術などの発展・向上に伴って多様化している。近代化を背景としてマス・メディアが発展し、「受け手」と「送り手」の関係は大きく変化した。ポピュラー音楽の享受の仕方、さらに音楽自体をも変化させている。
ところで、「人と人とのインターフェイスとしてのメディア」の存在を考える以前に、音楽というものの構造が「送り手→受け手」という基本的なコミュニケーション構造を持つことに変わりはない。
そこで、音楽とは人間にとって何であるのか、そもそも、音楽とは何なのかという、基本的な人間と音楽の関係を歴史を紐解くことによって、本研究のメディア論的背景を見ていきたい。第1節 人間と音楽 ~近世までの音楽史
( 本節はシュバープの著作に強い影響を受けました)
映像と音楽の関係を理解する上で、こうした非言語的コミュニケーションであった時代の音楽とその変化をふまえることには一定の意義がある。またテレビドラマと主題歌およびその社会学的文脈での理解には、音楽が社会性を持つ過程の理解が欠かせないであろう。本節は音楽学者シュバープの論を中心に、音楽の起源から中世までの音楽を考察する。
音楽という手段で自分が無名になっていくことが大事だと思う
武満 徹 「FM fanインタビュー」より
「音楽がいつ発生したか」というテーマには、「音楽とは何か」そして「音楽を音楽と規定するものは何か」という問題がつきまとうだろう。言うまでもなく正解はない。作曲家の表現を具現した「作品」が音楽なのか、はたまた机を叩いた「音」から音楽を定義すべきなのか。ここで一つ言えることは、音楽は音によるコミュニケーションであるということだ。音楽の発生段階においては、言葉以前の非言語的コミュニケーションであったといえよう。
人間が一つの動物として進化し始めたとき、生存のための攻守両面における連絡としての叫び声や、意味を音程に持たせた叫び、楽器として利用される以前の打音などが利用されていたと言われている。先史時代の出土品にはそうした楽器らしき存在を物語るものがある。
未知といわれるような時代において、人間には社会と呼べるほどの組織的な機能はなく、ある単位の「群れ」をなして生活を守ろうとした。人間は言葉を持った。言葉を知ると言語として規定できない自然の模倣を試みた。集団を形成する初期の意識の連帯として、信仰が生まれた。神に対する語りかけは日常の言葉とは差別化された。多くの儀式における独特の昂揚のある言葉やリズムから、音楽の発生が予測できる。
このように、現在の音楽といわれるものの存在とは考えを異にする、生活、信仰、政治と直接関わってくるものとして、音楽は発生したといえるだろう。
音楽がより音楽「らしく」なる過程は、社会構造の発展と共に進んだといえる。より複雑なリズムやハーモニーを持つ音楽が、生活に密着し根づくものとして社会に広まってくる。人々はリズムが仕事に「のり」を与え、効率を上げられることを、生活の知恵として知っていた。音楽は生活の反映でもある。このような音楽は現実に鳴り響く音として残っていないまでも、世界中の民族音楽や伝統音楽にその一部を垣間見る事が出来る。
人間は情報の交換の手段として音楽を利用し、その情報を個人内で処理していく(カード、モラン、ニューウェル 1983)。この過程において、個人内での情報処理の方法は、情報内容(この場合、音楽)によって、また各個人内の既存の経験によって変化する。こうして音楽が社会性を獲得していくのである。音楽コミュニケーションの形態と音楽文化の関係は、こうした社会性に見ることができよう。
近世の音楽を一言でまとめるならば「非日常と遊びの空間としての音楽(シュバープ 1986)」といえるだろう。教会の社会的地位の向上と音楽の祝祭空間との結合は、音楽の階層化・階級化を生んだ。貴族のための祝典音楽、宮廷における演奏、学者のためのアカデミー・コンサ-ト、学生の仲間同志の音楽、身分の低いもの同志の競演・・など社会の階層化にしたがって、音楽はその情報内容を多様化させてきた。また音楽の行事化は、人間を演奏する側と聞く側に分化させた(シュバープ 1986)。
17世紀は経済上の大変化が社会に見られる時代でもあった。自給自足経済は資本主義経済へと移行し、都市が発展した。商業主義の思想は音楽にも及んだ。音楽の娯楽的要素と、「弾く/聴く」の分業化を利用したコンサートが多く開かれるようになった。入場料を払えば音楽に参加できるという形態は、不特定多数の聴衆をあてにした音楽の販売行為の始まりだった(シュバープ 1986)。
近世の音楽の歴史からは、音楽コミュニケーションの大衆化が、社会の変化と同時に進行していることと、それによる音楽の変化がみてとれる。
第2節 メディアと音楽 ~メディア時代の音楽史~
別に音楽一筋に生きるつもりはない。かと言って詩や絵、ファッションに没頭する気もない。その時に強い印象を与えてくれるものをやりたいんだ20世紀に入ると音楽コミュニケーションの形態は大きく変化した。メディアの発展によるマス・コミュニケーション化が進んだことが要因である。これまでの音楽が即時的な「いま・ここで」というような一回性に特徴づけられるものだったのが、産業革命や電気革命によって複製可能となり、「いつでも・どこでも・何度でも」というような新しい聴取のスタイル、コミュニケーション形態が現れたのである。
トーマス・ドルビー 「Sound & Recording Magazine」誌 インタビューより
こうした聴取スタイルというコミュニケーションの形態の変化を考慮に入れておくことは、テレビドラマの主題歌の役割を考察する上での視点を提供するであろう。そこで、音楽メディアの発展を簡略に年表で示したものが図1である。表に記したものは、音楽コミュニケ-ションの形式に変容を与えたと思われるものに絞った。
略年表図1(引用失念しました。失礼します。)それぞれの年次のメディアの変化について簡単に説明しておく。
音楽とマスメディア (1) 1878 エジソンによる蓄音機免許取得 (2) 1920s レコードの発達 (3) 1948 コロンビアレコード社33、1/3LP盤発売 (4) 1940s ラジオの普及 (5) 1953 テレビ放映開始 (6) 1958 ステレオレコード発売 (7) 1959 民放の開局 (8) 1960s FM/テープ/ステレオの普及 (9) 1967 オールナイトニッポン(深夜放送)開始 (10) 1968 ラジカセ発売 (11) 1975 カーステレオの普及 (12) 1979 SONY社ウォークマン発売 (13) 1980s CD/DAT/レーザーディスクなどデジタル化
(1)(2)であるが、音楽が「複製」可能になったことは、音楽をめぐるコミュニケーションに急激な変化をもたらした。現在の電気を通じた音楽をめぐるコミュニケ-ションの始まりはここにある。
(3)が示すものは、レコ-ドが「商品」として「大量に生産」されるようになったことである。こ音楽が「大量複製」されることを意味する。 (4)では、それがラジオで流されることにより、さらに「販売」が「促進」され、より「多くの聴衆」を得る。音楽をめぐるコミュニケーションの「大衆化」の始まりである。「ポピュラ-音楽」という「新しい領域」の確立ともいえよう。
(5)(7)を通じ、音楽は「映像」とミックスされる。音楽は、「情報」の観点からより複雑な「メッセージ」となる。情報の「受け手」である視聴者の、音楽聴取のスタイルも少しずつ変化してくる。私たちの聞く音楽が、テレビの提示する世界と、同時に触れ合うこと。これは私たちがコミュニケーションの傍観者になったことといえるのではないだろうか。あるいは音楽コミュニケーションを内に含むコミュニケーションとして考えられるかもしれない(図2)
テレビのもつイメージ、文化、社会を通じて一つのものへと収斂していくものの誕生である。聞くことという娯楽の形態は風俗などと結び付いた。ツイスト、サーフィン、ダンス・・・等。
(8)では音楽が特定の場から「開放」され、より深く「日常空間」に浸透した。コンサート会場はこの時点で音楽のアジールとしての機能を失くしはじめるのである。かくしてラジカセが仏壇に収められることになる。神棚のテレビに変わって.......。
図2メディア・ミックスとコミュニケーション(音楽)
送り手-[送り手→受け手]-テレビ
↓
受け手-視聴者
(9)はAM放送の深夜放送のことである。深夜放送は「若者」に人気を得て、若者文化と密接に結びつき、若者の中心的な音楽メディアとなり、フォーク、ロック、ニューミュージックなどの音楽を支えたと言われる。
(10)では好みの音楽を好きなときに「録音」し「再生」するという、音楽の日常化である。
(11)では音楽の「パーソナル化」がさらに進展した。コンサ-ト会場からステレオ、ラジカセのある部屋へ、部屋から電車のなかへ、電車のなかから車のなかへ。思い起こせば音楽はそれ自身において、移動体の性格を内在していたはずだ。街の街路での出会いのように。都市が人々を切り離すように、テクノロジ-が音楽をある領域に定住させる。そして出会いのない速度機械での移動........。再び開放された音楽......。しかし人々は歌うことはない。近代社会の音楽は交通である。所有の意味が問われる「パーソナル化」である。
1980年代は音楽のデジタル化に注目すべきだろう。CDはアナログレコ-ドを短期間で衰退させた。アナログとデジタル...........数字であるなら全く同じコピ-が作れる。保存、流通にも便利で情報量も多い。「情報化」時代において、音楽が溢れる情報の一つになっていることを、象徴的に表した技術革新である。カラオケは音楽を、「遊びに伴う」ものから「遊び自体」にした。CD、LDなどの普及は良質な音を提供し、視聴者の「聞く」レベルをある意味で向上させているかもしれない。
エレクトロニクスよりも木のアコースティック・クオリティーの方がはるかに重要だ。サウンドに最も影響を与えるのは木なんだ。スピーカーから聞こえてくる音楽。機械とのコミュニケーション。そこには作曲家の作品を具現しようとする演奏者の能力や苦悩に触れる遭遇はない。音楽完成の瞬間の稲妻の光、adam&ive的な不完全性へのあこがれも忘却の彼方にある。私たちが小さな円盤を再生機にかけ「本物」と思っているものは、「実は『コピー』なのだ(清水 1972)」。人間の活動範囲を越えて到達した音楽からは、誰が演奏しているのか確かめる術はない。オリジナルなものは遠くにあって手も耳も届かない。「実物はコピーと照合することはできない(清水 1972)」のだ。しかし私たちはコピ-に満足するしかない。コピーに向かって一喜一憂するしかない。
ロジャー・サドウスキー 「ギターマガジン」誌 インタビューより
では送る側の意図はどうだろう。送る音楽の取捨選択は一部の独占的な企業によって行われている。そしてコピー作り(ソフト制作)は営利事業である。資本主義的な観点から行われる取捨選択は、マーケティングという「万人主義」や「平均主義」である。すべては売れなくてはならないのだ。こうして公衆は、意識ある消費者と自らを思いながらも、一方的に流される音楽に「音楽」を見出せないまま、消費するのである。マス・コミュニケーション化した音楽に、マス・コミュニケーションの諸問題があてはまることは、現代音楽を論じる際に決して見逃せない要因である。第3節 広告と音楽
(本節は、小川博司先生の著作に大いに影響を受けました。論文全体もですが....)音楽からメタリックな輝きを奪い、閉じた空間の中に重く沈殿させる、いくつもの罠。その中でも最大のものが「意味」と「情念」にほかならないブロックバスター型メディア・ミックス時代のテレビドラマと主題歌の関係を理解するにあたり、コマーシャルと音楽という先行研究は極めて示唆的である。
浅田 彰「ヘルメスの音楽」より
パッケージ化された音楽の大量生産と販売は、新しいメディアに適合した音楽を生み出した。ポピュラー音楽、テレビのCM音楽、イージーリスニング・ミュージックなどだ。これらはいずれも生活、時間、価値を消費するという傾向と深く関係しているように思われる。そしてメディアと音楽、メディアと消費、消費と音楽という三つ巴関係を考察するにあたり、ラジオやテレビなど、音声のあるメディアが登場して以来、変化してきた広告と音楽の関係の歴史を振り返ることは欠かせない事である。この論文のテ-マの一つである、メディア利用によるブロックバスター型の消費戦略も、これらの一つの延長と考えられるからである。消費の促進と価値形成に大きな力をもつ広告と、音楽はどういう関係にあるのか、主に小川博司の研究に着目し論考していきたい。
「我々は現在音楽に接しない場面に遭遇するほうが難しい(小川 1988)」と小川博司の言葉にもあるように、意思に関わらず投げつけられる音楽は、なぜこれほどまでに大量に流され続けられるのだろうか。その答えの一つに、音楽の広告効果があげられるだろう。それは、ただ鳴っているだけの効果から、音楽のもつイメージ付け効果まで実に多様だ。ラジオやテレビといったメディアは音声機能が重要な役割を果たしているが、その感覚的な効用は、媒体がマス化すると共に注目され、また、常に新しい音楽シ-ンを形成してきた。
この広告音楽の流れを小川(小川 1988)は次のように整理している。テレビ、ラジオが登場して「広告と共に音楽を」という形でCM音楽が広まった。広告音楽は音楽の利用のされ方と広告の形態によって大まかに3段階に分けることができる。
まず初期段階である。1950-60年代中盤までは、CMにおいて音楽は「歌」というよりも「サウンド」として使われた。具体的には簡単なメロディーに、商品名の連呼だけといったものだった。流行歌とは別世界の機能重視のCM音楽である。この背景にはモノを中心にした広告形態があるといえる。
1960年後半あたりから、映像と音楽の結びつきの生む感覚的な効果が注目された。この段階ではサウンドの効果が中心であった。言語的な直接のモノへの言及ではなく、サウンドによるイメージの提示となったことは、モノ離れした広告形態と消費ブームが背景にある。
さらに1970年代にはいると、音楽によるさらなる個性化と差異の主張がなされた。ここではヒットした曲をCMソングとして利用することで、商品なり企業なりを、消費者に注目させよう、知らせようとする。これは音楽からのイメージの転化を狙ったものだ。「音楽が好きだからその商品も気に入ってきた」といったアピ-ルだ。企業のキャンペーン広告とアイドル人気が重なったこの時期に、イメージソングは最盛期を迎える。
音楽もモノも同じで、企業は業績重視である。価値の名の元で、モノや資本主義的情念に屈する音楽.........。それは利用か、大道芸か。いや、むしろ意味からの脱却にこそ、広告時代の音楽が音楽たりえる契機ではなかろうか。
1980年代になると、広告の音楽による個性化と差異主張はさらに声高になる。ありとあらゆる音楽が使われるようになる。聞く側の差異化も進む。メディアの発展とともに音楽の嗜好は細かく分化した。一つの尺度では捕らえられない大衆という、現在の大衆をターゲットにした広告音楽が成立してくる。誰にでも受け入れられる、気に入られるといった音楽よりも、良質さやマッチングのセンス、奇抜さなどが主張される。例えば、ホンダ車のプレリュードのどこにボレロの荘厳さがあるのか、疲れたサラリーマンがアリナミンAを飲みながらなにが「What A Wonderful World」なのか、やや疑問なところだが、音楽文化はこうして生活に根付きながら広まっていくのである。
広告としての音楽を見ていくと、音楽事業にも目がいく。企業メセナとしての音楽支援だ。「冠コンサート」とよく言われる。「こんなアーティストを支援して、我が社はこんなに文化的ですよ」といわんばかりの広告事業である。海外有名アーティストを音の悪い米粒程にしか見えないような大ホ-ルに招聘し、10日間も連続で1万円もとっても「文化的」な企業である。言ってみればイメージソングの事業版である。「バブル経済崩壊だ」といっては真先に文化支援を止めてしまうのも「文化的」な企業である。おおむね「文化産業」とはこうした、広告音楽的で、市場の論理を優先するものである。
このように広告音楽の変遷をみていくと、メディアを介した音楽が、音楽シーンをリードしてきた事がよく理解できる。メディアの作った流行現象が数多くのヒット曲なりスタンダ-ドなりを生んだことは、人間の豊かさを、音楽というコミュニケーションを通じた人々の生活に活性化を与えた点で、メディア時代の音楽は「公的」な文化財でもある。しかしこの公害性も決して無視できない。
第4節 まとめ - 音楽と社会 -
以上、人間・技術・広告の観点から、音楽をめぐるコミュニケーションについて見てきた。まとめてみたい。
1、音楽は人間が生存するのに欠かせない、コミュニケーションの1形態である。
2、音楽はコミュニケーションの結果として、生活や社会的集合体を作りだす。
3、音楽が作りだす社会的集合体は、資本主義社会に利用される。
音楽をめぐるコミュニケーションを社会学的に「現象の原因」の背景として見ていくことと、音楽が作りだす社会的集合体について考えることは、トレンディードラマを分析する際に有効であろう。主題歌はパッケージソフトとして実際に流通機構にのる。それに対し、テレビの試聴行為は、実際の数値的な消費を表さない。主題歌の販売量などのデータは、実際の数値から、経済的な集団を考えることができる。そしてこの集団を、テレビ試聴の集団にシフトしてゆくことが可能になる。
こうして曖昧な視聴率からだけでない、メディアが作りだした社会の規模・性質をより明確に知る事が出来る。
第2章 トレンディ-・ドラマ現象とその原因
第1節 テレビドラマの商品性
1991年オリコン・シングル・レコードチャートでは、1位がChage&Askaの歌う「Say Yes」、2位が小田和正の歌う「ラブストーリ-は突然に」だった。これらは二曲ともテレビドラマの主題歌である。この現象はメディアと音楽、そして消費の関係の一つの新しい形態と言えるだろう。このブロックバスター型の消費現象の実態を、テレビドラマの商品性という観点から考察し、トレンディ-・ドラマ現象とその原因について明らかにしていきたい。
今日、小説や新聞を開きテレビをつけるという行為は、いかにも身近で無造作なものだが、しかしこのささやかな行為が、その後必要となる物語コードを、我々のうちに一挙にもれなく備えつける
ロラン・バルト 「物語の構造分析序説」より
テレビドラマに関して論じる前に、「ドラマ」という言葉について明らかにしておく必要がある。「ドラマ」とは「演劇、劇、戯曲、しばい.....」などなどである。「劇的な」というような意味合いもある。
この論文において「ドラマ」とは便宜的にテレビドラマを指すことにしておこう。「演劇」という言葉は、辞書には(辞書にもよるが)「扮装した俳優が劇場で脚本に従って種々の言語、動作を見せる芸術」とある。であるからテレビドラマとは、簡単に言えば「テレビで見れる作り話」がテレビドラマである。
同時にテレビというメディアによって行われる放送であり、それによって起きるコミュニケ-ション過程においての情報、メッセ-ジである。テレビの内容分類(中野 1963)からみてみると「報道・教育・娯楽・その他」のなかの「娯楽」にテレビドラマは分類されるだろう。
第1節 労働・商品としてのテレビドラマ
テレビドラマという放送を、消費社会になかで「商品」として位置づけて論じる際に、その商品性をいかにとらえるか。労働の代価となるものを商品としてとらえ放送の商品性を論じたのが稲葉 三千夫の「マス・コミュニケーションの生産過程(稲葉 1963)」である。以下はその簡単なまとめである。これを前提に次の考察に進みたい。
マルクスは労働を「人間がその自然との物質代謝を彼自身の行為によって媒介し、規制 し、調整するところの一過程である」と定義している。そして「労働過程が営まれるからにはそこには3つの契機(労働そのもの、労働対象、労働手段)が存在する」と述べている。
資本主義社会の発展と共にコミュニケーションのマス化が進み、組織として発展した 。
マス・コミ産業は上のような労働過程を含む資本家である。彼の労働手段は技術を利用した放送である。そして労働対象は彼の見る世界とその表現である。彼の見るものは社会であり、かつ資本主義社会においてそれは商品である必要がある。さらにはその商品は受け手の欲求を充足し、享受されなくてはならない。ここから放送は商品であることが分かる。
報道にしろ教育にしろ経営のための商品であることには変わりない。マス・メディアが単なるサ-ビス業とは異なるとはいえ、制作活動が労働の中心となっていることは放送が商品であることを表していると言えるだろう。ここからテレビドラマの商品性に着目し、トレンディ・ドラマ現象という経済現象を対象に、現象の原因を明らかにしていきたい。
第3節 トレンディー・ドラマとは ~トレンディー・ドラマの変遷~
自分たちが見て面白いと思うものを同世代感覚で作ったんですよ
大多 亮 「朝日新聞 インタビュー」より詳細な「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」の内容は、後々説明することになるが、ここでも簡単に述べておく。
図3 
浅野温子
「101回目のプロポーズ」
「君の瞳をタイホする」ほか織田裕二
「東京ラブストーリー」
「あの日の僕を探して」ほか

今井美樹
「以外とシングルガール」
「思いでにかわるまで」ほか石田純一
「抱きしめたい」
「思い出にかわるまで」ほか

石田ひかり
「君だけにできること」
「悪女、ワル」ほか江口洋介
「愛という名のもとに」
「もう誰も愛せない」ほか

田中美佐子
「結婚の理想と現実」
「10年愛」ほか柳葉敏郎
「素敵な片思い」
「ハートに火をつけて」ほか

中山美穂
「素敵な片思い」
「君の瞳に恋してる」ほか吉田栄作
「キモチいい恋したい」
「君だけにできること」ほか

浅野ゆう子
「君の瞳をタイホする」
「ハートに火をつけて」ほか唐沢寿明
「愛という名のもとに」
ほか

小泉今日子
「あなだけ見えない」
「パパとなっちゃん」ほか大鶴義丹
「君の瞳に恋してる」
「逢いたいときにあなたはいない」ほか
「東京ラブストーリー」は、3人の同郷の同級生が東京を舞台に東京で出会った友人を織りまぜての恋愛スト-リ-。出会い、恋、別れ・・といったストーリーが何パタ-ンかあり恋愛感情を中心とした描写が特徴である。
「101回目のプロポーズ」は、99回お見合いしても結婚できない中年サラリーマンと、過去の婚約者を結婚式当日に亡くした100回目のお見合いの相手の美人音楽家との恋愛ストーリー。主人公のひたむきな愛と相手の迷いを中心に、周囲の友情と恋愛をストーリーに散りばめている。
両テレビドラマとも現在人気の「トレンディー・ドラマ」と呼ばれるものだ。二つのテレビドラマに共通する点がいくつかある。第一に恋愛ストーリーという点である。また第二の共通点として製作主体があげられる。この二つのテレビドラマは「フジテレビ」が制作したものである。
「素敵な片思い」「東京ラブストーリー」「101回目のプロポーズ」の三作は、制作段階から、純愛3部作として一連のシリーズものとして製作されている。
第三の共通点は、上記の3つのドラマに共通のプロデューサーが関わっていることである。大多亮氏だ。
第4に俳優や描写の面でも共通点がある。テレビドラマを演じる俳優はほとんど全員(「101回目のプロポーズ」の武田鉄矢は例外?)いわゆる美男美女ぞろいである(図3)。彼らは都会派スタイルの生活を送り、仕事よりアフタ-ファイブを楽しむ。ちょっと使ってみたくなるようなセリフ回し。若者のある種のあこがれを表現したものと見ていいだろう。
簡略ではあるが、トレンディ-ドラマの歴史を振り返ってみよう。始まりは1986年にTBSの放映された「男女7人夏物語」。翌年「君の瞳をタイホする」で本格的にトレンディードラマが始まる。その後はフジテレビが次々とトレンディ-ドラマを放映し、「トレンディードラマといえばフジ」という図式ができあがる。1988年の「抱きしめたい!」「君が嘘をついた」。1989年の「君の瞳に恋してる!」「ハートに火をつけて!」「愛しあってるかい!」。1990年は「世界で一番君が好き!」「恋のパラダイス」「キモチいい恋したい!」。TBSは「想い出にかわるまで」「クリスマス・イブ」と反撃する。
(卒論を書き終えて10年。インターネットが登場し、トレンディ-ドラマもHPで詳細に紹介されている。以下のサイトは、こうしたトレンディ-ドラマの歴史に非常に詳しい。御参考にどうぞ。)
- トレンディ・ドラマの系譜
- テレビドラマデータベース
第4節 「T.R.E.N.D.Y.」現象と原因
WARNING: ADVERTISING CAN CAUSE SERIOUS DAMAGE TO YOUR BRAIN AND OUR WALLET
モスキ-ノ/MOSCHINO 広告ポスタ- より
なぜこのようにトレンディードラマは爆発的な人気を得たのだろうか。こうしたトレンディードラマは、大多氏のいう「同世代感覚」以上に多くの世代間で共鳴を呼んだ。時代背景は「バブル経済」の真っ最中。
そこで、本節では、この流行の原因について、キーワードでもある〔T.R.E.N.D.Y.〕という単語を使って、分析してみたいと思う。 トレンディーとは「TRENDY:流行かぶれの、流行の先端を行く」という意味であ る。「売れる/流行る」などの要因は、多分に多くの要素が絡み合っている と考えられる。以下の図(図4)は、この〔T.R.E.N.D.Y.〕という語に着目しつつ、そのさまざまな側面について触れたものである。
T | Theme | 主題としてのアフェクション |
| 物語 | 結婚/恋愛/友情 | |
R | Regurar | 連続もの。一度みると次もみたくなるのは人の心 |
| 円環 | 時間の強調 | |
E | Eco | 見ることに意義がある。問題は次の日の会話 |
| 振幅 | 付和雷同と作為の流行 | |
N | Network | プロモーションとメディアミックス |
| メディア | 放送の商品化 | |
D | Distinction | 俳優が好き |
| 権威 | 名前に記号 | |
Y | Yourself | 鏡よ鏡、最も美しいのは誰 |
| 鏡像 | それは石田ゆり子に似ている私かしら |
T:THEME(テーマ性)は、ドラマの物語の放つ刺激の要素である。こうしたテーマは「受け手」の現実というコンテクストに引き入れられ、視聴者の反応を形作る。テレビドラマのテーマの一つに貫徹しているのは〔AFFECTION=愛〕である。この内容については論の後半の構造分析の際により詳しく論ずるので参照してほしい。
R:REGULAR(連続性)は、視聴者の心理が「見る、見ない」の選択に影響する生活様式の一つである。また、個人の嗜好や気分など、連続性にまつわる要因はさまざまである。生活様式であれば、社会的な背景や状態も反映するであろう。むろん、社会・集団の心理は、個人の気分にも反映しているはずである。
ドラマの放映と時間の関係から、生活者としての視聴者の時間意識について考えることは非常に重要だ。現在の区切られた時間の連続性に基づいた生活が、社会様式を見る標識になるからである。テレビを「見る、見ない」とは実に生活様式そのものなのである。
区切られた時間の連続性はどこに起因するのであろうか。例をあげれば、ミクロなレヴェルにおいて時計の針、マクロなレヴェルでの生と死の間、その中間にあたるカレンダ-などなどが上げられようか。さらに私たちは「メディアの場」というものをしばしばこうした時間測定の道具にしている。テレビに内在する時間の細分化と流され続ける電波。15秒きっちりに収まったCM、現実のカットアップである映像も細切れになり次々と姿を変えて続いていく。テレビを見ることは時間を忘れさせる娯楽ではない。それは意識させ身動きを取れなくする。新聞のテレビ欄を見てみよう。ここには固定され動けなくなった死の時間が表されている。時間のレールに乗せられた人々が連続物のドラマを見続けること。同じ駅から同じ駅へのトランスの連続。それこそがメディアの場に見られる生活様式である。メディアの内も、メディアの外も、である。名だけの時間移動、移動に伴う目的の消滅。流行現象とは移ろいやすい生活様式の場そのものなのである。
E:ECHO(反響性)。社会が流行を規定する。よく言われることである。しかし、同じようによくあることは、その流行が社会を規定し始めるといった倒錯現象である。もはやだれもどちらが真実なのか分からな いまま人々はテレビのスイッチをいれるしかないのである。
N:NETWORK(伝導性)。音楽や雑誌などとのタイアップによるブロックバスタ-型宣伝を、ドラマのメディア戦略がどのように利用したか、そしてどのような効果があったか・・これは前半の中心的論議であるので後述することにしよう。
D:DISTINCTION(卓越性)。ドラマは商品であり、その価値の受け入れられ方は多様化している。中心にあるストーリーだけ見られているわけではない。あらゆる周縁がドラマの価値に転嫁される。現実との差異化が生む「ゆらぎ」は、ドラマのあらゆる映像・感動から引き出される。
DISTINCTIONの意味は「差異」「卓越化」「栄誉」などである。コミュニケーションとは「差異化」の結果という側面がある。同時に「卓越化」という利害的な目的を持っている場合もある。マス・コミュニケーションの場合、こうした傾向はますます強くなる。
Y:YOURSELF(潜在性)。鏡の中の想像の世界と、現実の二項対立は、現実が切り取られシミュレートされメディアに乗った時、それは潜在的な現実として想像と同化する。私たちはテレビにヴァーチャルな自画像を見ることになる。鏡に移る自分の像=メディアの像は、像でしかないと分かっていても、自分自身の認識体系の表出=現実となる。それは、鏡を見たい気持ちである。それが、テレビを見たい気持ちである。
以上、「T.R.E.N.D.Y.」というというキーワードから、「テーマ性/連続性/反響性/伝導性/卓越性/潜在性」という語を浮かび上がらせ、トレンディドラマの人気・流行の原因を考察した。やや観念的ではあるが、これはなにもトレンディドラマだけにあてはまることではないと確信している。「T.R.E.N.D.Y.」な時代が終わった後も、メディアに関わる流行現象には、全般的に適用できるものと信じている。
第3章 トランディドラマの主題歌分析にみる
メディアミックスとブロックバスター
テレビドラマを見ること、つまりはメディアに触れることは、放送を商品性をふまえれば消費の一形態である。しかし、それは間接的な消費であり、「テレビショッピング」などを見ている場合以外には、実際にテレビを前に財布を開くことはない。 視聴率のようなデータが、ある種の市場を指し示すことはあるが、消費者が直接、貨幣と等価交換できる場を創出するまでには、かなりの段階を経ることを要する。
ここでドラマの主題歌について考えてみよう。ドラマ主題歌の消費現象を分析することは、ドラマという放送の流通機構を分析することにもなるであろう。その理由は既に述べた。
音楽の機能として生活の表象というものがあった。では、生活のシミュレーションであるテレビドラマを、主題歌が象徴的に表現しているのだとすれば、主題歌のヒット現象をドラマのヒット現象の象徴として考えることもできよう。CMソングの研究事例を振り返れば、音楽と映像が相互に売り上げを補完している過程がよく分かる。広告のメッセージを音楽に意味として託し、あるいは音楽の持つテクストを広告の表現にシフトした方法は、一種のマーケティングであり、この方法はテレビドラマに関しても応用可能であろう。
主題歌とテレビドラマの相互利益関係をつくり出すこの方法を「音楽マーケティング」と呼ぶことにしよう。「音楽マーケティング」という言葉は既に使われつつある言葉であるが、これまでテレビドラマと主題歌の関係には言及されてきていないように思われる。マーケティングとは「個人と組織の満足させる交換を想像するために、アイデア、財、サービスの概念形成、価格、プロモ-ション、流通を計画・実行する過程である」(AMA アメリカマ-ケティング協会)とある。つまり顧客満足と企業利益の同時進行のための方法論といえる。マーケティングの定義をふまえた上で、テレビドラマと主題歌の関係に注目してみたい。
「テレビドラマ、主題歌、視聴」の3者に関わるル-プに着目してみよう。二つの重なりあいがみえると思われる。1つ目の重なりは主題歌を含むテレビドラマ全体/視聴者である。これはテレビドラマを商品、あるいは財と考えるなら「テレビ局/視聴者」と考えられいわゆるマーケティングの概念に合致する。2つめの重なりはドラマ/主題歌の図式だ。売上を満足とするなら「ドラマ/主題歌=企業/顧客」、あるいはその逆としても考えられる。2つ目の重なりはいわばマーケティングという語から図式的に導き出したものであるが、この2つのル-プの絡み合いを「音楽マ-ケティング」と、ここではいったん定義しておきたい。
ではいかにして「音楽マーケティング」を成功させたのか。本稿のタイトルでもある現代社会のなかでのメディアの位置づけを明らかにしていきたい。
第一に、テレビドラマと主題歌の流行現象について、「うた/テレビ」という二つのメディアの関連から考察し、現象の原因について考察する。
第二に、主題歌がテレビドラマの象徴としての役割を実際に果たしているのか、ドラマは音楽をいかにしてイメージづけたかという観点から、主題歌の流行現象の原因を考察する。
第1節 主題歌の流行現象について
まず第一に、「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」はどのような人に視聴されていたのか、データで示してみよう。図5-1/5-2は「東京ラブストーリー」と「101回目のプロポーズ」の年齢別・男女別の個人視聴率である。
図5-1
| 年齢層 | 4-12 | 13-19 | 20-34 | 35-49 | 50- | |||
| 男女 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 視聴率 | 10.70% | 30.40% | 20.20% | 30.00% | 8.20% | 15.30% | 4.20% | 5.10% |
図5-2
| 年齢層 | 4-12 | 13-19 | 20-34 | 35-49 | 50- | |||
| 男女 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 視聴率 | 12.50% | 28.80% | 15.7% | 29.60% | 7.50% | 18.90% | 4.10% | 7.20% |
このデータから視聴者の年齢や性別によるおおまかな集団分類ができる。
データが示すように、両テレビドラマの最も中心となった視聴者層は、13-19才(これは男女分類がなく、ティーンという範囲だろうか)と、30-34才の女性であり、30%近くとかなり高い視聴率である。
年齢層が高くなるにつれ、男性よりも女性のほうが多く視聴しているようである。
全体的な傾向として視聴率は高く、これは放送期間中はおおむね「人気がある」と言われてきたことからも理解できる。両テレビドラマは明らかに流行現象であったと言ってよいであろう。
テレビ視聴者は、現実において何らかの形と程度において、関心・信念・年齢などの心理学的要因や人口統計学的要因の先有傾向を共通に持つ集団に所属している。放送という商品は、このような集団、つまり商品のターゲットとなるマーケットに対して、メッセージとして届けられている。先有傾向による諸処の要因によって、振り分けられた小集団にこのようなメッセージが届いたとき、その反応は集団によって異なる。しかし、違いこそあれ、流行現象とはマス・メディアによる囲い込み、つまり小集団の差異を内包しながらも拡散・拡大し、その差異を雲散夢消しながら巨大化していく集団の形成なのである。
次に、主題歌が流行するという現象を、テレビドラマの人気との関係から考察してみたい。
図6-1は「東京ラブスト-リ-」の世帯視聴率の伸びと「ラブスト-リ-は突然に」の売上の伸びを、図6-2は「101回目のプロポ-ズ」の視聴率の伸びと「SAY YES」の売上の伸びを示している。横には各数表を示してある。 図6-1 「東京ラブスト-リ-」の視聴率と「ラブスト-リ-は突然に」の売上
|
|
図6-2 「101回目のプロポ-ズ」の視聴率と「SAY YES」の売上
まず視聴率であるが、両テレビドラマともに盛り上がりをみせ、最終回に近づくにつれて、視聴率が右肩上がりに急上昇していることが分かる。
ドラマ主題歌も発売から同様に売上を伸ばしている。
特に総売り上げの伸び率を棒グラフにすると、「ラブスト-リ-は突然に」の最初の三週間の売り上げの伸び率が、「ラブスト-リ-は突然に」の最後の三週間の放送の視聴率の伸び率とほぼ平行しており、主題歌の流行とテレビドラマの人気の関係が明瞭である。
また両主題歌ともに、テレビドラマの放映が終了した後は、右肩上がりの伸び率もやや横ばいへと変化していることが分かる。
数表には、主題歌売り上げの週順位が出ているが、テレビドラマ放送中は常に売り上げ1位を示しており、テレビドラマ放映中により顕著に売り上げが高いことが分かる。
注目したいのは、主題歌はドラマが盛り上がる放送の3~5回目まで、発売なされていないことである。つまり、放送が始まったころは、テレビでしか主題歌は聞けないわけである。視聴者がテレビで2度ほどしか流れない主題歌を、「別の場所で聞きたい」「何度も聞きたい」と思ったころに、狙いを定めてCDを発売するという販促方法があるようである。
CDの売上の伸びとドラマ視聴率の伸びは、見事にシンクロしていて、「囲い込み」の効果は容易に推測できるといえるだろう。
このように、主題歌の流行現象とは、テレビドラマの人気と相互作用的に生まれた現象であることが分かる。この相互作用のことをメディア戦略的には、一般に「タイアップ」と言う。そこで次にこの「タイアップ」という手法について分析しておきたい。
第2節 「タイアップ」というブロックバスター型メディア戦略
第二に、テレビドラマで主題歌を用いる「タイアップ」という手法の効果をある程度、把握しておきたいと思う。
図7は、1991年に発売されたシングルCDの売上上位100曲(オリジナル・コンフィデンス社調べ)を対象に、「タイアップ」先、つまり他のメディアでこれらの楽曲を使用しているかどうかを示したものである。
図7 1991年シングルレコード売り上げベスト100タイアップ先内訳(%)

オリジナルコンフィデンス調べ(オリコン年鑑 1992年)
コマーシャルが33%と最も多く、テレビドラマが「タイアップ」先の楽曲は21%となっている。「タイアップ」のないものは27で%ある。つまり、70%以上は何らかの形で映像メディアと「タイアップ」していることが分かる。ここから楽曲のヒットや流行に、映像メディアがいかに大きな役割を果たしているかが理解できる。「タイアップ」とは現在、最も強力な流行現象の原因となっているようである。
すでに第二章で触れたが、広告音楽の目的はイメ-ジづけと販売促進であった。主題歌はドラマという商品をイメ-ジづけ販売促進(この場合、テレビの商品性を計ることができる視聴率のアップ)するためのものだと考えられる。さらに主題歌はドラマがあってこそ意味付けが行われるという二重性を持っている。音楽イメージにより、「モノに対する共通感覚的なイメ-ジ」形成が見られ、そのイメ-ジによる集団形成がある。
「モノに対する共通感覚的なイメージ」といっても分かりづらいので、CM音楽を例にとって、説明したい。
図8は、1991年のシングルレコード売上トップ100のうち、広告CMとタイアップしていた曲の、広告内容内訳である。
オリジナルコンフィデンス(オリコン年鑑)
図8 タイアップ曲の広告内容内訳(%) 自動車 5 宝飾品 11 化粧品 11 音響機器 19 食料品 24 企業広告 22 旅行など 8
「食料品」のCMが多いが、そのなかの小分類内訳では「飲料関係」が多い傾向が見らている。特に「酒・アルコール」が多い傾向であった。アルコールという嗜好品として付加された価値が商品のものが、音楽でイメージ付けされているわけである。
音響機器は、イメージが直接、音楽である。
企業広告も、広告の性質じたいが、イメ-ジ付けの性質を帯びていて、音楽が適当な媒体となったようである。
このデータは、数値よりもその内容内訳が重要だ。というのも広告全体の量とは比較していないからだ。このように「モノに対する共通感覚的なイメージ」とは、「機能と価値の間」を「埋める」ものとなっているようである。
図9は、1991年のシングルレコード売上数ベスト10の「19911年通算売上数」「タイアップ先」「オリコン誌に初登場した時の、売上数と順位」を表している。
図9 1991年 CD年間売上トップ10
この表から次のようなことが分かる。
1、「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」の売上が、他を引き離して抜群に高いことである。10位のB'Zの売上数の4倍近くである。
2、「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」は、初登場時の売上数が、他と比較にならないほど多いことが分かる。「ラブストーリーは突然に」が、発売した週に売れた数は、Dreams Come Trueが1年かけて売った数より多いのである。
3、タイアップ先がドラマの曲のほうが、タイアップ先がCMやバラエティー番組より、初登場時の売上数が比較的高めである。そのほとんどのテレビドラマはフジテレビで放映されている。ちなみにタイアップ先のない曲の最高順位は、米米クラブの27位が最高となっている。
以上のことから、ドラマの主題歌が、非常に特徴的な売上スタイルを示すことが分かる。明らかにテレビドラマと関連があるようである。そして、その中でも「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」はにその傾向が顕著である。「イメージ」というものをメディア戦略に組み込んでいった結果、こうした現象が生まれてきたのである。
第3節 主題歌と象徴
Resolution CMソング、イメ-ジソングがCMの持つメッセ-ジや広告意図を内包して伝達されたように、ドラマの主題歌もドラマの内容を持ち合わせていたのだろうか。まずは歌詞の世界を分析して、テレビドラマと主題歌の関連を見ていきたい。
Acknowledgement
Pursuance
Psalm
John Coltrane 「Love Supreme」
(1)「ラブストーリーは突然に」の歌詞の内容分析
~歌詞 右参照~
「ラブストーリーは突然に」
何から伝えればいいのか
分からないまま時は流れて
浮かんでは 消えていく
ありふれた言葉だけ
君があんまり素敵だから
ただ素直に好きと言えないで
たぶんもうすぐ 雨も止んで
二人 黄昏
あの日 あの時 あの場所で
君に逢えなかったら
僕らはいつまでも
見知らぬ二人のまま
誰かが甘く誘う言葉に
もう心揺れたりしないで
せつないけど そんなふうに
心はしばれない
明日になれな君もきっと
今よりもっと好きになる
その統べてが 僕の中で
時を 越えていく
君のために 翼になる 君を守り続ける
柔らかく 君をつつむ
あの 風になる
あの日 あの時 あの場所で
君に逢えなかったら
僕らはいつまでも
見知らぬ二人のまま
今 君の心が 動いた
言葉 止めて 肩を よせて
僕は 忘れない この日を
君を誰にも渡さない
誰かが甘く誘う言葉に
もう心揺れたりしないで
君を包む あの 風になる
「主体」は〔僕〕、「客体」は〔君〕である。
〔僕〕は〔あの日・あの時・あの場所〕で〔君〕と〔逢え〕る。
〔逢えなかったら見知らぬ二人のまま〕という逆説から「出会い」の強調が示されている。
出会いの次の段階として「意思の伝達」が提示されている。
〔僕〕は〔君〕が〔好き〕なのだが、〔君があんまり素敵〕なのを理由に〔ありふれた言葉〕に〔時は流れて〕〔伝え〕られない。
〔二人黄昏〕という言葉から実は〔君〕である人も〔僕〕を好きであると思われる。
〔誰かが甘く誘う言葉〕は恋愛における「事件」の表象だ。
〔もう〕という言葉から「事件」の実在性を確認できる。
〔明日になれば~越えていく〕は恋愛という物語の「連続する時間性」のあらわれである。
〔時を越え〕ることにより〔僕〕は「愛」を手に入れる。
〔そのすべて〕とは〔君〕が〔僕〕を愛する心であって、歌詞全体における〔時〕を意味するものはここで〔僕〕の「愛」の象徴として定義されている。
〔君のために~風になる〕は〔僕〕の「愛の行為」である。
〔翼〕と〔風〕が事件に関する「嫉妬」〔切ない・心は縛れない〕の対局にある自由を表して愛の「成就」を示す。
これまで「愛」の変形であった〔言葉〕を〔止めて〕、「愛」の形は〔肩をよせて〕といった「肉体」の関係に移り変わっていく。
最終的に〔僕〕は〔君を誰にも渡さない〕という宣言のもとに「愛」の「永続性」を宣言する。
〔この日〕を忘れないことは「時間=愛」という形式の確認であり〔心 揺れたりしないで〕と愛を乱す新たな事件が起きないように祈り、終わる。
「ラブストリ-は突然に」というタイトル自体もそうであるが、歌詞の内容は「出会い→伝達→事件→迷い→成就→不安と歓喜」というような構造を持つ恋愛物語である。
(2)「SAY YES」の歌詞の内容分析
~歌詞右参照
「SAY YES」
余計な ものなどないよね
全てが君と僕との
愛の構えさ
少しぐらいの 嘘やわがままも
まるで僕を 試すような
恋人の フレーズになる
このまま二人で
夢をそろえて
何気なく
暮らさないか
愛には愛で 感じ合おうよ
ガラスケースに並ばないように
何度も言うよ 残さずいうよ
君が溢れてる
言葉は心を越えない
とても伝えたがるけど
心に勝てない
君に会いたくて 会えなくて 寂しい夜
恋人の 刹那さ知った
このまま二人で
朝を迎えて
いつまでも
暮らさないか
愛には愛で 感じ合おうよ
恋の手触り 消えないように
何度も言うよ 君は確かに
僕を愛してる
迷わずに
SAY YES
迷わずに
登場人物の「主体」が〔僕〕、「誘惑」される側が〔君〕である。
時間、情景、登場人物に関する情報提供子は一切示されない(〔恋人〕であること以外)。
さらに歌詞は、段落で区切られた単位により、それ自体で意味をなす機能体として存在しつつも、その前後の文脈の相関関係はほとんどみられない。
一つの文脈はそれ自体で完結していて閉じた構造を持っている。
さらに物語としての始まりと終わりがない。
存在するのは登場人物の意識・感情のみである。
そして、分布的で意味提示的な文脈の羅列に生成される物語のテ-マは「愛」である。
〔余計なもの〕は〔無〕く〔すべて〕が「愛」である。
〔少しぐらいの嘘やわがまま〕も「愛」であり、〔愛〕が〔僕〕を〔試す〕(=試練)という認識も〔愛の構え〕の一つである。
〔このまま~暮らさないか〕は〔僕〕の「愛」の認識の一つとして提示される。
〔僕〕にとって〔暮ら〕すことは〔愛で感じあう〕方法である。
「愛情と伝達」の欲求は、〔逢いたくて〕=「愛情の欲求」、〔とても伝えたがるけど〕=「伝達の欲求」のように示され、〔逢えない〕〔心に勝てない〕というように「抑圧」されている。そして(知る)のは〔切なさ〕である。
〔僕〕は〔君〕に対して「愛」を与えかつ求めるという立場にある。
さらに〔言葉〕〔逢う〕の二つが「愛」の認識として意味されること分かる。
最後に〔SAY YES〕という語りかけで終わっているが、〔YES〕は与えられた〔愛〕への「解答」の形態として示されている。
「SAY YES」には「ラブストリ-は突然に」のように明示的な構造を持つ「物語」ではない。「言語的なもの」をその指し示すものを用いずに提示したものである。「愛の欲求」がそれである。詩は要約できないとよく言われるが「SAY YES」は要約できないのである。
(3)「SAY YES」と「ラブストリ-は突然に」の共通性
二つの歌詞に共通することは、場所・登場人物・時間を具体的に示した言葉が示されていないことである。
ただ〔僕・君〕〔あの日・あの場所〕というように、抽象的で非明示的にのみみられる(SAY YESに関しては抽象的にも示されてない)。
また〔僕・君〕という「主体」には「男女」というジェンダーに関する設定はなされていない。歌詞の中で「主体」と「客体」の入れ代わりは見られず、「愛」の「送り手」は常に〔僕〕で「受け手」は〔君〕である。
場所や時間の限定もないので、歌詞は「万人に共通にあてはめられる可能性をもつテクスト」なのである。つまり〔僕〕に男性を、あるいは女性を代入してもそれを遮るような具体的記述はないので、意味の成立においては特に差し支えがない。共通なテ-マである〔愛〕は人間の基本的な社会的・心理的欲求でもあり、そのテ-マ性を訴えられる範囲は極めて広範である。
ドラマのテ-マは既に示した通り「AFFECTION」である。論の後半では、その内容をドラマのほうから詳しく見ていくことにするが、主題歌の歌詞内容のテーマはテレビドラマのテ-マ性に沿ったものであるといえる。実際、「東京ラブストーリー」のセリフには、主題歌の歌詞と全く同じ言葉が見られた場合もある。
「SAY YES」での〔暮らす〕ことは結婚を表しているといえ、この点も「101回目のプロポーズ」の内容に対応している。
「ラブストーリーは突然に」と「SAY YES」の違いについても見ておきたい。「東京ラブストーリー」においては「ラブストーリーは突然に」がその構造を示しており明示的に指し示す対象を持つのにに対し、「101回目のプロポーズ」では「SAY YES」は内容の象徴であり、ストーリーの潜在的な意味内容の提示である。
換言すれば、「ラブストーリーは突然に」が「物語というモノ」の提示をするに対し、「SAY YES」が「愛という物語のもつコンセプト・イメージ」を提示するというように考えられる。この違いと役割から、主題歌はある種の広告音楽的である。広告音楽の歴史からも見てきたように、メロディーに商品名の連呼といったごく初期的な広告音楽の形態に「ラブストーリーは突然に」が当てはまる。この場合の商品は「テレビドラマ」である。商品-モノは曲名や歌詞になり、放送によって露出され繰り返され、曲とモノを連結する。それに対して「SAY YES」の場合は、提示するものは商品としてのドラマのコンセプト、つまり生活様式であり生活感覚であった。この点でイメージソング的なのである。
主題歌の言語的メッセ-ジは、音楽的メッセージと一体化し、言語的メッセージは歌詞として、ドラマの内容を彷彿させドラマの印象をイメージ付ける。一方、音楽的メッセージは、恋の生活様式とあこがれを印象として提示している。これら言語的メッセージと音楽的メッセージによって植えつけられたイメージを持つモノは,それ自体メッセ-ジ性をもつドラマであり、「機能と価値の間」を「往復」しながら、イメージとモノの間を彷徨うのである。
第4節 主題歌の音楽的テクスト
「テレビドラマの人気があったから」というだけの理由で、「ラブストーリーは突然に」「SAY YES」が売れたわけではなさそうである。歌自体にも流行現象となった原因があろう。
演奏するア-ティストの力も忘れられない。広告音楽は作られるイメージをアーティストに期待して、始めから売れるような、曲かア-ティストを使うことが多い。「ラブストーリ-は突然に」を歌う小田和正も「SAY YES」を歌うChage&Askaも事実「超」のつく売れっ子である。小田和正は、1970年代終わりから1980年初頭にかけて「オフコース」というバンドで大活躍したのち、1985年からソロ活動をしている。作詞・作曲・プロデューサー・アレンジャーとして多くの曲を手掛けるビッグアーティストだ。Chage&Askaは、1979年にデビューして以来、20枚もアルバムを出すベテランだ。Aska(飛鳥涼)は提供楽曲ヒットも多く、Chage(チャゲ)は最近にソロ活動も行う。売れるべくして売れたといっても過言でない。
音楽自体の雰囲気などはどうであったか。ごく主観的であるが、その感覚的共通点と特徴を上げておきたい。メロディーは切ない悲しさや不安を持ちつつ希望的であって決して暗くない。コード感、ハーモニーも同印象だ。アレンジは至極現代的であり機械仕掛けの人間的リズム、重厚かつ厭味のないストリングス、1991年のブームの一つだったAORリバイバル(1980年代初頭に流行した、大人の洗練された都会派ロック Adult Oriented Rock)の影響も見えるような曲に仕上がっている。コンテンポラリーなサウンドは実に聞きやすい。
第5節 主題歌の露出とイメージ付け
では、このような特徴を持つ主題歌が、どのようにテレビドラマのなかで用いられ、そしてどのようにイメージ付けをしていったのか、考察をしていきたい。
テレビドラマ内での主題歌の露出について考えてみたい。主題歌はテレビドラマの番組中に何度となく流れる。図10-1は「ラブストーリーは突然に」、図10-2は「SAY YES」がドラマ中のどこで何回流されたかを示している。
図10-1 「東京ラブストーリー」の主題歌の露出 放送回 放送日 放送タイトル シーンの概略 主題歌の曲調 第1回 1/7 出会いと再開 冒頭
赤名リカと永尾完治(カンチ)の出会い
三上が関口のキスシーンを目撃
フルコーラス
インスト
1番
第2回 1/4 愛ってやつは 冒頭
----------
----------
フルコーラス
インスト
1番
第3回 1/21 二人の始まり 冒頭
----------
----------
フルコーラス
インスト
1番
第4回 1/28 君の翼になる 冒頭
----------
----------
フルコーラス
インスト
1番
第5回 2/4 いつも思い出して 冒頭
リカとカンチのデート
三上を待つ関口、カンチに電話
関口と会ったカンチ、リカの前で仕事と嘘を。怒るリカが家を出る
フルコーラス
インスト
インスト(マイナー調)
フルコーラス
第6回 2/11 赤い糸に結ばれて 冒頭
----------
----------
----------
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
第7回 2/18 愛は待たない 冒頭
----------
----------
リカの買った愛媛行きの切符を見つけたカンチ、感動して抱き合う
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
第8回 2/25 この恋を信じたい 冒頭
----------
----------
カンチとうまくいかないリカ、和賀と公演で相談
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
第9回 3/4 行かないで 冒頭
----------
カンチがリカに「俺なんてよせよ」と突き放す
カンチがリカに会いに行こうとするのを、関口が「行かないで」
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
フルコーラス
第10回 3/11 約束 冒頭
----------
----------
----------
----------
愛媛のカンチの母校、カンチの落書きにリカの名前が
フルコーラス
インスト
インスト
インスト
インスト
フルコーラス
最終回 3/18 さよなら 冒頭
----------
----------
3年後、偶然リカと出会うカンチ、少し話をして別れる
フルコーラス
インスト
インスト
フルコーラス
図10-2 「101回目のプロポーズ」の主題歌の露出 放送回 放送日 放送タイトル シーンの概略 主題歌の曲調 第1回 7/1 運命のお見合い 冒頭
知恵が達郎に、薫が昔受けたプロポーズの言葉を教える
達郎、練習場に乗り込み、教わったセリフを叫ぶ
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第2回 7/8 一生に一度の賭け 冒頭
薫、コンサートチケットを達郎に渡す
ボーナスを競馬に注ぎ込んで、薫に見せに来る
競馬ははずれ。薫は感動するが「好きにはならない」
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
インスト
第3回 7/15 僕が幸せにします 冒頭
薫の誤解を解く
公園で達郎と薫が会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
第4回 7/22 愛が動くとき 冒頭
達郎と薫の部屋の描写
達郎、薫の親と食事
薫、達郎が薫の父親の説得したことへ礼を言う
達郎は、静岡に帰った薫を迎えに行くフルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第5回 7/29 愛のない結婚できますか 冒頭
結婚について話す各登場人物
達郎と薫のデート
達郎と薫の食事
達郎、以前の婚約者にばったり会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト+コーラス
インスト
フルコーラス(フェイドイン/二番のみ)
第6回 8/5 婚約 冒頭
回想シーン
薫、達郎が好きであることを告げるが..
トラックに突っ込む達郎、「僕は死にません、あなたを幸せにします」
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第7回 8/12 まさかあの人が 冒頭
婚約を発表、薫は知恵に、達郎は純平に
達郎、真壁の墓参りに行く
達郎と薫の婚約パーティ
薫、真壁とそっくりの人物と出会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第8回 8/19 悲しき婚約指輪 冒頭
達郎、薫に無理矢理婚約指輪をはめようとする
薫、藤井の家で抱き合う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第9回 8/26 婚約者を取り戻せ 冒頭
達郎、薫の父親と酒を飲む
薫、藤井と以前結婚するはずだった場所へ
達郎は、桃子に過去の薫の結婚式場を教わり、向かう
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第10回 9/2 僕はあきらめない 冒頭
薫のさよなら宣言
あぜんとして、何も手に付かない達郎
達郎、薫の前で弁護士になると宣言。あきらめない。
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
第11回 9/9 愛の女神よ 冒頭
試験勉強をする達郎1
試験勉強をする達郎2
試験勉強をする達郎3
達郎と薫、いつものバーで久々に会う
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
最終回 9/16 SAY YES 冒頭
過去の回想
留守の達郎にお守りを届ける薫
薫、コンサート途中に立ち上がり、教会へ
試験に落ちた達郎
薫、夜の街をウェディングドレスを着て駆けてくる
フルコーラス(二番のみ)
インスト
インスト
フルコーラス(二番のみ)
インスト
フルコーラス(二番のみ)
上記の表のように、主題歌がある特定の場面で露出していることがわかる。
まず、冒頭で俳優やキャストの紹介とともに「ラブストーリーは突然に」は全曲、「SAY YES」は2番から流れる。冒頭での露出により、この2曲が主題歌であり、テーマ曲であることが示される。
ドラマの中では、それぞれの曲が、歌なしのインストロメンタルになって、特定の場面で流れる。「東京ラブストーリー」は永尾完治と赤名リカの心情と行動描写中心の展開であるが、二人に心情や行動の変化に合わせて「ラブストーリーは突然に」が明るい調子になったり、静かな調子になったり、あるいはマイナー調のやや暗い感じになって流される。
私たちがドラマを見るという行為は、ある意味でドラマの中に自分を置き、あるいは自分の中にドラマを引き寄せ、その中の世界を生きることによって、展開する物語を再構造化し、その世界を認識することである。しかし、主題歌は、ある特定の場面が、その物語における鍵となり、感情想起のトリガーとなることを、さりげなく視聴者に示している。「東京ラブストーリー」では「シーンの概略」データが抜けてしまっていることが多いが、こうした視聴行動に一定の指針を与えているのである。
このインストロメンタルは、冒頭と異なり、「いかにも主題歌」というような主張はしない。よって、その存在は希薄であると言ってよい。しかし、データからも分かるようにそのインストは、一回の放送で、少なくとも2回、多いときは4回は流れている。
着目すべき点は、放送期間が後であった「101回目のプロポーズ」のほうが、インストロメンタルの曲をより多く使っている点である。
「SAY YES」がイメージ的な歌詞内容を持つことから、効果的に感情想起の道具となっていることがあげられよう。「SAY YES」がインストとして流された場面を見てみると、「達郎」が主体のときと「薫」が主体のときと、比較的に均等にインストロメンタルが流されている。また、主体が複数あるような描写の場合にも同様に用いられている。つまり、「求める/拒む」というストーリーの主体の位置付けによらず、「SAY YES」はその「愛の欲求」というテーマを刷り込んでいるのである。
また、これは「シングルCD」の販売日時や売り上げと関係していると思われる。実はテレビドラマの第5回の放送までは、両テレビドラマの主題歌ともに、発売がされていないのである。つまり、市場との関わりである。
歌ありのフルコーラスが必ず一回はストーリー中に流される。両テレビドラマとも54分、11-12週にわたって放映されたが、それぞれ一話づつが、必ずある種の物語として完結している設定になっている。そして、それぞれにクライマックスがある。図5-1/5-2には簡単にそのクライマックスシ-ンが書かれている。制作上は実に巧妙で「ハッ」とするシ-ンに、うまく曲の「アタック」を乗せている。例えば、ドアを閉めた瞬間であったり、恋敵とのキスシーンであったり、である。ストーリー中のフルコーラスの露出度はドラマが盛り上がるにつれて多くなっている。
「SAY YES」を音楽的に分析すると、イントロの第一音、つまり曲の始まる瞬間に、各楽器が一斉に音を伸ばしている「アタック」がある。俗っぽく言えば「ガ~~ン」というような感情のような音である。その後に、やや静かになり、鐘の音のような静かに、しかし重く鳴り響くような音でメロディーを奏でる。このアタックと静寂が、登場人物の心境のいわば「ショック」と「無力感」のようなものを表現している。
「ラブストーリーは突然に」も同様に、曲の始まる瞬間は、ギターだけが勢いよくコードを弾く部分がある。カッティングと呼ばれる奏法のこの音が、クライマックスシ-ンの一瞬の静寂を破り、その後に走るような勢いのある曲調へと進行する。
いずれにせよ、非常に巧妙な演出なのである。
このように、露出度の高さと強力なインパクトを与えることによる、効果的な曲の利用によって、主題歌がドラマに映像では与えられない「何か」をあたえる。一方ドラマが主題歌のイメ-ジングを行い、つまり音楽に人格を与えて、視聴者に送りだす。テレビドラマが主題歌に与えたイメ-ジは「愛と感動」である。そして視聴者は「愛と感動」といった人格を持った音楽に、意識的にも無意識的にも、何度も触れることになる。
視聴者は、自らの経験から、主題歌を愛の歌と認識するのを止め、ドラマに触れるという非現実表象が提示する経験から、主題歌を愛の歌であると認識しはじめることになる。ここには、なにも出会い→告白→成就といった図式や結婚形態だけが愛ではないことや、「ラブストーリーは突然に」は愛の歌ではないかもしれないことは、ストーリーテラーの関心外である。テクストは既に作動しているのである。
第6節 主題歌の流行という現象と原因
レコードが売れているってことよりも、ようやく僕等のイメージが変わってきたんだな、という感じのほうが強いですね
Chage&ASKA 「FM fun」誌インタビュ-より
これまで説明してきたように、テレビドラマは「若者・愛」という要因でマーケットの囲い込みをした。楽曲との関連でいえば「囲いこんだ集団に音楽に興味をもつ集団を含んでいた」ということと、「音楽に注目している集団にもドラマに注目させ囲いこんだ」という二つの事象を説明できよう。
「SAY YES」「ラブストーリ-は突然に」はこの様に作りだされた、あまりにも漠然としていながら差異を内に含む巨大なマ-ケットの創出によってあのようなセ-ルスが可能となったといえよう。
さきほど歌詞の分析をしたように二つの主題歌は、主体に制限のない構造や、内容の単位においての抽象性を持ち合わせていた。この主題歌は、視聴者がテレビドラマにチャンネルを回したとき(これはリスナーが心に組み込んで物語る以前の段階において)意味とテレビドラマのコンテクストを与えられる。主題歌はドラマを記号化したものである。
歌詞の内容分析でみたきたように、歌詞というメッセージのなかで、物語は完成しておらず、消費者の参加(意味的に、あるいは、ドラマを見て主題歌を聞いて、CDを買って.......)をもってその物語は完成を見るのである。リスナ-が、自分の経験なり心情なりをこの2つの歌に代入し、それぞれ各人の物語を作りだすこと。歌はこうしたテクストの作用から耳にした者を逃さない。それは参加・想像・創作への消費者満足でもある。マーケッターからみれば、複雑な社会心理を持つ(「感性」とか言われるもの)消費者群に対し、抽象的な枠(この場合歌詞のテクスト)を提示することによって、後の市場参加を消費者が意味を顕在化していく過程に任せればいいわけである。この市場が成立するか否かは、いかに消費者が「語りたがっている」物語テクストを示すかである。前章で示した流行の「T.R.E.N.D.Y.」モデルは、このような「音楽マーケット」の心理的創出でもある。
主題歌のテーマである〔愛〕は人間にとって普遍的なテーマであって、決して一時的な流行ではない。人間に必要不可欠な〔愛〕のテクストの提示は、消費者ニ-ズを巻き込んみ、しっかりと掴んだ商品となった。
主題歌は、音楽CDとして流通することによって「一人歩き現象」が見られよう。ドラマの主題歌はドラマの枠を飛び出し、一つの音楽としてリスナーに聞かれるようになるのである。各種の音楽メディアに乗って、より多くのリスナ-に聞かれるようになる。もはやドラマの視聴者だけが「主題歌」とフレーム付けられた音楽に触れるのではない。
音楽自体の解説で触れたように、コンテンポラリ-な2曲はより多くの音楽ファンにアピールした。このことはドラマという商品がターゲットとしたマーケットを、大幅に拡大した。つまり、ドラマのファン以外である音楽ファン層を、ドラマに注目させる可能性が出てきたといえよう。テレビドラマは、その強烈なイメージングにより、市場を形成し拡大する。一方、主題歌はテレビドラマのマーケットを形成し拡大する(右図 参照)。
広告音楽が必ずしもリスナー全体に効果があるとは考えず、音楽的共通認識のもとにある、集団を作りだし、効果の可能性を集団に対して求めているように、ドラマの主題歌も効果の可能性を求めたものである。しかしその対象とする、あるいは作ろうとする共通認識の集団=マーケットは、イメージの世界と相互作用しながら、二重・三重に広がる広範なものである。
第4章 ドラマ・現実・虚構
第1節 トレンディドラマのシミュラークル性
偽物を本物から区別したり、実在をその人為的復活から区分する最後の審判も存在しない。なぜならすべては、すでに死に絶え、前もって蘇っているからだ本論後半の第4章から第6章では、トレンディドラマの内容分析を行い、こうした内容の現代的意味を明らかにすると同時に、視聴者である「受け手」がいかなる様式のメディア・コミュニケーションに対峙するのかに着目する。これまでの章では、トレンディードラマに関わる現象が「いかにして生じてきたか」「いかにして現にそのように存在したのか」ということを論じてきた。次には、その現象が持つ「私たちへの関係=機能」を論じようと思う。
J・ボ-ドリヤ-ル 「シミュレ-ションとシミュラ-クル」より
こうした「機能」を考察するとき、ドラマ試聴を通じた「現実」と「虚構」の交錯に着目しておきたい。テレビドラマとは既に定義したように「虚構」にほかならない。それは「現実」にはどこにも在りえなかった世界であり、テレビの窓の中において以外では決して触れることのできないものである。作られた物語であり演劇である。視聴者がその世界とコミュニケートすること、言い換えれば、ドラマの世界と相互に作用しあうことはありえない。
しかし、テレビが作りだす世界は視覚的素材が「現実」の「モノ」である。認識ができる「現在」であって、存在する「モノ」が映し出されている。つまりドラマは私たち「人間」そして「社会」「生活」を素材とした「シミュレーション」として「現実的」であり、現実から構成された「虚構」である。
J・ボードリヤールは著書「シミュレーションとシミュラークル」において、画像が「シミュレーション」であることを指摘し、さらにそれが現実と対応関係を失った、「シミュレーションのシミュレーション」、つまり「対応すべき現実を失ったシミュレーション」=「シミュラークル」であると述べている。
このシミュラークルに着目して、テレビドラマのシミュラークル性について議論してみたい。テレビドラマの素材や場所は、明らかに「現実」のモノである。一方、俳優の演じる愛の物語や生活は、私たち個々人の「現実」生活とは無関係である。独自の物語であるか、他人の生活である。しかし、価値や規範において、それをあたかも最も維持すべき必要なものと訴えかけているように感じるものも少なくないのではないか。「現実」としての視覚映像は、それが物語であることを「忘れ」させる。マス・コミュニケ-ションであるから、メディアの映像の中の世界と「受け手」が容易にはアクセスできない。こうしたことから、視聴者は、テレビドラマを「現実」と類似したものとして自分の周囲・周辺と同視する。いわゆるテレビの環境造成機能である。ボードリヤール的に見れば、それは現実の「シミュレーション」であるテレビドラマの画像を「現実的」なものとして見ることである。テレビドラマという「シミュレーション」は「現実」という実在と照合される事がなくなるということである。
一方、テレビドラマは「現実」の現在の時代や欲望を「シミュレーション」として表現しているのであろうか。視聴者は、テレビドラマを見て、「現実」と照合せず、その「シミュラークル」の中でしか生きていないという、「虚構の現実化」をしているのであろうか。否である。
少なくとも、視聴者はテレビドラマを「虚構」として認識し、それが「現実」ではないことをよく知っているようである。例をあげてみよう。「東京ラブストーリー」の主人公である赤名リカのような勝手気ままな女性に、多大な魅力を感じる東京ラブストーリーの男性陣......日常会話で「なんか違う」という話はよく耳にしたものである。「101回目のプロポーズ」における浅野温子と武田鉄矢の結婚、ひたむきな愛の答えにウェディングドレスで夜の街を走る薫........例をあげればきりがないが、明らかに「現実」の行動としては考えられない部分が多い。トレンディードラマはいわゆる娯楽モノとして捉えられている。私たちがドラマをみて笑っている段階で、既にそれは「現実」性の否定であると考えてもいいだろう。
「101回目のプロポーズ」において、登場人物の設定では、武田鉄矢と江口洋介は兄弟である。放映中に江口が友人に「兄弟であることが信じられない」と指摘される場面があった。江口は「髪形が似ているだろ」「昔はもっと似ていたんだ」と答えている。これは一つのコメディ・シーンなのだが、このようなコメディ・シーンが用いられているのは、武田鉄矢が若いころは江口洋介のような髪形をしていたが、決して現実の兄弟ではなく、髪形だけが似ていて、その外見にギャップがあることが、おおむね視聴者に理解されているからである。
視聴者はテレビのスイッチを入れることで、フィクションの世界に入り込みながら、引っ張りこまれたままになることなく、ある距離を保っている。さらにテレビドラマの側からしばしば「非現実感」を助長して、視聴者を「現実」に押し戻す。上の例であれば、主人公と準主人の兄弟のコメディ・シーンが「非現実感」を助長して、二人が俳優であるという「現実」のバックグラウンドを呼び起こし、「現実」に押し戻しているのである。
つまり、ドラマはその「虚構性・非現実性」により、視聴者に「現実」をそして日常を強く意識させるものとなるのだ。「虚構」が「意識」させる「現実的」なもの。これこそボードリヤールのいう「シュミラークル」にほかならない。視聴者はテレビドラマの「虚構性・非現実性」を理解しているからこそ、その対極にある自らの「構成的な現実認識」を強くするのである。
テレビドラマは決して価値・規範を強制したり、視聴者をその枠の中に単純に組み入れたりはしない。その意味でテレビドラマの影響力とは、極めて限定的なものである。しかし、テレビドラマの「非現実性」に気付いている視聴者が、それを楽しむことそのものが、そして、その精神が「シュミラークル」を生み、見えない影響力というテレビドラマの機能がそこに果たされるのである。
既存の価値・規範を繰り返し強化して画一化して規格化していく「機械」。これこそドラマの持つ潜在的機能であり、権力構造である。ドゥルース&ガタリが論じるように、メディアの性質である「断片化や分離化」は機械的性格である。テレビドラマは視聴という文脈において、個々の経験と関心により断片化され、「現実と虚構」に「シミュラークル的」に分離されるのであろう。ドゥルース&ガタリは「機械」について、静的な構造から差異による一元的な結果を生む概念として、そして、動的な自己再生産の形式としてとらえている。こうした「断片化や分離化」は、テレビドラマをめぐる私達の「自動機械化」であり、メディアに触れる人の感情や意思が「規格化や統一」を生産する力になると同時に、メディアに触れることによる動き自体が力となっていくのである。
こうしたテレビメディアの持つ「機械」性を背景に、価値・規範や「知」そのものといった、私たちの拠り所としているものがテレビドラマによって「権力構造」に包括されていくのである。この場合の「権力」とは、フ-コ-が論じるように、「行使されたり利用されたりする力ではなく、人が接する関係自体」という概念である。また、「知」についてもフーコーが述べるように、「環境や物の見方、言語の表現などの在り方を支える認識の体系」を念頭においてある。
一般的なマス・コミュニケーション論によれば、「テレビでの認知は欲求の増大につながっても、直接の購買に結びつきにくい」ということは、これまでしばしば指摘されている。テレビドラマの場合はどうであろうか。テレビドラマの中の生活を見て、そのままの形で消費に転嫁することがあるだろうか。これは上に同じであろう。「虚構」をそのまま「現実」として、消費行動に結び付けることは少ないといえるだろう。
社会心理学的に考察するならば、欲求とその充足の過程をふまえる必要がある。消費行動を引き起こす動機の問題である。欲求とは「生活体の生理的あるいは心理的状態が、なにかの不足や過剰によって安定した均衡を失った状態」をさすとされている。そしてその不足を何らかの行動で足す、あるいは過剰を消し去ることで充足する。テレビドラマの場合で考えるなら、不足や過剰がドラマによって与えられたイメ-ジであろう。一つは「虚構」としてのイメージであり、もう一つが現実の価値・規範に照らされながらもドラマによって生み出された「シミュラークル」としてのイメ-ジである。
そのイメ-ジを「現実化」させること、つまり消費行動によってイメージを消し去る、つまりイメ-ジを消費することによって充足することになるはずであるが、それは直接的な行動では示されないことは既に述べた。では社会心理学的に考えると、テレビドラマの「シミュラークル性」とはどうとらえればよいのであろうか。そこで欲求の質をふまえて議論してみたい。人間の欲求には生理的欲求と社会的欲求がある。後者は人間自身の内で作りだせるものではない。後天的に学習されるものであって、外からの与えられたものだ。メディアによって明確なイメ-ジが与えられ続ける中、私たちの満足への指向は、与えられたイメージの「現実化」という間接的な意味での消費に向けられる。
私たちはテレビドラマに存在するモノの直接的な消費は行わなくとも、それを見ることで生み出された個人それぞれの価値・規範に影響されたイメ-ジを消費しているのである。そしてテレビドラマは無限に続く「シミュラークル」の円環によって、画一化・規格化された価値・規範を視聴者のなかで無限に生成し、確実に消費されるイメ-ジを生成しているのである。この「消費されるイメ-ジ」とは........あらゆる行為の根幹となる「意味」を生成することなのである。
第2節 トレンディドラマ分析の意義
「101回目のプロポーズ」と「東京ラブストーリー」を分析することによって明らかにしたいことはマス・メディア内容に関することだけではない。
しばしば内容分析という手法は、その意義が不明確であることが指摘されることが多い。一般的には、「いったいなぜこのようなことを行うのかが不明である」と言われることが多いように思う。また「内容分析の結果がどう生かされるのかが不明である」という意見も多いように思う。たしかに、メディアの効果や利用の形態が内容という変数と関連しているかどうか、実証的に明らかにしずらいという部分はあろう。こうした点で、禁欲的になっているという側面もあるのかもしれない。
しかし私は実証的な点については譲るにしても、内容分析を通じたメディアの総過程の分析にあえて挑戦してみたいと思う。しかし、その方法はいわゆるマス・コミュニケーション研究の手法に基づいたものではない。個々の方法については個々の分析の前に論じるつもりであるが、以下のように、分析の目的と方法を示しておこう。
分析の目的をまとめて言うなら、「冗談」や「趣味」「愛」「便利さ」「常識」といったような、私たちの生活に欠かせなくて、しかも、自らの意思で自由であると思っているものにある、隠された操作や支配の体系や、自らががんじがらめになっている枠のようなものを、見つけるということだ。
方法について言うなら、テレビドラマから、多くの事象に共通する上のような「権力の構造」を見つけていくために、構造主義や記号論、テクスト分析など方法を採用する。
ピアジェは構造について「定式化と変換の様式」と定義しており、レヴィ・ストロースは「要素と要素間の関係からなる全体であって、この関係は、一連の変換過程を通じて不変の特性を維持する」と言っているが、物語と視聴をめぐる空間を構造的にとらえることにより、なにが定式化されなにが変換されるのか、こうしたことについて明らかにしていきたい。
以下の章は「101回目のプロポーズ」と「東京ラブストーリー」の構造テクスト分析の試みである。「101回目のプロポーズ」の分析では、内容の要素を記号化することで、ドラマだけではない、メディア自体や試聴行為といったことに言及できるような「変換様式」を作る。いわゆる構造分析という方法を用いる。「東京ラブストーリー」では精神分析のな見方を中心に、メディア・テクストの分析を行う。
第5章 「101回目のプロポーズ」の構造テクスト分析
分析対象となるテレビドラマ「101回目のプロポーズ」は、1991年7月1日から9月16日までの期間に、一回の放映あたり広告を含めて54分、毎週一回12回で全12回の放映が行われた。時間にして10時間48分にあたる。
対象となる放映をビデオテープで録画し、分析を行った。
各放映ごとのタイトルなどは図10-2(第3章)に示してある。放映においてドラマは毎週50分の単位で終了し、週単位で完結した物語を内に含むが、それ自体が物語構造の単位とは限らない。意味的な単位は放送の枠を越えた、大きな物語に位置付けられるものである。よって以下の分析では、放映単位を基準としてはいない。
以下、「登場人物」を単位とした分析(第一節)、「用いられるモノ」を単位とした分析(第二節)、登場人物の「感情」を単位とした分析(第三節)を行う。
次に「視聴行動」について議論し(第四節)、第一節に対応する現実の人口統計調査(第五節)や、第二節に対応する「指輪」の意識調査(第六節)、第三節に対応する「結婚観」の意識調査(第七節)などを分析し、テレビドラマの意味作用について考察する。
第一節 登場人物の指標 ~主体と構造~
第一に、主体の行為に着目しながら、この「101回目のプロポーズ」を構造テクスト分析してみよう。
「101回目のプロポーズ」は「お見合い」で出会う「達郎」と「薫」の二人を主体として展開していく。
「101回目のプロポーズ」特徴として、主体の二重性をあげられよう。相互の心理描写を対等に行うことによって、物語内における「送り手」と「受け手」を、同時にかつ分離不能に表現している。
行為のレベルでは二者は明らかに対等な位置付けにプロットされている。
一方、意味のレベルでは明らかに対立している。
両者は「主体」でありかつ「客体」である。
物語の発端は「お見合い(結婚しようとする男女が面会してお互いに様子を見ること)」による出会いによって始まる。
「見合い」とは以下の3点を指し示す指標となっている。
第一に、登場人物の提示である。登場人物は男女であり、かつその時点まで全く顔見知りのない他人であったことが分かる。「達郎」と「薫」は手違いによって見合い写真を見せられていず、そのため出会いの会場で相手を間違える。同時に外見的判断材料が提示される。会話内容に登場人物の社会的背景が示されている。
第二に、登場人物の物語への態度および性格等が示される。見合いへの意識が物語における「達郎」と「薫」の役割を指し示す。見合い賛成派か「達郎」で、反対派が「薫」である。このことは同時に、恋愛における二人の態度が暗示される。「達郎」が「薫」に対して恋愛的行為を示す。「薫」は行為の積極的な受け手である。
第三に、「お見合い」は結婚を暗示する。つまり今後、展開されるであろう恋愛・結婚の物語を指し示している。一見していわゆる似合わなそうなカップルである二人の恋愛物語の始まりを、出会を自体を唐突なものとし肯定することが見合いの意味となる。「お見合い」という伝統的な出会いの様式を、きわめて近代都市的な恋愛として転換するのがこの冒頭なのである。
図11は両主人公が冒頭で提示した初期情報である。
図11 主体の初期情報
物語の素材としてのその他の登場人物をみてみよう。
物語は「達郎」と「薫」の二人だけに主体の特権を与えていない。主体の複数性は「達郎」と「薫」の二人だけにとどまらず、両者の家族/友人の併置のなかにも見られる。
彼等自体の行為は独自に機能的シークエンスを完結させている。つまりそれだけでも物語と成立しうる。ドラマ内の構造は閉ざされてはいるが、社会的構成物として「開かれた」形式(エーコ)をとっていることがわかる。
「達郎」の弟である「純平」と「薫」の妹である「千恵」とは、「達郎」と「薫」か出会う以前に同じ大学の生徒として出会っている。二人はその後は、大学の友人として、さらに次第に淡い恋心を持つニ人として描写され、「達郎」と「薫」の恋愛物語を連続させる下位構造となっている。
「純平」は「達郎」が相談を受ける部下の「涼子」に恋をする。
「千恵」は「薫」に恋をする人物「尚人」に恋をする。
「涼子」は「尚人」に恋をするが、「達郎」にも極軽い恋心を持ってている。
さらに後半に出てくる「藤井」は「達郎」の上司であって、「薫」に恋をする。
このようにテレビドラマ内で見られる社会構造は、偶然性に支配され、あるいはそれを許容する村落共同体的な小さな社会構造を示している。デュルケイムが単純な社会構造の連鎖を生物学的にとらえた環節的社会の図式であるともいえよう。図12は図式化したテレビドラマ内の関係図である。
図12 「101回目のプロポーズ」に見られる恋愛関係
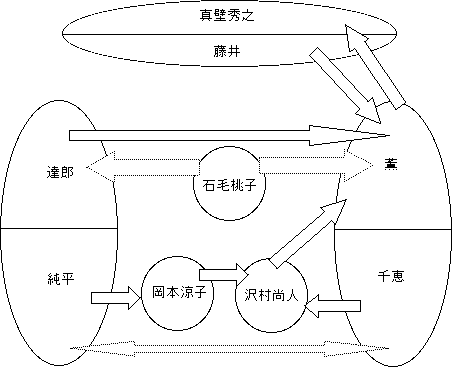
図13 プロップの行為モデル 1. 不在
2. 禁止
3. 侵害
4. 偵察
5. 引渡・漏洩
6. 詐欺
7. 共謀
8. 悪行・敵対行為
9. 仲介
10. 反作用・決定
11. 出発
12. 試練の提供
13. 試練との対面
14. 供給・準備
14-2. 魔法作用
15. 空間移動
16. 戦闘
17. 照準
18. 勝利
19. 初期不幸・欠乏の解消
20. 回帰
21. 追跡
22. 援助
23. 気づかない到着者
24. ニセの主人公の強要
25. 難題
26. 解決
27. 承認
28. 自己顕示
29. 変身
30. 処罰
31. 結婚
周囲の家族や友人などの相互交流が、出会いから恋愛成就へと移行する物語展開に、常に介在する。ロラン・バルトが物語の機能に言及したように「あらゆることがさまざまな程度に意味する」。このようにその他の登場人物は物語構造において機能的な役割を担う。
単独で意味をなさないと思われる事象も、主体および客体の上位の意味的物語に組み込まれることで意味が与えられる。
「101回目のプロポーズ」では恋愛物語が上位の意味的物語であろう。
「101回目のプロポーズ」は、物語の大部分を「達郎」の求愛と「薫」の迷いの描写に費やしている。
そのなかで、主人公「達郎」および「薫」の兄弟同士の淡い恋と友情のさまよいは、「達郎」と「薫」の物語を継続させる役割を明示することなく持つ。「純平」と「千恵」の絆が、「達郎」と「薫」を結び付ける要因となり、「純平」と「千恵」が、それぞれ別の人物と恋をすることは、恋愛による強固すぎる結び付きと、決定的な別れを回避させているのだ。つまりこうした兄弟たちの行為は物語の「補助者」としての役割を持つこととなる。さらに純枠な補助者としての「薫」の友人「桃子」や「薫」のもと婚約者の思い出など、あらゆる人物、行為、事象か物語を意味づける。行為の連関が、より上位の意昧性が付与される「シークェンス」に組み込まれて物語を形成している。
この意味で、「主人公=主体」という構造は成り立たない。しかし、意味的な構造のうちでは、主人公は物語構造の上位に組み込まれていることになる。そこで、主体の上位構造を担う主人公の二人を中心に分析していく。
上位の意味的物語である「達郎」の求愛と「薫」の迷いの場面について、いくつかの機能的な単位「シークエンス」に分割して分析を行う。
この「シークエンス」に分割のため、以下のモデルを採用する。 第一に、プロップのモデルであり、ロシア民話を31個のモデルを使って説明した(図13参照)ものである。
第二に、グレマスのモデルであり、相対する登場人物の機能を対にして類型し、適用しやすいモデルを作成していたものである(図14参照)。これは登場人物の心情や行為を、言語の文法に基づいたモデルであり、登場人物の目的論的モデルである。
図14 グレマスの行為項モデル 送り手 → 対象 → 受け手
↑
補助者 → 主体 → 反対者
この二つのモデルを用いて「101回目のプロポーズ」をテクスト分析したものを、以下に示す。
第一の単位(不在・移動・侵害・禁止)
(ストーリー)
両主体は見合いによって出会う。見合いとその後の食事で二人はまったく会話がかみ合わない。結果は「薫」からの断わりという形で締めくくられる。
(テクスト)
この場合、「不在」とは二人が出会う以前の状況である。主体の二重性のなかで、客体なき状況で主体はありえず、行為の意味は「不在」なのである。
見合いは物語行為中の「移動」である。
出会いは両者の「侵害」となる。
特に「薫」の不本意な見合いが「侵害」を強調している。過去に婚約者に結婚式当日に交通事故で死なれた「薫」にとって、「不在」への「侵害」でもある。
100回目の見合いに出向く「達郎」は相手の写真を見ていない。気の向かない見合いは「侵害」となる。
見合いの断わりが「禁止」である。
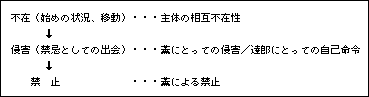
第二の単位(共謀・仲介・出発)
(ストーリー)
「達郎」は「薫」の妹から「薫の以前の婚約者」のプロポーズの言葉を教えられる。有名なセリフ「僕は誓う。50年後の君を今と変わらず愛している」だ。
「達郎」はこの言葉を「薫」が所属するオーケストラの練習場まで訪れて叫ぶ。
(テクスト)
妹の「仲介」および「達郎」との「共謀」であり、既存のプロポーズの言葉による再生産が行われる。
両主体は、恋愛という関係性を持って「出発」となる。

第三の単位(偵察・詐欺・悪行)
(ストーリー)
「薫」は動揺・感動しコンサートに来てもらうようにチケットを渡す。 喜ぶ「達郎」が知らぬうちに妹はセリフを教えたことを「薫」に話す。「薫」は怒りコンサートに来た「達郎」につめたく当たる。わけの分からないうちに喜びと悲しみを味わう「達郎」。
「達郎」は部下の「涼子」の相談を受けているところを「薫」に見られ冷たくされる。
「涼子」は「達郎」が立派に相談を果たしたことを「薫」に伝える。
見直され好期限になった「達郎」は「薫」にプロポーズするが、「薫」は突然、過去の婚約者に会わせて、と泣きすがる...............。
また「達郎」は偶然に「薫」の家にいるときに「薫の父」が尋ねてくるが、新聞の押し売りと間違えて罵倒する.........など。
(テクスト)
「達郎」の求愛が純真にも誠実にも繰り返される。「達郎」の再「侵害」である。
あるいは脇役の誰かによって「達郎」の英雄的行為が示唆されたりする。こうして「共謀」「詐欺」が実現を生む。
これに対し「薫」は感動や慰め、愛情を感じる。
しかし、その度に「達郎」の失敗や「薫」の誤解などで試みは失敗に終わる。両主体は常に「偵察者」として行為し、真実を知らぬままループに陥る。
「薫」の「禁止」によって「欠乏」という不幸を再生産する。
そして「仲介」によってフィードバックした「欠乏」が物語を振りだしに揺りもどす。
物語の脇役は一貫してフィードバック系を担うシステムとして機能している。

第四の単位(試練の提供・試練との対面)
(ストーリー)
「薫」はデート中に「達郎」の収人の話をするが、ボーナス全額を競馬の一点買いに投ぜられないような人(「薫」に言わせれば勇気のある人、かつ断りの理由だった)とは結婚できないという。
「達郎」は断る言い訳と知りなから82万円近くをつぎ込むのだった。
当然、競馬などやったことのない「達郎」は(これも「達郎」の性格を表わしていると言えるだろう。というのは競馬はこの時期の流行であったのだか、「達郎」はそのようなことには疎くかつ賭けといったような大胆なことや競馬が表彰する緻密な計算といった行為は出来ない性格である)当たらない。「達郎」のこの行為は「薫」の「お金、いっぱい使っちゃいましたね」という言葉と笑顔だけか報酬となった。
(テクスト)
「達郎」のプロポーズは「薫」にとって「試練との対面」であったが、「薫」も主体として「達郎」に「試練の提供」をする。
この要求は竹取物語的無理難題である。
「過去の婚約者に会わせて!といった要求、また嫌われないて別れたいいという「薫」の感情も一種の暗黙の「試練の提供」となっている。
試練の提供 → ← 試練との対面
第五の単位(戦い・狙い・勝利・魔法・初期欠之の解消)
(ストーリー)
「どんなにあなたか索敵であろうと好きにならない」と言われた「達郎」は、一時的に田舎(静岡)に帰った「薫」を追って行く。一瞬の気持ちの通じ合いが起こる。「薫」はそれをフィーリングと表現する。
デート中に迷子の子供を助け尊敬を得る。
「薫」が別に恋人を作り妊娠したという噂(桃子の「詐欺」による)によって誤解が起きる。「達郎」はそれを聞き、結婚していない「薫」の生活を心配し夜に工事現場でアルバイトをするのだった。
「薫」はそれを聞き工事現場に駆けつける。「薫」は「達郎」か好きだが、以前のように恋人に死なれる(愛するものを失う)ことを恐れていることを「達郎」に打ち明ける。すると「達郎」は猛然と走ってくる道路のトラックの前に飛び出す。トラックはぎりぎりで止まり「達郎」は「僕は死にません!あなたか好きだから!あなたを幸せにします!」と叫ぶのだ。
(テクスト)
物語中盤は「達郎」の求愛は成功へ向かい「勝利」が見え隠れする。
フィーリングに代表される小さな「魔法」が小出しにされる。 「狙い」の対象となったのは「薫」ではなくトラックと自己の生であった。これがマスコミで騒がれた有名なシーンであり、生を消費することで生まれる「魔法作用」である。
ここで一応二人は婚約し見合い以来続いていた「初期欠乏の解消」を行う。
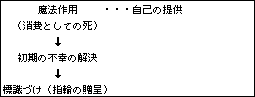
第六の単位(認められない存在・処罰・回帰・追跡・難題の解決・変身・結婚)
(ストーリー)と(テクスト)
物語後半では「達郎」の行為に対する敵対人物が出現する。それが「藤井」という人物である。彼こそが「認められない存在」だ。この敵対人物は「薫」の以前の婚約者とそっくりな人物で、「薫」とは偶然の出会いによって恋愛物語に引き込まれ「達郎」とは敵対者であるうえに仕事上の上司となって現れる。バルトのいう「あらゆることがさまざまに意味する」ように。
「薫」はたちまち「藤井」と恋に落ち、それが原因で「達郎」との確執か起きてくる。死者へと「回帰」する「薫」。
連郎は弟が祝福に渡した貯金で婚約指輪を購入するが、誤ってサイズの遵う指輪を無理やりに「薫」にはめようとする。これが恋の終わりの表象かのように「薫」は「藤井」に魅かれていく。消費の魔法作用によって求愛を表現し成功していた「達郎」への「処罰」である。
「藤井」と「薫」のキスシーンは死者へ「回帰」する「薫」であり、場面を目撃する「達郎」は自ら恋愛関係を放棄してゆくのだ。
上司との恋愛上の確執は「達郎」を退職へと導くことになる。
その後「達郎」は少年野球のチ一ムの補欠選手の逆転ホームランという場面に遭遇し、「薫」への愛をあきらめない決意をする。
達郎の「回帰」であり、「変身」のきっかけでもある。
「達郎」は「薫」が以前から求めていた夢と自信をつけるために、若いころの自分の夢を思いだし、司法試験を受け弁護士になることを志す。そしてそのことを「薫」に告げる。その時のセりフ「泣くんです。心がピーピー泣くんです(中略)・・もう一度、男としてあなたを取り返します」。「薫」はその努力を止めさせようとするが「達郎」は耳を貸さない。
「普連じゃないと思う。もう一度はだめなんだ。101回目はないんだ」という連郎のセリフは「薫」との恋愛か最後であることを示す。これが「迫跡・難題の解決・変身」である。この場合の難題は自分に課すもので対象が描かれていない、自己言及である。
その間、薫は「藤井」の離婚暦などの過去を知り、「ニセの主人公の摘発」を行っている。
「達郎」は司法拭験に合格発表の日に、合格したら「薫」が以前結婚式を挙げようとした教会に指輪を置いておくとの言葉を残し去る。発表当日、薫はコンサートの最中に突然立ち上がり教会に向かう。薫による「主人公の識別」である。
しかし教会にあったのは指輪のケースだけであった。「達郎」海で指輪を投げ捨てる。全てをあきらめて土方のアルバイトをする「達郎」のもとに「薫」はウェディングドレスを身にまとい駆けてくる。薫は道ばたに落ちているボルトを自ら自分の指にはめ、「達郎」を抱きしめる。薫の非現実的な意味での「魔法作用」である。
鳴り響くウェディング・ベルとともに物語は終幕を迎える。
↓
↓
第二節 映像的諸要素の指標 ~モノと生活~
本節では、登場人物の「住」生活という観点から、テレビドラマで用いられる「モノ」に着目し、その「モノ」ふが指し示す意味について論じてみたい。
まずは住居である。
「達郎」は私鉄沿線郊外に住んでいる。観察からすると丸の内線沿線である。
家は和風の内装の4、5階たてのマンション。
部屋を風景描写から再構成すると図15のようになる。映像として全く移らない部分もあったので不正確な部分もあるが......
4畳半の「達郎」の部屋と6畳近くの「純平」の部屋に簡単な台所、8畳ほどの台所と、ベランダがある。
「純平」の趣味がアニメという設定のためか、大型のテレビが居間に置いてある。
またオーディオはコンポサイズのものが置いてあり(「達郎」は音楽に疎いことはミュージシャンである「薫」との会話で分かるから〉「純平」のモノの多さが伺われる。
「純平」と「達郎」が20才近く年の離れた兄弟であることをも暗に指し示している。このときの恋の強力兵器である電話は「達郎」宅も「薫」宅もコードレスフォンである。
途中ではピアノが購入され、部屋はさらに狭くなる。
図15 達郎の部屋
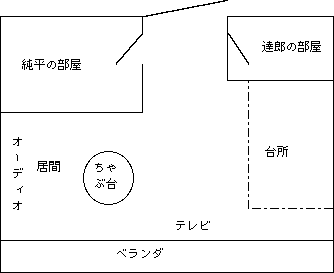
それに対して「薫」は都市住宅街に仕む。観察からすると高井戸から徒歩数分に位置する。
6、7階建ての洋風建築の高級マンションに住み、内装は豪華。
ニ人の兄弟はそれそぞれ約8畳の部屋をそれぞれ個室に使用し、間取りの広いダイニングキッチンにバス・トイレ付き。
部屋中には6か所にも生け花が、7か所に絵画が飾ってある。
大きく高級な家具がふんだんに配置されている。
不思議なことにテレビのない部屋である。
「薫」の部屋にはダブルベッドかあり、グローゼットには洋服がもう入りきらないほど掛けてある。不思議なことにテレビのない部屋である。
バスタブなどは体を延ばしてもまだ余りそうな大きいものだ。
部屋を風景描写から再構成すると図16のようになる。
図16 薫の部屋
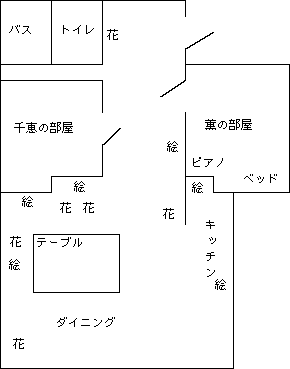
次に、登場人物の家庭における食生活を覗いてみよう。
「達郎」の家で食ベられたもの、飲まれたものをざっとあげてみると............「カツカレー、メザシ、味噌汁、ご飯、鯵の開き、コップでウイスキ‐の水割り、オレンジジュース、麦茶.............」。これをちゃぶ台の上で食べる。
「薫」の家では........「サラダ、スパゲティー、そうめん、エビフライ、ステーキ、アイスクり一ム・ワイン、ビール、紅茶、カクテル............」これをテープルで食べる。
対象的なのは、喉が乾いたときの飲み物で、必ず麦茶の「達郎」家とワインの「薫」家である。
また「ちゃぷ台」と「テ一プル」が二人の主体の対象を示す指標となっている。
外食場面はほとんどないが、異常に多い場面を見せるのが「酒」の場面だ。
この場面がない放映週はなかった。
「達郎」が一人で飲む時は赤堤灯の日本酒、見栄を張るときだけはバーに行く。
「純平」は赤堤灯の日本酒か、一人で水割りを飲む。
これに対し「薫」とその友人はもっぱらバーである。
「薫」はバーではマティーニしか飲まない。食事前も食中も食後も、嬉しいときも寂しいときもマティーニだけだ。
衣装をみてみよう。
「達郎」はサラリ一マンなのでスーツ姿か多い。でなければスラックスにポロシャッやチョッキ。家ではパンツとノースリ一プシャツだ。
純平は一貫してジーンズにティーシャツ。
これに対し「薫」は出る度に服が変わる。もしかすると同じものは一枚も重複してないかもしれない。女性出演者はみんなそうだ。
次に自動車である。
「達郎」は会社の軽のトラック(趣称軽トラ)を極たまに私用で使っている。
それに対し、「尚人」は赤のトヨタ・セリカ(一応スポーツカーである)。
藤井は白のトヨタ・マーク2である。大衆的でありなから高級車に位置する。観察によると2500c cの夕一ボモデルでこのクラス最強のモデルである。
以上の例は物語を構成する全ての要素ではないにしても、それ自体が物語の内容を表わす指標と成りうる重要な要素だ。
家屋の違いは「達郎」と「薫」の生活レベルの指標に、衣・食生活の違いは価値観の指標となっている。
つまり明らかに物語の中で特定の意味を与えられた「モノ」なのである。
住居はさておき、上記の例であげた「モノ」はドラマのスポンサーとなった企業の製品と合致していることには留意しておく必要がある。
テレビドラマで用いられる「モノ」は、「モノ」自体、そのものがそれとして持つ意味とは区別されている。
「軽トラ」も「セりカ」も「自動車」であるには変わらないが、指標として物語に組み込まれたときには「達郎と尚人の違い」という意味を持ってくる。 さらに意味は物語の構造に網目に位置付けられ、生産され、記号的な離脱となる。
付加価値的な意味合いがもともと強い「酒」のような嗜好品も、テレビドラマのなかではさらなる意味づけがなされている。「マティーニ」は「薫」の拒絶の強い意識を与えられるともに、その反転意識である「達郎」のしつこさという意味を与えられる。
一方、記号としての「ワイン」は、実在との関係を明確に示さしないドラマにおいては、視覚映像が実在としての「ワイン」を見せるんので、言語のように指標としてだけの機能に注目させない。映像に「あれ」はないのである。そのときは「ワイン」であり、そのことを否定する指標構造上の体系は見当たらないのである。
マスコミ研究において、積極的なメディアの「受け手」の存在、つまりリテラシーがあり理性的にメディア内容を解釈する主体としての「受け手」の存在についてしばしば言われている。しかし、「受け手」がいかようにも映像を解釈したとしても、そして、それが物語に与えられた意味と差異が生じていても、その解釈は「差異」そのものを明確化するにとどまる。実在としてのモノの意味を顕在化する過程なのである。それは、映像の意味生産および付与における、虚構と現実の二重の交錯、つまりシミュラークルが存在するからである。
このシミュラークルの分析によって、批判的な読者の冷静な(一般に冷めた言われる)態度こそが、既存の意味を生産する受け手像が見られるのである。それは、実はメディアによって生産された意味の再生産なのである。
第3節 感情的諸要素の指標
これまで「達郎」「薫」および登場人物、映像の構造的な役割を論じてきた。構造的役割としての分析を通じて、二人の行為が指標するものや、無意識のレベルで物語言説が表すことを読み取ることである。「101回目のプロポ-ズ」が表すものは、ダイナミックな社会の象徴、あるいはコミュニケ-ション過程のモデルと捉えることができよう。
主体の「薫」と「達郎」は物語においてそれぞれの心理的役割を持つことが分かる。心理的役割として「達郎」は「愛」の「送り手」であるのに対し、「薫」は「愛」の「受け手」だ。「達郎」と「薫」という二つの主体の行為を、愛を媒介にした相互行為とする視点で分析してみよう。
二人の「愛」に対する相互の意味付与の過程から、テレビドラマで意味づけられる「愛」の意味の差異と変化が見られであろう。これは「愛」という観念的構成体を、合意的な共通項としてコミュニケーションする主体の、ディスコミュニケーション状況の描写でもある。言語や視覚を媒介とするコミュニケーションのなかで、感情というものが、そこにいかに侵入し、コミュニケーションを規定していくのか。また、どのようなレベルでの合意をしていくのであろうか。
第1項 恋愛的相互作用の集合表象的側面
二人の行為者が指し示すものを、マクロにとらえていくと、「達郎」は「一般化された制度・社会、あるいはその根底観念でもある集合表象」として置き換えることが出来るであろう。「薫」はそこに存在した要素・個人である。つまり主体の行為は、他者と相互作用するコミュニケ-ションの象徴として考えられるのである。
物語中、一貫して変化しない「達郎」の結婚願望と結び付いた「薫」への「愛」は、社会的にある一つの制度のなかで共有されている意味、デュルケイム流に言えば「集合表象」的意味である。
結婚制度に「愛」という感情が基礎になるという一般的事実は、個人的な「愛」という感情を、一般的な「愛」へと拡大させる契機である。それが制度に組み込まれた「達郎」の「愛」である。
そして、制度的に組織的に成立していないような集合意識が、「達郎」に「薫」を無理目の女、似合わない女として扱わせるという構造にいなっている。「達郎」は制度のなかで恋愛の自由を追い求め、常に不可視の制度によって制限されている人物だ。
「薫」は恋愛を受けるという作用のなかで、その恋愛感情を変化させてゆく。「愛」という、相互作用の媒介である意味を、コミュニケーションのなかで変化させてゆく人物である。
第2項 集合表象的「愛」の記号的表出
第1項で、変化の媒介となる「愛」とは観念的構成物である。そこで、「愛」自体の意味性を行為のレベルに落として分析を行いたい。「愛」は表象され、行為として表現され、その意味を付与される言語的存在であるからだ。一方、「愛」はモノとして映像的にも表現される。
「薫」はどのような集合表象に対して作用したのであろうか。それは、表象である「達郎」自身の行為において見ることが出来よう。「達郎」における「愛」の定義は何だったのか、「達郎」が「愛」に求めたもの、その成就に求められたものを見ていこう。
「達郎」は「薫」の幸せと自己の幸せを同一化することで、「薫」の幸せを結婚と結び付けている。「薫」が「愛」にどのような形であれ「答える」ことは、「達郎」にとっては結婚そのものにあたる。「薫」の「幸せにしてください」という言葉は、「達郎」にとっては「プロポーズ」と響く。
第1に、 「達郎」の「愛」は「幸せ」である。
しかし「幸せ」は行為とはいえない。「幸せ」を満たすものがそれである。
「達郎」の「幸せ」は「結婚」である。
「結婚」はそれ自体が行為として制度化されていることは言うまでもない。
その意味で「薫」は単なる幸せの一要因でしかないのだが、「薫」と結婚することがその条件となることから、自分が「薫」を幸せにする必要がある。
「達郎」から見れば「薫」の幸せ=結婚=自分の幸せとなるからだ。
彼にとって結婚に必要なものが「愛」なのであり、制度がその集合意識を規定していく図式が見ることが出来る。結婚は「愛」という観念から自由になりつつも、すべきことになっているのだ。
第2に、「達郎」の「愛」は「手段」である。
つまり「薫」を得るために必要なもの......「手段」が愛なのだ。
彼にとっての方法は3つの内容を含む。
それは一つは「薫」を自分に引きつけること、一つは「薫」に対する献身的な態度、もう一つは「薫」の望む「達郎」に変身することである。
「薫」との仲が浅い段階では「達郎」は「薫」を「見栄」による演技で引きつけようとする。
コンサ-ト鑑賞の後のフランス料理は「達郎」が普段家で食べる「めざしと味噌汁」と対比されて見栄の象徴となる。
二人で合う場所は「ピアノのあるバ-」にほぼ限定される。「薫」の頼む「マティ-ニ」は、マティ-ニの名前を覚えられない「達郎」流に言えば「オリ-ブの串刺し入り焼酎」だった。
「達郎」は「薫」との偶然の出会いを期待して足しげくバ-に通う。
「薫」の聞くクラシックのCDを買うこと、競馬の一点買いにボ-ナスを注ぎ込むこと・・など、あらゆる見栄が愛の手段となる。そしてこの見栄は消費によって実現するのだ。
こうしてようやく第三の愛の定義が行動として表される。「消費」こそ「達郎」が定義する愛なのだ。
「達郎」と「薫」が婚約する決定的原因は「「薫」が愛するものを失うことを恐れるのに対した、「達郎」のトラック飛び込み事件」である。
自らを死という象徴的意味においての消費.......最も美しく、最も贅沢な、ボドリヤ-ルの言葉を借りれば「まさにこのことによって消費社会がその豊かさを具現するような」......におくことで、拡大再生産する愛の形を示したこの事件が、愛が消費であることを観念的に決定付ける。
婚約後の「愛」の手段を象徴するものが「婚約指輪」である。
この100万円する「指輪」はテレビドラマ後半の「愛」の動きに密接の関連する。
婚約=指輪という消費図式だけではない。
結婚に悩む「薫」に、焦った「達郎」がサイズの違う指輪を無理やりはめ込もうとする場面は、サイズの違う指輪に「愛」のすれ違いが象徴されている。
無理やりはめようとする「達郎」は、変化しない「愛」の定義をおしつける「「達郎」の規範性」を象徴する。
試験に落ちた「達郎」は指輪を海に投げ捨てて「愛」の放棄を証明する。
「薫」が「達郎」の愛を受け入れるとき.......このことが個人が社会において適合化していく象徴として物語を締めくくるのだが.......「薫」は自ら落ちているボルトを指にはめることによって、「愛」の意味としてモノの必要性、「愛」の定義としての「消費」を肯定するのだ(それまでは執拗に否定してきた)。
「私を貰ってください!」というセリフは、「達郎」の「愛」の定義である「消費」 を肯定するのである。
第3項 集合表象の受容の記号的表出
次に「薫」の「愛」の定義について分析しよう。
「達郎」と出会う以前の恋愛場面において、「薫」は自分なりの「愛」を自覚していることが示唆されている。それはおおむね、「愛」=「自分自身を幸せにしてくれるもの」という定義づけがなされている。
「達郎」とのコミュニケーションを、その定義された「愛」を媒介としていない、あるいは媒介する意味が定義された「愛」ではない、という意識のもとに、恋愛という関係性を否定する。「薫」の持つ「愛」の意味は、これまで経験的に会得してきた意味に制限されている。
達郎の行動を見て、コミュニケーションの媒介は「温情」へと変化する。「温情」は「愛」へと変化しないという確固とした自己認識を持つ。セリフでは「とにかくフィーリングがあわないの、もうあなたとは会えません」とある。この「フィーリング」とは、物語構造上では、「愛」と「温情」の中間的位置付けとなっている。この「フィーリング」、「なんとなく」といった以心伝心的意味合いである。
「フィーリング」を経て、「達郎」の献身を「愛」に意味に置き換える過程が存在する。「薫」にとっては「愛」は、自分自身を幸せにしてくれるものであり、「達郎」の献身がそれにあたったのである。
「為せば成る・夢を持って・女は夢を見たい」という「薫」の「変化」への要求が「達郎」の目標になるとき、「達郎」は職業を放り出して、弁護士になると決意する。
「薫」は「女は」といった社会的属性の価値方向性を示して、社会的価値を象徴する「達郎」に反抗・衝動の態度を示す。
その結果として「何もない、ただのおじさんですよ」と言ってしまう「達郎」に「愛」を抱く「薫」は、社会的適応過程を通じて「愛」を再定義するのだ。
第4項 互酬と非互酬の記号的表出
ここまでで「達郎」が象徴するものが、形態としての「制度(結婚を代表とする)」や、手段としての「消費」を表すことが分かった。しかし、これだけでは、社会が個人に対して適応を助長するという機能に限定した見方である。
「薫」の行動に象徴される、全体性に対する個人の要求の利己的な一面も十分に見ていく必要がある。「達郎」の愛の要求は、見方によっては、一方的な供与といえるような交換の非互酬による権力性の象徴のようにも見れる。視聴者にさえ同情を与えるような「薫」のことごとくの「達郎」への冷たい態度がまさにそれへの対抗であった。
ところで、「薫」の前に「藤井」という過去の婚約者とそっくりな人物が現われる。一度は「達郎」の「愛」を受け入れた「薫」は、過去の婚約者とそっくりな男性(純個人的欲望の対象)へ「愛」を媒介としたコミュニケーションを移していく。
この愛の移行は、形態としての「愛」と意味としての「愛」の同一視である。さらにいうなら「藤井」の存在は「薫」の二つの「愛」の意味の解釈の矛盾および葛藤なのだ。つまり、定義されたものが経験的であることと、積み重なる経験によって生成されるものとの葛藤である。
いったんは葛藤は過去への回帰によって解消される。
一方、「藤井」は存在そのものが虚構的であった。過去の離婚歴や離婚理由の嘘などがそれを象徴する。過去という非実在の、過度の美化による失望は、イミテーションとしての経験的現実認識へとたどり着く。
「薫」は、「愛」を解釈することに迷いを持つ。
これは自分自身を弱い人間であると認識することで解決しようとする。「薫」の妹である「千恵」は、「わたしは弱い人間です。そんな顔をして会いにいけばいい」と相談にのる。
もしも、最後に拾った指輪(ボルト)が「消費」とは無関係のものとして表象されており、それによって愛を価値的判断から引き離した、といった結論と解釈するなら、それは愛という観念が生成されるものではない、という考えに基づいた解釈であろう。
こうして恋愛は成就することとなるが、自己の意味解釈を一般的な形態を持つ方法に適応させつつ、満足することで可能となるのだ。
これにより「達郎」の意味する「愛」を肯定するのだ。幸せな結婚形態およびその表出である「消費」である。
つまり、そこには意味の生成があるのである。
第4節 構造から現実へ ~指標の比較研究への視座~
真実と虚偽、現実と幻想の「非差異」を受け入れることこそ、演劇が機能するための条件なのです
M・フ-コ- 「M・フ-コ-」より
これまで「101回目のプロポーズ」が提示した要素を、行為/登場人物/映像/感情にわけ、指標という観点から「101回目のプロポーズ」の意味生成過程を論じてきた。しかし、さらに論じるためには、この指標を導いた概念のコ-ド、つまり体系の存在が先になくてはならない。このコ-ドこそ現代社会を形作る集合表象であるのだ。
「101回目のプロポーズ」を「愛」の物語としてとらえると、その構造は、多くの物語が従っている「民話的」なものであるし、あるいは「神話の断章」として見ることができよう。
例えばユングの著作にある「美女と野獣」では、主体の具体的な行動を、無意識と意識に関することの束縛/解放・親切/残酷といった行動へと還元し、「美女」の行動が「精神と自然の結合」であると述べている。恋愛の形を借りない同じような構造を持った物語は多く見つけられるだろう。
レヴィ・ストロ-スは神話を次のように定義している。1つは、「太古の物語であり、事物の生成、現況、将来を記述し、それぞれがそれぞれを説明するときの秩序の連続性の確認」であるという。また2つには「一現象説明による多次元の状態の説明」と述べている。
「101回目のプロポ-ズ」を「神話の断章」と述べたのは上の定義に沿うような、それでいて現代的な事象を盛り込んだ物語であるからだ。「事物の生成」の記述とは、「101回目のプロポ-ズ」の場合、見合いから始まる社会と個人の関係の発見である。「現況」の記述とは、恋愛行動というコミュニケ-ション過程の表現である。「将来」の記述とは、恋愛成就という社会へのコミットメントの表現であり、人間の社会化という行動の社会心理学的側面を説明している。そしてこの恋愛物語は規範の権力性を「神話的」に説明しているといえよう。
神話は社会の近代化とともに解体し、爆発した。そしてその断片が気付かぬ所に散りばめられている。私たちはその断片の一つ一つを見つけ、掘り起こすことによって、かつて「神話」が説明しようとしたことを精神活動に取り込もうとする。その方法が音楽であり、文学であり、芸術であり・・・テレビドラマである。それらは規範の権力性を説明する「神話の断章」なのである。
制度化された意識、規範、道徳、思想などの暗黙の社会理論は、モノの記号化を可能にし、さらには「行為」の記号化も行う。行為は個人の精神的活動を基礎に置きながら、社会的な制限を受けつつ、相互に意味交換するような体系になる。行為はそれ自体の単純な結果だけに意味があるのではなく、上のようなコ-ドによって社会的にかつ個人的に何かを指し示す「指標」となるからである。
行為はモノと違い自然としてそこに存在せず、個人の精神活動を必要とするので個人的なコ-ドによる規定の度合いが物のそれより大きくなる。
「達郎」のあらゆる恋愛行動はある人にとっては純粋に男らしい行為として写るだろうし、ある人にとってはまったく考えられない行為に見えるだろう。しかしあらゆる人はこの物語が恋愛の物語であることは疑わないであろう。つまり「達郎」の行動は社会的行為として「現実」であり、個人的行為として「現実」と「虚構」を往復することになるのだ。
このような二つの観点から、ドラマの視聴者は、単にドラマが「物語」として「虚構」であるという認識以上に、つねに個人の精神的活動の一貫として、社会的な集合表象による規制になるような、「意味の検証」を行っているのだ。
この「検証行為」がテレビドラマ視聴のメカニズムである。テレビドラマの「現実」や「虚構」は、視聴者の社会的・個人的現実認識のあり方を表出せずには存在しないのだ。言語が体系を認識せずともそれに規定されざるをえない図式は、テレビドラマの記号的解釈=検証を行う視聴者が認識ぜずともそれによって規定されるものの存在を裏付けていよう。
さらにこの視聴者が認識をする・しないに関わらず規定されざるをえないものは、ドラマを見ること、つまりテレビのスイッチを入れた時に始めて出現する。テレビドラマ視聴という行為の記号的解釈はその方法によって、それまで認識されなかった現実を産む。ここで留意すべきなのは、それが存在しなっかったわけではないことである。
ドラマの視聴だけでなく、あらゆる映像メディアにおいて、このメカニズムによって視聴者は絶えず、繰り返し「虚構」と「現実」の検証を繰り返す。そして、「既存」の社会的構造の法則を生産し、拡大していく。こうしたメディアの機能こそ潜在的な権力として、社会的統合を実現するのである。
ドラマのような恋をしないことですら、メディアによって作り出された意味に支配されている。自由な記号体系の選択といった観点からは、そもそも自由で主体的な「受け手」という概念は成立し得ないのだ。メディアに支配された意味作用とは、強制的顕在化という「受け手」の積極性によるものなのである。
「101回目のプロポ-ズ」において何が「現実」で何が「虚構」なのかを明らかにすることは非常に困難なことになる。
そこで「愛=消費」という構造をもつことは説明した通りだが、そこおける物語内の行為や表象を、現実の行動と比較検討する。
そのために、消費者の意識を探ったいくつかの市場調査の結果を用いる。このデ-タが視聴者とは決して限らないところは、デ-タが「視聴に伴う生成された現実=シミュラ-クル」ではなく、「既存の現実」であることによって、構造と現実・実践を結ぶ判断を可能とするだろう。
そこで、指標について整理しておきたい。指標とは
第一に、一つの指示対象を持つものに与えられた記号の体系である。
第二に、物語構造において意味づけられた記号の体系である。
第三に、現実の社会生活で意味づけられた記号の体系である。
物語内の行為や表象を、現実の行動と比較検討するため、上記の3点の記号の体系の比較、指標の比較研究を行う。
そこで、「101回目のプロポ-ズ」のうち、重要な要素であり、物語構造のメルクマール的存在である、「指輪」「結婚観」を選択することにする。
上記の、「視聴者が、あらゆる指標を比較/認識しながら意味を生みだしてゆく行為」を「検証行為」と筆者は定義しておこう。第一の記号体系はドラマそのものであるから、すでに論じたことになる。第二と第三の記号体系を比較することにより、理念的な「検証行為」について考えてみたい。
第5節 結婚観の意味作用
「101回目のプロポ-ズ」では、全体としてのテ-マの中に「結婚」が重要な意味を持つ。「達郎」と「薫」は過程こそ違えども、恋愛行為の帰結として「結婚」を考えていることに違いはないからだ。
第1項 20代OLの持つ「結婚」観の現在
「101回目のプロポ-ズ」が放映された同時代を生きる若者は、「既存の現実」としていったいどのような「結婚観」を持っているのだろうか。
以下のデ-タは、「ポ-ラ文化研究所」が「20代OLの結婚観・職業観」についての意識調査を行ったものと、「総理府」が行った「女性に関する世論調査」「婦人に関する世論調査」「東京女性白書 '92」からの抜粋である。
「ポ-ラ文化研究所」の調査は1989年8月に「大都市圏の会社に勤める20代OL」を対象に行われたものである。結果は右図のようになっている。
「東京女性白書 '92」では、「結婚適齢期の有無」についての調査があるが62.7%の人が「ある」と答えている(マガジンハウス社のCLiQUE誌より抜粋)。
「ポ-ラ文化研究所」 「20代OLの結婚観・職業観」
対象数は「292人」である。その内訳は20才(8%・22人)・21才(11%・31人)・22才(9%・25人)・23才(13%・38人)・24才(17%・48人)・25才(15%・41人)・26才(10%・29人)・27才(9%・25人)・28才(4%・11人)・29才(3%・8人)となっている。
「30代で結婚したいですか」との質問には88.6%もの人が「したい」と答えている。したくない人の理由については「年齢にこだわらない(27.3%)、夫に縛られたくない(15.2%)、相手なし(12.1%)、一人が楽(9.0%)」などとなっている。
「今、結婚したいですか」という質問では「はい」と答えた人が46.3%、「いいえ」の人が53.7%になっている。「いいえ」と答えた理由は「まだ若い(39.0%)、相手なし(12.3%)、独身のうちにしたいことがある(10.3%)、夫に縛られたくない(8.9%)」となっている。
「今一番欲しいもの(自由回答)」では「お金(14.5%)、時間(14.2%)、車(10.6%)、彼(2.5%)」
「今一番したいこと(自由回答)」では「旅行(39.0%)、遊び(6.0%)、結婚(3.5%)、のんびりしたい(2.8%)」
「男に養われることは嫌か」との答えには「いいえ」が82.8%となっている。 「結婚して、子供がいて仕事を続ける女性を素敵と感じるか」では、「はい」が77.8%、「いいえ」が22.2%となっている。
「映画に出てくるようなキャリアウーマンに憧れるか」では、「はい」が36.9%、「いいえ」が63.1%となっている。「入社するとき結婚までの腰掛けの意識はありましたか」では、「はい」が30.9%、「いいえ」が69.1%となっている。
「国民生活白書」は、昭和54年の調査と「結婚観」の比較をしていて分かりやすい。
「女性は結婚したほうがいいのか」という質問で、昭和54年の調査では、男女ともに60-80%の人が「結婚したほうがよい」と答えているのに対し、平成2年の調査では、40-60%に減少している。
「女性が結婚する・しないの理由」を幾つか上げ選択させた項目がある。 内容は、「1.女の幸福は結婚にあるから」「2.精神的・経済的に安定するから」「3.人間である以上自然だから」「4.独り立ちできればしなくてよい」「5.自由を束縛するからしなくてよい」「6.個人の自由なのでどちらでもよい」である。
結果は昭和54年では、1と2の回答率が平成2年より1割高である。3は変化がなかった。6の選択肢は平成2年だけのものだが、圧倒的に他の選択肢より回答率が高い。
以上の資料を分析してみたい。
現在、女性が「結婚適齢期に30代という壁を考えていること」が分かる。
「今結婚したくない人」が53.7%と「結婚したい人」を上回っていることは、調査の対象が20前半のほうが若干多いことからも納得いくところだが、このことは25、26、27才と年齢を上げるにしたがって結婚願望が即時的・現実的になっていることを示していると言えるだろう。
20代OL達にとって「結婚」が意味することも、いくつかの質問の回答から推測できる。
「結婚」は生活上の明らかな変化として考えられている。しかしその変化の内容といえば、日常生活の変化が中心であり、視点はごく身近で、その場限りのものというか、近未来的なものでしかない。
自分の仕事は「腰掛け」とは考えていないまでも、仕事に夢や情熱を賭けるというほどのこともなく、また結婚と仕事の問題は明確になっていない。
つまり、「遊ぶ」ことや「自由」であることといった、曖昧な意味で、現在との変化を望まない一方、明確な自立意識などは持たないという、ある意味で矛盾を持つ思考である。その場限りの「遊び」や「自由」を束縛するものとしての「結婚観」は否定できない。といって経済的生活の場としても結婚を否定したりはしない。 こ
のような自己中心的な思考から、モラトリアム人間の思考が思い出される。モラトリアム(執行猶予期間)を20代と設定して、その場に居続けたいというような思考。手身近で不確かな人生設計。まるで生活のための結婚と、自分の目標を区別して、かつ結局は「結婚」しなくてはならない事実を、ク-ルに受け止めているようなふりをする。
その矛盾を埋める一時的な解決方法は、旅行に代表される「消費」である。欲しいものが「お金と時間」で、したいことが「旅行」。「旅行」はその指標として「日常=束縛からの脱出(一時的な)」を表すかのようでもある。
第2項 テレビドラマ内の「結婚」観
「101回目のプロポーズ」の「薫」にとって「結婚」とはどのようなものであったのか。薫の言説から「結婚観」を引き出すことが出来る。
薫にとって「結婚」が「恋愛」と同義として捉えられたのは、亡き「真壁」との関係においてであり、真壁の死が恋愛と「結婚」の関係を断絶させている。
次第に「(達郎と)いっしょにいると楽しいしほっとする」ということを「結婚」の必要条件と考え始める。
薫にとって「音楽という仕事」は「結婚」との対比上には存在してこない。暮らしや生活は「結婚」に影響を与えるとされていない。ただ幸せの永続(愛の成就)の象徴としてのみ「結婚」を定義している。この場合の幸せとは自他の幸せである。
象徴的意味において、「薫」の愛への欲求は、自分の愛の力の外化が、真壁の死によって、意図的・非意図的に搾取されたのである。いわば薫のヒューマニズム的な疎外をうめるものとしての「結婚」や、全体的人間の完成......失われた薫の愛の力を、埋めるべきものを探究する過程......への「結婚」に、意図的とも思えるような「消費」の概念の欠如が見て取れるのだ。この欠如が否定的とさえとれるほどに、物語は「虚構性」を強調する。あるいは「愛の感動」の影に隠されることになる。
第3項 視聴者と検証行為
「101回目のプロポーズ」の最も高い個人視聴率を持ったのは20-34才までの女性だった。彼女らが上のような、新たな「結婚」の意味に触れたとき、即ち「検証」を行う。
結婚=束縛、結婚=先の話、と考える視聴者が「薫の」「結婚」を見たとき,考えることは(当然、各自違うだろうが)どのようなことだろうか。
世論調査によれば、「結婚」は「個人の自由」と考えられている。「薫」が誰と「結婚」しようが、それは「自由」として判断される。
ところが「結婚」への考えと、「自分が結婚すること」はまるで違う。
「自由」でも「自分は30代までに結婚したい」のだ。そして「結婚への不安」は「消費」によって解決したいのだ。
「薫」の結婚はその文脈ではどうであろう。音楽つまり仕事はどうするのか、あれだけ広い家は手放すのか、本当に暮らしていけるのか........。あるいは「愛」があれば自分とは関係ない自由と思うかもしれない。
この点で、ドラマ内の「結婚」の意味には、社会における20代OL達の「結婚」観との間に、大きな「差異」がある。
この「差異」がなにであるかは各自の視聴者の違いによる。しかし、20代OL達が「101回目のプロポーズ」を「差異のある物語」として判断した瞬間、彼女たちの「結婚観=意味の体系」が顕在化されるのだ。
つまりより大きな「意味の体系」の中で、二つの体系(ドラマ内とOLの持つ意味)がお互いの「差異」によって、より大きな意味を生み出し、顕在化するということだ。それは「メディアの意味作用の体系」である。
この「認識=顕在化した意味」は、「101回目のプロポ-ズ」に触れることで起きたものであり、彼女の既存「結婚」観を浮かび上がらせる。こうして思い浮かんだ既存の「結婚」観が、彼女たちを「制度としての結婚」に向かって急ぎ足にさせるのだ。
「検証」の方法や「結果」(簡単に言えば「101回目のプロポーズ」をどう思うか)は、いかにも主体的で主意的なようでありながら、「101回目のプロポ-ズ」が提示したコ-ドの支配を受けているのである。
第4項 結婚行動の現在
結婚行動の現在を、厚生省が行っている「人口動態統計」と総務庁が行っている「国勢調査」を使って示してみよう。
「人口動態統計」では30代の婚姻数が85年から90年にかけて8万7000人から10万2000人と2万人近く増加しており、20-24才の婚姻数は逆に5万人近く減少している。
「年齢別人口(国勢調査)」を見ると、20代人口は1687万1000人、30代人口は1679万2000人と、約8万人ほど20代の人口が多い。
ここから、婚姻年齢が上昇していることが分かる。
「年齢階級別有配偶率(国勢調査)」をみてみる。
20-24才の男性(6.2%)、女性(13.5%)。
25-29才の男性(33.9%)、女性(57.5%)。
30-34才の男性(65.2%)、女性(82.7%)。
35-398才の男性(78.1%)、女性(87.3%)。
「平均婚姻年齢(人口動態統計)平成元年版」によると、東京都の男性(29.3才)、全国の男性(28.5才)、東京都の女性(26.7才)、全国の女性(25.8才)である。
以上の統計からは、女性が20代後半から30代始めにかけて、婚姻数や、結婚している人の数が、実際に増加していることが分かる。
「人気・流行=共感」でないことは明らかだが、「人気・流行=意味生成・強化」であることは言えそうである。
「101回目のプロポ-ズ」の最も多かった視聴者層は20-24才の女性だった。彼女達の「モラトリアム結婚観」は、視聴・検証行為によって、確実に強化され、行動化されているのである。
第6節 指輪の意味作用
「101回目のプロポーズ」後半において、「婚約指輪」が「愛」の象徴になっていたことはすでに指摘した。映像としては明確な「モノ」であって、指標する意味も多く持つ「指輪=宝飾品」について、視聴を通じた意味作用を考えてみたい。
第1項 宝飾品に関する消費者意識
「指輪」を代表とする宝飾品は、現代社会に生きる人々にとって、どのようなものなのか。
次の資料は「プラチナ・ギルド・インターナショナル」が「宝飾品ギフト」にかんする意識調査を行ったときのものと、「郵便貯金振興会」が「お金及び金銭感覚に関するアンケ-ト」を行ったときのものである。
「プラチナ・ギルド・インターナショナル」の調査は、「東京30Km圏」で「19-69才」の男女を対象に「1010人(女493/男517)に行われた。(91年5月)
宝飾品の保有状況は、女性全体で98.2%が平均8.7個を所有している。さらに18-29才の女性は99.2%が平均9.6個の宝飾品を所有し、女性全体の平均を上回っている。つまり「宝飾品」が女性の非常に身近で、特に若い女性においてその傾向が高いということである。
女性の宝飾品の年間受理率は全体で35.1%である。いっぽう18-29才独身の女性は67.0%と、3人に2人は何らかの宝飾品を誰かかれかから受理している。30才代になると数がぐっと減っているのがわかる。
男性の宝飾品の年間贈与率は全体で21.9%、18-29才で25.0%、30代で24.8%である。
女性がプレゼントされる機会の増大とともに、男性がプレゼントする機会も多くなっているようだ。
「愛する人の贈りたいもの(複数回答)」の調査では「宝飾品」がトップである。以下に「花束」「食事」と続く。
18-29才の女性(贈られたい意向)は宝飾品が84.4%、花束が63.1%。食事が46.7%だ。
一方、男性(贈りたい意向)は宝飾品が60.3%。花束が49.6%、食事が37.4%となっており、総じて男性の贈与意向のほうが、女性の受理希望よりも低い。
20代独身女性は91.0%もの人が宝飾品を望んでいる。一方20-30代独身男性は宝飾品の贈与意向が36.8%と非常に低い。
宝飾品の受理意向のある20代独身女性はその予算を、1-2万円が10.9%、3万円が42.2%、5万円が18.8%。10万円が9.4%と考えている。
一方、贈与意向のある20代独身の男性は1~2万円が14.3%、3万円が25.3%、5万円が28.6%、10万円が14.3%と考えている。
つまり女性は男性が考えるほど高い宝飾品を望んではいないのである。
「郵便貯金振興会」の調査は、銀座と渋谷において20-49才男女20人づつ100人を対象に行ったものである(92年1月)。
「あなたにとって大金とは」との質問に、1000万円が34.0%,100万円が26.0%、1億円が21.0%となっている。それ以上という人も3.0%いる。この時期はバブル経済全盛の時代であったことも付加しておきたい。
男女別にみると、男性は1000万円が34.0%、それに続いて1億円が30.0%、1000万円が20.0%だが、女性は10000万円が34.0%、1000万円が32.0%と同程度に存在し、1億円が18.0%、50万円以下が12.0%となっている。男女間で金銭感覚は類似しているものの、総じて男性のほうが大金の額が大きい。
「もし大金が入ったら何に使うか」という質問では「海外旅行、41.0%」「不動産購入、36.0%」「衣料、23.0%」「レジャー、21.0%」と続く。
男女別では「海外旅行」が女性では54.0%とトップなのに対し、男性は28.0%と少ない。
一方「不動産購入」では男性が46.0%とトップなにに対して、女性は26.0%とすくない。
宝飾品と答えた人は全体では6.0%、男女別では男が4.0%、女が8.0%だ。
大金の額の男女差が、使用額の違いになり、女性を消費財指向に向けているといえそうだ。
「友人・知人と食事を楽しみたい時の費用の上限」に関する質問では、男性で「5千円超2万円以内」が57.0%でトップなのに対し、女性は「3千円超1万円以内」が76.0%となっている。宝飾品ともども男性のほうが高めである。
「恋人や配偶者への誕生日のプレゼントの費用の上限」に関する質問では、男性で「5万円以内」が34.0%、「3万円以内」が32.0%と続くのに対し、女性は「3万円以内」が44.0%、「1万円以内」が32.0%となっており、「プラチナギルド・インターナショナル」の調査とも合致しているようである。
以上の結果を分析すると、女性にとって宝飾品は非常に魅力的なものであり、また一般的にもなっている。かつそれは愛の証としても魅力的になっている。
女性は男性が上げたい気持ちよりも多く貰いたい気持ちがある。
しかし女性は決して高い宝飾品を望んでいない(安いとは言えない)。
どちらかと言えば、値段は男性の「愛」の気持ちを表す方法としての意識の表出である。
女性は宝飾品を気持ちとして貰いたいが、値段として気持ちが現れることは望まない。
男性は贈与意向が低いが、気持ちとして上げたくない訳ではない。
どうせ上げるなら高いほうがといったところだろうか。
男性は、総じて支出額が高めになる。このことは支出の対象や目的の違いによって生じたと考えられる。
このように見てくると、宝飾品は、経済や文化といった体系によってその意味を決定されているようである。金・プラチナといったような自然的な特性だけでない、「愛」の証、「消費」の対象といった意味である。
第2項 ドラマ内の指輪の意味
「101回目のプロポーズ」で「指輪」はどのような意味をもったのだろうか。
達郎の購入した指輪は100万円近い値段のものだった。
なぜ買ったのか。それは婚約=指輪として考えていたからである。
婚約という「愛」の契約形態を、指輪という「消費」
財で交換しようとしたのである。
信用は利益を意味として内包するという現代社会の法則を愛にあてはめたのだ。
達郎は愛のためには指輪を贈呈しなくてはならなかったのだ。
さらに物語では「愛」の終わりを悟った達郎は指輪を海に投げ捨てる。つまり達郎にとって「愛=消費」の一つが「指輪」の意味だった。
薫は達郎の愛を受入れたものの、即形式的な行動にでる達郎を疑う。指輪は薫にとって拘束の恐怖を誘うもので、けっして「愛」の証などではない。
一方、全てを失った達郎の「愛」を受け入れる薫は、落ちているボルトを指にはめて「愛」の証とする。薫にとって「指輪」とは「指輪=金・銀」では全くなく、ただ「指輪=愛(無償の)」であった。
第3項 視聴者と検証行為
視聴者は、テレビドラマで提示された多彩な意味を持つ「指輪」に触れ、検証行為を行う。
「101回目のプロポーズ」は、従来のトレンディードラマに比べ「普通のおじさん(達郎)」が出演していて、親近感があるという風潮だった。しかし実際はどうであろう。
「愛」の証として、気持ちだけでも入っている宝飾品が欲しい女性層からみると、達郎の行動は奇異に写るだろう。
達郎は形式(指輪が表象する契約)より「愛」を重んじるべきだ、あるいは食事でもして愛を語ったほうがいい、という考えが浮かぶかもしれない。
デ-タで示した現実をみれば、どんなささいなことでも、形式だけでないプレゼント(安くても愛があるという意味、あるいはプレゼントする気持ち)が欲しい女性の心が現れている。
贈与意向の低い男性から見れば達郎の行動はまた奇異に写るだろう。なぜ、そんなにまでしてプレゼントを希望するのか?。
愛しているとはいえ指輪がそれを表さないという考えが浮かべば、それはますます男性の贈与意向を下げるだろう。
「愛」の証としての宝飾品の費用上限の高い男性からみれば薫の行動は全く奇異に写るだろう。達郎は100万円もする指輪を上げたのに、喜ばないなんて変だ!。
あんな高い指輪をあげたのだから「薫」は喜ぶべきだ、と考えれば男性は高い宝飾品を誰かを喜ばすのに購入するだろう。 デ-タで示した現実をみれば、宝飾品よりも「愛」をといった男性の意識が表出されている。実は、男性が贈与意向が低いのは、規範に忠実なだけなのである。
「かもしれない分析」であるが、これは「達郎」の行動から導かれた、女性からの「男性への行動規範」に類するものであろう。しかし、この生成された規範こそが現実を、そして行為を規定していくことになるのである。
第4項 達郎と薫の指標比較から見た消費行動
「指輪」が直接「モノ」として消費の対象になる。
「達郎」や「薫」を「消費者」として見た場合、どのような位置付けにあてはまっていたのか考えてみたい。
データとして1992年度の経済企画庁が行った「国民生活白書」を利用してみよう。
「達郎」の働く会社は「中堅どころの建設会社」という設定である。
ボーナスが「82万円(競馬の時の言説)」であるから、推定月給は「30万程度」と考えられる。
とすると推定年収は約442万円ということになる。
「薫」は「オ-ケストラ楽団員」であるが、収入等は全く不明だ。
「国民生活白書」によると「30人以上の規模の事業所で支払われた賃金」の平均は、月平均(定期給与+特別給与(ボ-ナス等))で37万2390円、年収にすると446万8680円となっている。
「達郎」は職業分類では「建設業」、職種分類では「一般事務係長」にあたる。
「薫」は「自由業」あるいは「分類不能の職業」にあたる。
1992年は全職業帯で前年比4.6%の給与の伸びを見せた年だった。
一方、消費者物価の伸びが9年ぶりに3.3%と、3%の大台を越える伸びを見せ、全体としては、生活が変化したとは言いがたい。
達郎が分類される「建設業」は「特別給与」が前年比18%増しと、最も伸び率が高く、成長を見せた分野であった。
この点、達郎は42才という年齢を考えると、決して裕福な状況とは言えない。
ともすれば物価の上昇と相まって、苦しい生活を送ることになる。
消費 消費支出の伸びを、職業別・年齢別にみよう。
「自由業」では7%、「民間企業」では9%の伸びである。
30才代では7%、40才代では11%の伸びである。
年令の要因は、家族構成や収入と関わりがある。ここから「達郎」と「薫」の家族構成分類をしておこう。
「達郎」は20才下の弟と2人暮らし。両親はいない。
「薫」は10才下の妹と2人暮らし。両親からの仕送りを貰っている。
2人とも統計上は「二人以上の普通世帯」である。
注目すべきなのは2人の「家」である。
達郎の家は「持ち家」である。さらに達郎はロ-ンが残っている(何年分かは不明)。
薫の家は賃貸だ。
「土地・家屋の所有形態別、消費支出の伸び」は、持ち家/社宅/民間借稼世帯の順で伸び率が高い。そして住宅ロ-ンの有無は伸び率と相関がないという。
「薫」は自分で家賃を払っていないので、消費支出に対する住宅費を考えなくても良い。
しかし、現実の「薫」の年代の人々の、消費支出の伸びにおける住宅費が占める割合いは少なくない。
さらに注目すべきなのは、1992年の年代別消費では50代の消費が特徴的なことだ。 50才代の消費支出の内訳は、突出して「教育費」が高い。さらに「その他」の内訳で、「(学費等を目的に、大都市圏に出た長期不在者を持つ世帯の)仕送り金」が高いのも50才代だ。平均「仕送り金」額は14万9000円(月)である。
大学生程度の子供を持つ世帯の消費支出に、大きな伸びが見られたといえる。こうして年代別消費支出の伸びは50才代がトップになっている。
「達郎」の弟「純平」も、「薫」の妹「千恵」も、同じ大学(私立)の大学生だ。
以上のデ-タを分析すると以下のようなことが分かる。
「達郎」は収入において平均より少ない上に、養う弟がいる。ところが「達郎」の年代で家を持つ家族はロ-ンの有無に関わらず消費支出が伸びていた。ロ-ン持ちで弟を大学に通わせている「達郎」の支出はかさむいっぽうであろう。
「薫」は、一般の30才代に比べ住宅費がないことから、それ以外の消費支出の割合が高くなるはずだ。さらに「千恵」の学費は両親が出しているのだから、負担はない。収入の謎に上乗せする、支出のなさ。
このような状況において、「達郎」は「薫」のために「愛=消費」をしていることになる。
例えば、「達郎」が一ヵ月間、「薫」に偶然逢おうと毎日通っていた「ピアノバ-」を考えてみよう。「達郎」は必ず「マティ-ニ」を飲んだ。カクテルの相場は店によってまちまちであるが、「マティ-ニ」はバ-において決して安くはない。生演奏つきのバ-ならチャ-ジもあろう。私がフィールドワークとして、新宿の「ピアノバ-・ダンス」でマティ-ニを一杯飲んで出たところ、請求書には1200円+1500(チャ-ジ)で2700円であった。私が他店でもフィールドワークを続けたところ、統計的には明らかでないが、この値段は高くもなく、安くもないということが分かった。「達郎」がバーに30日間、毎日通った場合を、この例で計上するなら、約8万円ほどの支出になる。
苦しい「達郎」が、「薫」を愛すると、さらに支出がかさむが、「薫」は変わらない。不均衡が募るばかりである。100万円の指輪もその一つであった。ここで「ああ、かわいそう」などという主観的な感情は出すまい。むしろそれが現実とどうけ検証されるかである。
100万円といえば、アンケ-トでみたように男性にとって2割もが大金として上げているだけの額である。バブル崩壊で大金が入っても株の購入は考えないような、消費より貯蓄指向が見られる男性にとって、達郎の行動はまさにバブルな「消費」として写るだろう。
100万円の指輪を捨てないことを考えるだろう男性を証明するように、平成景気の落ち込みが見れるのは...........実は「メディアの意味作用の体系」であったのであろうか。これは仮説として留めておこう。
「愛」は値段で計れないかのようにボルトを指にはめる「薫」であるが、現実には女性も3万円近い値段を受理宝飾品の妥当な値段と考えているのである。いくら宝飾品が値段ではないといってもボルトでは済まされない。3万円は消費されなくてはならないのだ。
第7節 まとめ
「101回目のプロポ-ズ」の構造分析を通じて、「指輪」や「結婚」だけではない、モノやあらゆる行為、物語の構造がすべて「検証」の断罪に上る。
そして、検証の基準としての社会的意識・規範を強化していく。
それはメディア内の映像の、身辺性や即自己性による、単純な現実化・行動化などではない。
メディアと人間のコミュニケ-ションの過程においての作用なのだ。
こうして顕在化された規範の類が、意識・行為の基礎となって、社会的な行動やイデオロギ-を強制する。
これこそ資本主義社会におけるメディアの機能と言えるだろう。
「消費」という規範を生産し、消費させ、拡大再生産することによる、手に負えない統一こそ「メディアの権力性」といえよう。
第6章 「東京ラブストーリー」の言説分析
「東京ラブストーリー」は、1991年1月7日から3月18日まで1回放送ごと54分を11回放映されている。1991年2月といえば、世界では湾岸戦争が勃発していた時期でもある。情報統制の意義など、メディアの在り方にも注目のいった時期でもあった。そのような時期に30%近い視聴率をコンスタントに稼ぎだしていた「東京ラブストーリー」。メディアという「場」がいかなるものかを深く考えさせるものであった。
メディアとはそもそも十字路を意味する「場」の概念である。しかし、この「場」とは、「101回目のプロポーズ」の分析で「愛」に関して何度も言及したように、概念的な構成物である。この「場」という概念は実在と存在の間を交錯し、時には認知的枠組みとなり、時にはテレビジョン・セットという機械の外枠・窓枠ともなる。「東京ラブストーリー」の内容に関してはどうだろうか。「東京ラブストーリー」は枠組みとしての「場」がいかように提示されているのか。「場」の分析を行ってみよう。
第1節 登場人物の行為分析(簡易版)
「東京ラブストーリー」も「101回目のプロポ-ズ」と同様主体を1人にした人物構成ではない。「東京ラブストーリー」の場合は4人の描写がほぼ平均的になされることで物語が成り立っている。ここでは、「場」の分析のために、若干簡易化した行為分析を行っておきたい。「」付きでの行為のモデルは、「東京ラブストーリー」の主題歌「ラブストーリーは突然に」と対応するように示してある。
第1の単位:出会い
場面は「カンチ(永尾完治)」が空港にて「リカ」(赤名「リカ」)」と出会うところから始まる。
「カンチ」は田舎の愛媛から上京して就職(中途)のためにやってくる。
「リカ」はその会社(スポーツ用品商社)の社員である。
「カンチ」は高校時代の親友である「三上(三上健一)」と連絡をとる。
話題は二人の高校時代の憧れであった「関口(関口さとみ)」であった。
「関口」は「三上」と同様に高校卒業時に上京していたが二人は数回あった程度だった。
「カンチ」が東京に来たのは卒業後5年後という設定だ。
「カンチ」以外の登場人物は既に東京にいて、「カンチ」の行動が4人を結び付けている。導入部に不在な人物「カンチ」は主体の審級の上位に位置するといえるだろう。
その後、高校の在京同窓会で3人は再会する。
「リカ」と「三上」はその同窓会の日に偶然の出会いをし4人が結び付けられる。
第2の単位:伝達・成就
恋愛関係の提示がそれぞれ対等に併置されていることから恋愛関係の順序を追って見ていきたい。
1. 「カンチ」の場合と「リカ」の場合
「カンチ」は「リカ」に高校から憧れている女性がいることを話す。それが「関口」である。「リカ」は「カンチ」の恋に協力するが、一方では恋人であるように振る舞う。「関口」の電話番号を知った「カンチ」は「関口」に接近するが、「三上」と「関口」のキスシーンを見てしまう。失望した「カンチ」は「リカ」に慰められまた告白される。「カンチ」は一端「関口」に告白するが自ら断ってしまう。そしていつのまにか「カンチ」は「リカ」に恋愛感情を抱いてゆく。
2. 「三上」と「関口」の場合
「三上」は高校の同窓会で久しぶりに「関口」と会う。「関口」はナンパな「三上」を見て怒る。「三上」も「関口」の潔癖を非難する。「三上」は「関口」に嫌われていると思っていて、「関口」は「三上」が自分の事を好きだとは思っていない。気持ちの通じたところで「三上」は「関口」にキスする。「関口」は「三上」を好きになることを恐れるが、「三上」が真面目になることをすることで愛し付き合えるようになる。
3. 4人の場合
4人はお互いの付き合いを認め、4人での「食事や温泉旅行」などで絆を深めてゆく。
第3の単位:事件その1
1. 「三上」と「関口」の場合
「三上」は「関口」と付き合いつつも、大学でクラスメートの「長崎」と接近する。「伝達」状態で二人は止まっている。「関口」は用事で「三上」の大学に行くが、長崎と「三上」の仲良くする姿を見て不安になる。また過去の女性が「三上」の家を訪ねてくる。長崎は「三上」を「待つこと」で感情を維持するが、「三上」と長崎が抱き合うのを見て、別れを決心する。
2. 「カンチ」と「リカ」の場合
「リカ」は、「カンチ」が「関口」のことを「好き」であることを知っている。「リカ」は「カンチ」が「大好き」であることから、「関口」と「カンチ」が会うのを拒まない。その結果、「カンチ」は「関口」に近づいていってしまう。さらに「リカ」のロサンジェルス支社転勤が内定する。「遅刻」なり「誤解」なりから別れをむかえる。
第4の単位:事件その2
1.「カンチ」と「リカ」の場合
「リカ」がロスアンジェルス支社転勤を放り出して失踪する。「カンチ」は「リカ」を探しに、以前「連れてゆく」と約束した愛媛を探す。「リカ」と「カンチ」はそこで出会うが、「リカ」は一人で帰ってしまう。そのまま「リカ」はロスアンジェルスへ行ってしまう。
2.「三上」と長崎の場合
長崎は婚約者がいるが、「三上」のことが好きだった。長崎は一旦結婚するが、新婚旅行を放り出して帰ってきてしまう。
第5の単位:不安/歓喜
3年後、「関口」と「カンチ」は結婚する。「三上」と長崎も結婚する。「カンチ」が偶然街で「リカ」と会うが、「リカ」は一人だった。「カンチ」は「リカ」に連絡先を聞くが、「リカ」は教えないで別れた。
第2節 言語/恋愛/記号
以上のように、「東京ラブスト-リ-」は主に4人、脇役を加えて6人の人物の行為描写から、彼らの行為の媒介であった「恋愛」という概念を導き出す物語であったと言える。
「恋愛」とは自然的な裏付けを持って存在する「モノ」ではない。それは内容や特性であって形態を持たない。であるから「東京ラブストーリー」から見られるものは「恋愛」ではなく、「恋愛という意味を作りだしたもの」である。つまり「恋愛」という記号の言表としての物語なのだ。
言い換えれば、「東京ラブストーリー」という文脈に位置づけられることによって確定された、「恋愛」という記号の生成、あるいは変換過程としての物語なのである。
ソシュ-ルは言語の構造について研究したのだが、その簡単な内容を以下の示す。
ランガ-ジュ(構造化できること、普遍的で生得的なこと)とラング(顕在化した構造、規則の総体)とパロ-ル(個々の言表)の関係は、モノをコト化する主体の活動を通じて誕生する関係である。このような関係を媒介するのが、言語という記号である。この記号は「意味するもの(シニフィアン」と「意味されるもの(シニフィエ)」を結びつける。意味は、ある体系から差異によってシニフィエを摘出すること「言表行為」によって、生まれる。
「東京ラブストーリー」は恋愛の言表行為である。であるなら、ラングを「愛」として、パロ-ルを「恋」として(これは暫定的に)、「ランガージュ」のある人間が「ラングとしての愛」を「パロ-ルとしての恋」に顕在化させていく言語的・記号的な考えができるのではないだろうか。
そこで、「東京ラブストーリー」の分析では、「101回目のプロポ-ズ」の分析とは若干視点を変えることになる。というのも構造的には非常に単純で、心理描写中心のスト-リ-であるから、「モノ」や「行為」から指標を選ぶよりも「東京ラブストーリー」の主人公達の「言説=セリフ」から登場人物の「無意識」が指標するものを分析するほうが有効であると考えれられるからだ。
第3節 主体の無意識の指標分析 ~恋愛言表の分析~
まず物語において重要な指標となる「移住」の要素から考えておきたい。
登場人物には必ず自分の育った場所が示される。
この「場」が、社会的人間の行為の基準となるものであるかのように、登場人物の行為の在り方をあらわす象徴となっている。
4人のうち、最後に愛媛から東京にやって来た「カンチ」は、5年前の思い出を忘れられない「愛媛」そのものである。
「リカ」は小さい頃から外国暮らしが続き(特に「おおぞら」が描写される)現在は東京に住み働いている。自由奔放な性格で、愛しても愛されることを恐れる「リカ」はユ-トピアとしての象徴「おおぞら」であり、またけっして定住のできない「場」を持たない人物である。
「三上」は高校卒業後すぐ東京にきて大学へ通う。「カンチ」と同じく、「関口」に好意を持ちながら、不特定多数の女性と交流を持つ「三上」はその多様さや派手な行動からも「東京」である。その後、「三上」は「関口」との別れから医者を目指し「愛媛でない東京の外側」へと変身していく。
「関口」は高校卒業後に東京に来て保母さんになる。「三上」と「カンチ」に迷う「関口」はあらゆる場に適応できる人物であり、付き合う人によって「場」が変わる。
「長崎」は東京を田舎にする人物の代表として「東京」であり、「羽賀」は東京で働き生活する人物として「東京」だ。
次に中心となる4人の恋愛言表の分析を行いたい。
第1項 「カンチ」の恋愛言表の分析
「カンチ」にとっての「愛」とは「愛媛」に象徴されるものであり、それが行為と感情になって「恋」として現れる。
「カンチ」は「愛媛から東京に移って来て高校時代のあこがれの女性に会う」というテクストの中で、また「憧れの女性を前に自由奔放な行動をする「リカ」に戸惑う」というテクストの中でのみ「愛」を「恋」として表現する。
「カンチ」は物語中において2つの「恋」をする。
「関口」に対してと「リカ」に対しての二つだ。
「カンチ」の「恋」する「関口」とは、愛媛の思い出の中の「関口」である。
思い出の中では、常に「「三上」・「関口」・「カンチ」」が同時に登場するそれは自己と他との区別なき世界における、全体としての思い出である。
つまり「カンチ」の「恋」する「関口」は、自己の中の他者なのである。
それに対して、「カンチ」が行為する現在(東京に居る「カンチ」)には、「関口」や「三上」が東京にいて、それぞれの生活や感情を持っている。
東京においては自己と他が分離していることを明確に意識させられる。
空白の5年間や環境の違い、感情の食い違いがそれを表している。
ここから、「カンチ」にとって東京での現実がどうあろうと、「関口」を「恋する」感情に代わりはないことが分かる。
「関口」が「三上」と付き合っている間も、自分自身が「リカ」と付き合っている間も、「カンチ」は「関口」に「恋」している感情を持てるのだ。
なぜなら、それは「関口」に「恋」することではなく、自分自身(あるいは自己の中の「関口」)に「恋」することになっているからだ。
「カンチ」が「愛」を「行為」として表現しない(「関口」が好きでも何もしない)のは、「カンチ」の「愛」に対する理想=愛の意味が、「他者を思いやる心」に根底を置いていることから葛藤が起きている。
この場合他者は「「三上」と「関口」」、「「関口」」、そして「「リカ」」である。
「カンチ」は理想に従って「他者を思いやる心」として「リカ」と付き合うが、自分が他者に「愛」を持たないことが他者への思いやりに反する、という考えにおいて「リカ」と別れる。
つまり「カンチ」の理想の「他者を思いやる心」は「自分が恋すること=愛を表現すること=自分の気持ちに反さないこと」に置き換えられる。「自分が恋する」対象は自分自身であるのだから、「カンチ」の言表した「愛」とは「自分自身への思い」ということになる。
図解 「カンチ」の恋愛言表

第2項 「リカ」の恋愛言表の分析
小さい頃から商社に勤める親とともに、外国を転々とする「リカ」は「故郷」を持たない。
それが象徴するように、「リカ」には一帰結としての「恋愛成就」はない。
明確な対応関係を持たないで浮遊する「リカ」は「狭い東京」にて「広大なおおぞら」を夢見る。
世間を騒がせた「赤名リカ現象」の本質はここにあるといってよいだろう。
「リカ」は「対象を恋すること」を望んでも「対象に恋される(妙な表現だが)こと」を望まない。
「恋すること」によって「愛」の存在証明をしていく。
ところが「対象に恋されること」を望まない「リカ」は、それによって自己の「愛」の欠如を示してしまう。「愛」は存在しても、決して持つことはないこと。
これが「リカ」の「愛」である。
多くの対象との「恋」(例えば羽賀との恋)を通じて「リカ」は「愛」の欠如を明確化していき、「愛」の場所を概念的に指定していく。
その概念的場こそ「おおぞら」だ。
「リカ」にとって「カンチ」との「恋」は「東京」という「場」の仲介によってのみ起きる。
つまり、自己と他の関係を維持する仲介機能として「場」があるという構造だ。
「リカ」は「場」へ準拠すること(東京にいるからという理由で「カンチ」と恋する事)でファルスとしての「愛」を、自己と他の間に関連付けることができる。
「カンチ」との「恋」のために(あるいは恋のためでなく、準拠の結果として)「場」へ準拠する。
ところが、「カンチ」にとって、「東京」とは「愛媛」との距離の差によってのみ意味される都市(つまり愛媛じゃない場所の、何処でもいいうちの一つ)でしかなかった。
概念として「カンチ」は「愛媛」にいるのである。
ここから「愛媛」という概念としての「場」が、「カンチ」からファルスとしての「愛」を剥奪する(「カンチ」は、愛媛という自分自身を含んだ場を愛としていた)。
そこで「リカ」は「愛」を「奪われた場=「カンチ」の愛の有るところ」に求めるようになるのだ。
「リカ」の「愛」は「場」に存在する=あるいは向かっていることになる。
こうして「リカ」は「カンチ」との別れの後に「愛媛」に向かうことになる。
しかし現実の「愛媛」は「リカ」と「カンチ」を仲介した「場」ではなかった。
こうして決定的な別れの後再び「東京」へ戻る。
人と人を仲介する概念として「場」を考えるとすると、「場」を持たない「リカ」が「恋」されるのを恐れる理由が理解できる。
3年後、「カンチ」が「リカ」に再会する時、「カンチ」は「関口」と、「三上」は長崎と結婚しているが「リカ」だけは一人であった。
だが「リカ」にとっての「愛」の言表行為(愛の一方通行)に、結婚という形態(愛の相互交通)は存在しないのである。
図解 「リカ」の恋愛言表
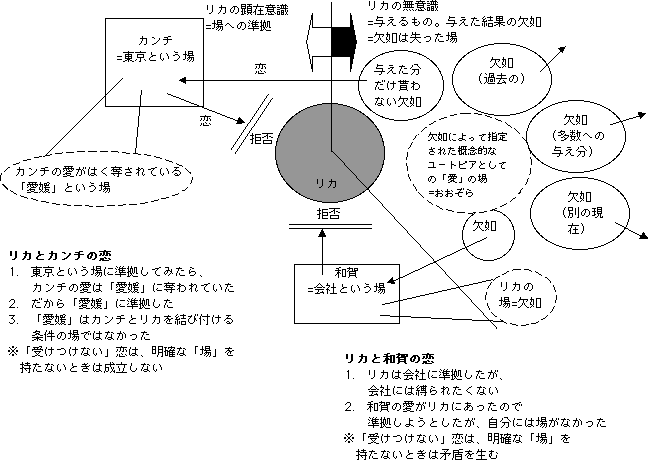
第3項 「三上」の恋愛言表の分析
「三上」は親を筆頭に、田舎つまり「愛媛」を嫌っている。
その理由は示されない。
「三上」の親は金持ちであり、「三上」も「東京」では結構な暮らしをする。
「三上」は私立医大に通っているが、それは親に金を遣わせてやりたいという反感であることだけが示されている。
ここから「愛媛」に対する理由なき反抗は、「東京」の「三上」の感情を支配していることが逆説的に理解できる。
「三上」にとって「愛媛」を土台にしてのみ「東京」が存在するのだ言葉を変えるなら「愛媛」との差異によって「東京」の意味が決定されているのだ(これは「カンチ」も同じだ)。
このことは「三上」の卒業後の夢が地方の医者になることからも、潜在的に汲み取れるのである。つまり「東京」が好きなのではない。
「三上」にとって、「東京」における「くだらない女たち」とのつきあい(これは「遊び」)は、「近づきも遠ざかりもしないもの、だから(自分を)縛ることの出来ないもの」としての「思い出としての「関口」」への反抗の帰結である。
「思い出としての「関口」」はまさに「愛媛」が象徴している。
「愛媛」への反抗となるものが恋愛言表なのだ。そのことが「東京」における「三上」の「誰とでも寝る遊びの恋」として表現される。
つまり「三上」にとって「愛」は「近づきも遠ざかりもしないもの、だから(自分を)縛ることの出来ないもの」であり、「縛る」ことへの「反抗」として、近づいては遠ざかる不特定多数の女性と交流を持つのだ。
「関口」も長崎もその一つである。
「三上」は「近づきも遠ざかりもしないもの」に自ら「近づく」ことによって、東京での「遊び=恋」を支配していたコードとしての「愛」を行為化する。
それは「三上」が医者となって地方へ赴任し長崎と結婚したことが表している。
図解 「三上」の恋愛言表

第4項 「関口」の恋愛言表の分析
「関口」は愛媛時代に親がラブホテルを経営していたことから、その反発として異常に恋愛的行為に対する嫌悪感を持っている。
このことから「関口」は「三上」との「恋」を嫌悪することになる(「三上」の恋は、すなわちSEXに結びつくものだった)。
ところが「三上」の「恋」は「愛媛への反抗」である。
「関口」は愛媛の思い出をいつまでも大切にする人物として、「三上」の「恋」に嫌悪する結果として、「愛媛への回帰」つまり「「三上」を愛する」ことになるのだ。
「東京にいて愛媛に回帰する」という矛盾は二人を別れさせる。
「二人(「三上」と「カンチ」)が仲良くしているのを見ているのが好き。ずっとこのままでいたい」という「関口」の言葉は、愛を「愛媛」で象徴していた「カンチ」に向けはじめることを示す。
「関口」は「寂しいのとか悲しいのとか、ヒョイっとすくい上げてくれた」「カンチ」を、「リカ」への純粋に献身的な態度から評価を高くしてゆく。
「関口」にとって他への「恋」も、自己への「恋」も同じように「愛」と考えている。
つまり自己から他へのコミュニケーションも、他と他のコミュニケ-ションも、本質が同じならば形態も同じものとして判断するのだ。
だから「関口」にとって過去の傷を癒す本質が「愛」であり、その方法が「恋」となるのだ。
図解 「関口」の恋愛言表
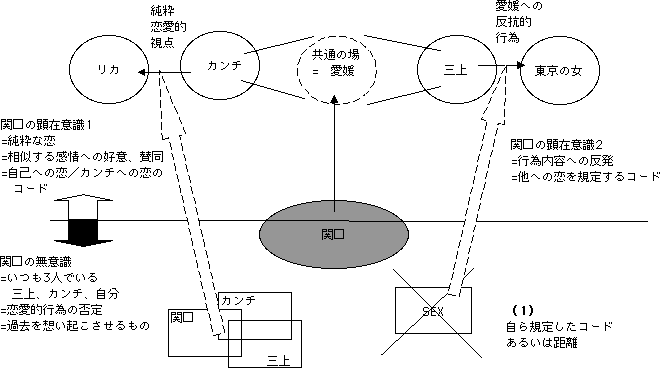
第4節 試聴の「場」についての一試論
本節は「東京ラブストーリー」の試聴という行為を通じた意味作用について論じる。第3節で述べたような「場」の指標と、メディア視聴という「場」の指標を対応させたいという試みである。しかし、この点に関しては、本卒業論文の作成において時間切れになってしまったので、一試論ということにしておきたい。いずれ、本格的に試みてみたいものである。
さて、「東京ラブストーリー」を視聴者が見るという行為は、以下のようになるといえる。 1. 「東京ラブストーリー」を、ある意味の表出として、その記号をとらえる。
2、とらえた記号を、自分が持つ意味の体系=ラングという構造に代入する。
3、構造のなかで意味を判断・検証する。
テレビドラマは視覚情報である映像と聴覚映像である言語によって意味を表出している。視聴者はあらゆる経験から、ラングを構造化して持ち合わせている。
テレビドラマも人間もそれぞれ独立してその潜在的構造を持ち合わせている。人間は視覚を持ち、テレビドラマは映像を持つ。これに関しては、テレビドラマを視覚するしないに関わらず、当該の潜在的構造は存在する。
しかし、潜在する本質だけであるテレビのスイッチを入れたと同時に、ドラマの言説は視聴という文脈の中に位置づけられて、意味生成の言表「パロ-ル」と化される。
これまで「東京ラブストーリー」における登場人物の行動から見てきたものは、「愛」という意味を「行動・心情としての恋」に変換する過程であった。
視聴者にとっても、「愛」という意味は視聴行動によって提示される。しかし映像や言語を駆使したドラマも、「愛」というものが実態のない概念であることを隠せない。「東京ラブスト-リ-」において、「愛」の象徴としてのモノが存在しても、「愛」という実質が映像で現れることは決してない。状況に合わせて「愛」という意味を文脈によって置き換えるような変換が行われているのみである。
その変換過程の一つが、視聴という文脈であることは、「愛」が「東京ラブスト-リ-」の中にしかないものではないことから理解できる。
つまり「カンチ」達が「愛」をパロ-ル化したことと、視聴によって「愛」を判断することは、記号の変換のレベルの差の問題である。
ここで以下のようなことがわかる。「愛」という本質が形態として存在しないがために「パロール」としての「恋」が「愛」と認識される、あるいは「愛」を意味していることになっている。「東京ラブストーリー」において「やさしさ」や「SEX」が「愛」として語られていたようにだ。
ならば視聴という、「他」としてのメディアとのコミュニケーションにおける「愛」の検証行為は、視聴者が「パロール」として「恋」を表象する過程と言い換えてもよい。
「愛」が意味を表現しようとするとき(それが恋であるとする)それは差異化を生む。それは、意味のレベルの差異であったり、自己と他という差異であったりする。これによって、コミュニケ-ションにおける「愛」の意味作用が生まれる。
この差異の空間を、より小さく、より狭くさせるもの。これが「場」である。
「東京ラブスト-リ-」の「場」は、自己と他を同化(狭さゆえ、鏡には奥行きがないゆえに)させたり、関係を仲介(出会うには、囲い込みが必要なゆえに)させたり、明確に指示するものを持つものとして(空間はすでになく1対1対応ゆえに)差異を作りだす........といった機能を持っていた。
つまり意味は「場」があることによって、生産されるのだ。「場」がなければ、意味は構造の網の目に迷い込んだら最後、再び出てくることはない。
視聴者が身を置く「場」とは何処か。もはや言い尽くされた電気の村でもなければ、「送り手」という資本主義のビルディングの中でもない。視線と意味が複雑に混じり合う視聴行為という、差異化と検証の渦型のピラミッド。ここである。
第5節 「東京ラブスト-リ-」の分析を通じて
「東京ラブストーリー」の分析を通じて、物語の意味作用を「恋愛」を例に説明したのだが、それは「視聴」という「場」にまで物語の意味作用が関与していることの分析でもあった。
こうして、メディアと意味の関係を考えてゆくと、メディアは、実態として存在しない限り、意味を実質的に持たないような全てに対して、視聴を意味そのものへと導くようにさせるのではないか、という結論に達せざるをえない。
つまり、視聴という行為が意味作用の根本的な規範としての役割(つまりラング・構造としての役割)を与えられることになるということだ。
「東京ラブストーリー」において登場人物が「存在しない愛」を「場」に移植して「恋」として言表したように、視聴者は「存在しない愛」を「テレビという、あるいはそれを視聴するという場」に移し替えたのだ。
メディアに意味生成の機能が付けられることによって、意味するものと、意味されるものの格差が意識的に、あるいは無意識的に拡げられることになる。実質と形態の対応関係さえも、メディアの操作(意識的な、あるいは無意識的な)の中に含まれることになる。するとメディアを支配する社会的コ-ドが意味生成を支配することになる。
それはまさしく資本主義的精神の再生産であり、経済的な要因の直接の有無とは関わらない、「恋愛」や「友情」といった感情までもが、思考や言表、態度、反応などの形で再生産されるのである。
視聴者がそれらの意味生成に了解するしないに関わらず、その支配の性格は変化しない。たとえ同意の上の認識でも、支配的強制がそこにあることには変わりはないからである。
第7章 おわりに
私がこの論文を書く直接のきっかけとなった理由は、実はほんの些細な出来事だった。
※
それは私が友人とのドライブを楽しんでいた時の事だ。夜の街を意味もなく徘徊する、そんなゆったりとした時間の流れを、軽い語らいと共に感じていた時の事だ。 言葉に疲れると手はカ-ステレオに向かった。夜の街と車と歌。この3つが揃わなくてはならない。皆が歌いだした。夜明けのなかでかかった曲に「SAY YES」があった。
この時である。友人の一人が冗談で「SAY YES」を歌い終わったと同時に、「101回目のプロポ-ズ」を提供していた会社のCMメロディ-を歌い始めたのだ。車の中は笑いの渦に包まれた。そう!思い出してみると、主題歌が流れ終わった後には、必ず同じCMが流れていた。順番も内容も、である.
※
その時冗談だった事は、そしてその時の笑い声は、確かに皆の一歩醒めた感覚を浮かび上がらせていた。楽しさに隠された目に見えない力、一瞬の笑いと引換えに盲目にも受け渡している何かを、薄々と感じ取っていた。
これといって何の魅力もない、耳をとらえない音の宣伝が、「SAY YES」と共に冗談になる。今では、もう覚えてもいないだろう商品や会社名。「101回目のプロポ-ズ」は、そんなことさえも主題歌にしてしまった。
私も友人も、決してそのCMメロディ-を覚えたかったわけではない。広告効果に影響されたとも思っていない。CMなんて好きでも何でもない。とはいえ、彼の冗談に気付いてしまった。笑ってしまった。記憶の沼に沈みかけていた広告が、「101回目のプロポ-ズ」とは全然関係のないあの広告が、脳裏に浮かんできてしまった。
私たちは何を歌っていたのだろう。もはやラブソングでなくなった「SAY YES」か、広告機能をなくした音の宣伝か。マグリットならこう言うだろうか。「君は歌っていない」と。
唇を動かせば溢れ出るメロディ-。体を動かせば揺れ出るリズム。会話のハ-モニ-。「音楽」はこんなにも簡単に見えて、「歌」わずにはいられない。しかし、「歌うこと」は決して簡単なことではない。投げつけてくる意味の矢から身をかわしながら、時には意味の沼に溺れないように、時には意味の森に迷わないように、「音楽」すること。それが「歌うこと」だ。
カラオケボックスには意味の監獄に閉じ込められた「歌」達が、面会を待っている。デパ-トにはサラリ-マンとして働く音楽が、役目という意味を遂行している。そして、テレビの絵本を開くと、「感動と共感」が翻訳されている。
歌っていると思っている人は、歌わされていたのだ。意味に縛られた私の友人が、笑いをとるためにCM音楽を口ずさまなくてはならなかったように。
※
ドラマの虚構/社会の現実という対立を越えて、全てのモノや行為を意味の体系に縛ること。これこそ権力の概念だ。そして権力の「場」は確実に存在している。民主主義の根源は「場」を均等に分配することだったはずだ。ところが、「合理化」「労働と生産」「消費」「愛」「趣味」「価値」などの、社会的精神や個人的精神の意味を作りだす体系は、権力を中心化している。
権力は、核の恐怖や暴力、支配/被支配の関係などだけに存在するのではない。点在する権力をまとめる「場」がある。それは民主主義をあやつっている力なのだ。 よく考えれば、私たちは生まれたときに、既にあらゆる意味の体系に位置づけられていたのかもしれない。客観的で完全な自由など、ユ-トピアでしかないのかもしれない。しかし、それが利用されていることは、全く別問題だ。全ての人々が、同じように思考・判断したり、同じようなモノが溢れたり、同じような場所で、同じような行為をする光景は、そら恐ろしい。これは意味のファシズムとでも言えるのではないだろうか。
※
私はこの論文を通じて、決して流行現象やメディアを積極的に読み解く「受け手」像を否定しているわけではない。実際に、私は「101回目のプロポ-ズ」も「東京ラブスト-リ-」も生で体験した。見ている時は楽しかったし、感動もした。泣きそうになったときも・・。私なりの解釈をし、私なりの視聴スタイルで、それを体験した。
ただ、誰もが同じようにトレンディ-ドラマの曲を聞いていたり、ドラマのような恋の話ばかりしたりすること。あるいは、盲目にも、売れているからといって、トレンディ-ドラマの主題歌だったという理由だけで、商業音楽に口を塞ぐことや、芸術/大衆の価値判断からだけで、物語を「開かない」こと。このようなことに触れるに従って、私は流行現象の弊害や、メディアを積極的に読み解く「受け手」像という知的な傲慢さを感じていた。
好きなことにお金をかける人のことも、それを使って儲ける人のことも、私の思考の対象外にある。「だます・だまされる」は表裏一体だ。しかし、権力に支配された「意味」を使って、判断した思考を押しつけること、これは見破らねばならない。その批判の一つ一つが、メディアを積極的に読み解く「受け手」像という、理念型ではない実態を照射するに違いにない。
※
※
「SAY YES」と「ラブスト-リ-は突然に」から意味を解き放って、もう一度、耳を澄ませてみよう。きっと大切にすべき宝石のぶつかり合う音が聞こえるはずだ。しかも宝石箱に入れたままの宝石ではない、大切に身にまとっている宝石の音が。
終
special THANX to.......
- Seigo Yamanaka
- Atushi Katayama, Tomo Ochiai, Chigusa Ito, Mr.Kanai, Mr.Yazaki, Kumiko Sato, Yukiko Ushikosi, Mr.Oochi, Mr.Kawazoe
- Fumiko Kikuchi
- Hironobu Takahasi, Hiroyuki Nakamura, Yasumasa Ohizumi
- Katuhiro Iwama
- Seiji Kimura, Sachiko Kitamura
- Jun Takahashi
- MUSiC JUNCTiON,beat club,seijo univ,Laser TX-R,audi gle,hutari-no-coffee-jinn,video research
- Natsuko Sekizawa
- Taku Ariyasu,Tuyosi Ohwada,Yasuhiro Ida
- Kyoko, Yumiko, Koujun, Miho, ,Rituko, Megu
- Takato Kuwahara, Hidekuni Shida
- Akira Masuda, Takahisa Suzuki
Get In Touch.
よろしければお気軽にメッセージをお寄せくだされば幸いです。
ErrorYour message was sent, thank you!